浅野英之(弁護士)– Author –
-

預貯金の仮払い制度とは?必要書類や手続きの流れ、上限金額について解説

-

相続において葬儀費用は誰の負担?遺産分割の対象外であり喪主負担が原則だが例外もある

-

夫婦で自宅を共有しているときの相続の注意点は?

-

遺言書とは?無効にならない書き方と例文、メリット・デメリットと注意点

-

離婚した親の相続はどうなる?親が離婚しても子供は相続人になる!

-

扶養型の寄与分とは?認められる要件について詳しく解説します

-

後継者がいない会社が直面する問題と対策について解説

-

相続分の指定とは?法定相続や遺産分割方法の指定との違いも解説

-

配偶者居住権とは?要件とメリット・デメリットをわかりやすく解説

-

法定相続人がいない場合の手続きは?相続人不存在だと遺産は誰のもの?

-

遺言書を勝手に作成されてしまったらどう対処すべきですか?

-

遺産の独り占めは違法?独占されたときの解決策と事前の防止策

-
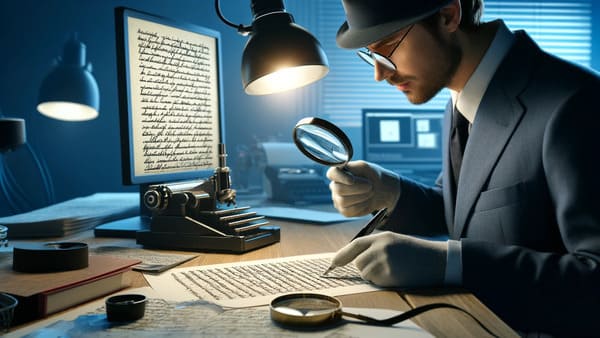
遺言書の筆跡鑑定の方法は?遺言書の筆跡が違うときの対処法

-

相続法改正のポイントは?変更されたルールと注意点をわかりやすく解説

-

特別寄与料とは?計算方法と相場、請求の流れと期限について解説

-

養子縁組すると相続に影響する?メリット・デメリットと相続人の範囲の注意点

-
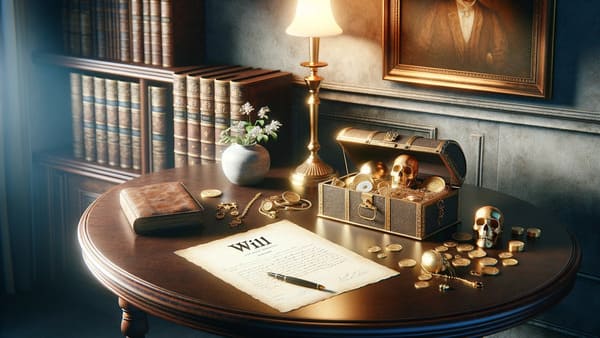
遺言書を撤回する方法は?撤回後に変更する手続きも解説

-
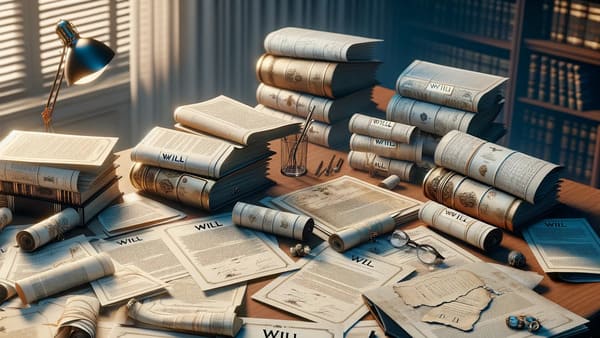
遺言書が複数見つかったら効力はどうなる?有効性や優先順位の判断基準

-

相続放棄してほしいと言われたらどう対応すべき?

-

遺留分の放棄とは?生前に放棄する方法と相続における手続きを解説

-

相続放棄は撤回できる?相続放棄の取消しが許されるケースについて解説

-

相続手続きの期限はいつまで?期限内に終わらせる方法と過ぎたときの対処法

-

デジタル遺品とは?相続に備えた生前整理とトラブル回避のポイント

-

子どもがいない夫婦の相続のポイントは?トラブルと対策を解説

-

生命保険金と遺留分の関係は?生命保険は遺留分侵害額請求の対象になる?

-

事業承継と廃業のどちらが最適?メリットとデメリットの比較や注意点

-

後継者の育成が承継を成功させる鍵となる!具体的な方法や戦略を解説

-

遺言執行者とは?役割やメリットと選任する方法を解説

-

事業承継の専門家とは?種類と役割や選び方のポイントを解説

-

相続の専門家とは?選び方とそれぞれの役割について解説

-

子供に相続させたくないときにすべき対策と6つの方法

-

相続で委任状が必要なケースと委任状の書き方

-

相続放棄してほしいと言われたらどう対応すべき?

-

清算手続き中の会社ができること、できないこと

-
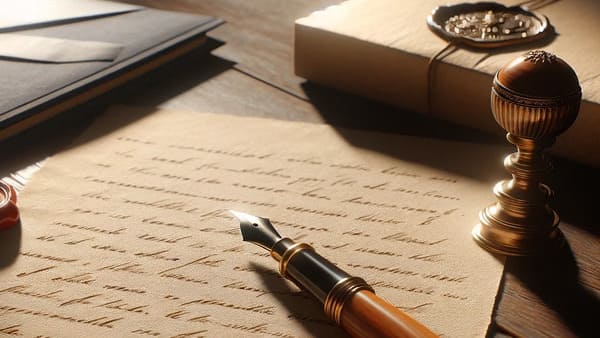
遺留分侵害額請求の通知書の書き方と、内容証明の注意点【書式付】

-

会社を放置すると危険?休眠会社のメリット・デメリットと注意点4つ

-

遺言書に書いた財産がなくなった場合の対応は?書き直さないと無効?

-
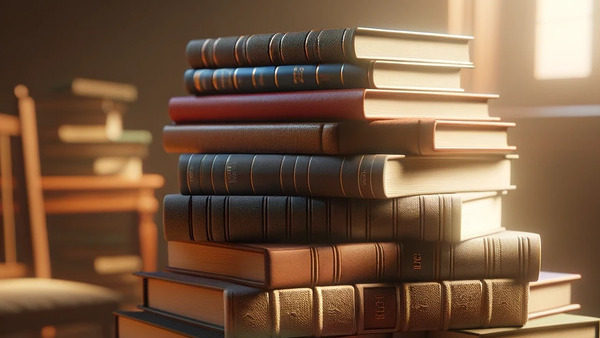
改製原戸籍とは?入手方法と相続手続きにおける利用法

-

遺言書を勝手に作成されてしまったらどう対処すべきですか?

-

遺産分割協議書とは?作成方法と注意点を解説【書式付】

-

亡くなった人の連帯保証人だと相続放棄できない?4つの対応

-

会社をたたむ方法3つ!解散・清算・破産の違いとメリットの比較

-

相続財産目録とは?作成方法と書き方の注意点【書式付】

-

外国人の相続人がいる相続手続きの注意点

-

超過特別受益とは?法定相続分を超える利益を返還する必要はある?

-

相続した連帯保証人の保証債務に消滅時効はある?

-

相続放棄したら督促状は放置しても大丈夫?すべき対応を解説

-

不動産売買における仲介と代理の違いについて解説

-

前妻の子・前夫の子も相続できる?財産を与えない方法はある?

-

いとこが亡くなったら遺産を相続できる?いとこが相続する方法は?

-
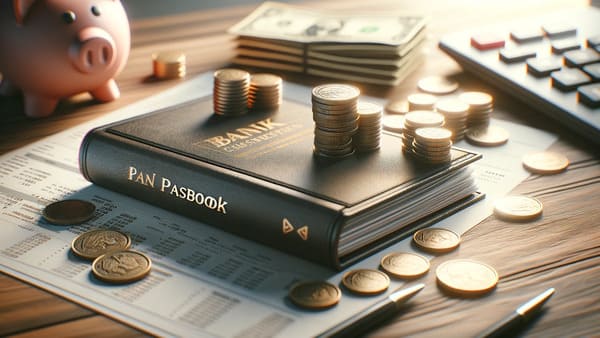
相続財産となる預貯金はどのように調査すればよいですか?

-

相続放棄と自己破産はどちらがよい?違い、判断基準と注意点を解説

-

夫婦で自宅を共有しているときの相続の注意点は?

-

相続財産に債務(借金・ローン)がある場合の遺留分の計算方法は?

-

生命保険の受取人が死亡していたときの対応方法と注意点4つ

-

連帯保証人の保証債務を、複数人で相続したとき、どう分割する?

-

換価分割とは?分割時の注意点6つと不動産相続の注意点

-

口約束の相続は有効?口約束した遺産をもらう2つの方法

-

相続した不動産の調査方法と、探す時の注意点を解説します

-

第三者対抗要件とは?不動産の取引や相続において問題となるケース


