事業の未来を決める重大な選択、「事業承継」か「廃業」か。どちらが企業の未来にとって最適なのか、覚悟のいる決断です。この判断は、経営者の将来を決めるだけでなく、将来の展望、従業員や取引先など関わる全ての人に影響します。
今後のあなたの信用をも左右するため、中途半端なことでは再起業や転職などに悪影響なおそれもあります。事業承継は、経営のバトンを次世代に渡し、ビジネスを持続的に成長させる方法、一方で廃業は経営にピリオドを打ちますが、あなたの人生にとっては新たな出発となります。どちらの選択にもそれぞれ意味があり、メリットとデメリットを比較する必要があります。
本解説では、事業承継と廃業の意味の違いと、そのメリット、デメリットを理解し、どちらを選択すべきかを決断するための知識を提供します。
事業承継と廃業の違い
事業承継と廃業は、企業経営においていずれも必ず存在する重要なプロセスです。
しかし、どちらを選択するにせよ、社内外の関係者に多大な影響を与えるため、覚悟をもった経営者の決断が望まれます。まずは、事業承継と廃業のいずれを選択すべきかを決断するにあたり、それぞれの選択肢の持つ意味について解説します。
事業承継とは
事業承継は、企業の経営権を、現在の経営者から次世代に移行するプロセスです。事業承継では、経営の継続性を保ちながら、理念や文化、戦略を後継者に伝達します。その方法には、親族内承継、社内承継のほか、事業売却(M&A)を活用する方法もあります。
将来も長期的に存続し、成長を続けるための選択肢であり、その理由には、経営者の高齢化や死亡による相続といったものがあります。
事業承継の基本について

廃業とは
廃業は、企業がその事業活動を完全に停止し、撤退することを意味します。その理由には、業績の悪化や後継者不在といった外的な要因のほか、経営者のモチベーション低下といった個人的なものもあります。
廃業した場合は、基本的には法人は解散し、清算します。事業を終了し、債務を清算、従業員を解雇した後、残余財産を株主に分配して、会社を閉じます。従業員にとっては職を失いますし、取引先にとっては契約を終了されるため、周囲に大きな影響を与えます。
通常清算の方法もありますが、債務超過の疑いがある廃業では、特別清算や破産といった法的手続きによって債務を整理しなければなりません。
会社をたたむ方法について

事業承継のメリットとデメリット
上記に説明した2つの選択肢のうち、事業承継の持つメリット、デメリットを解説します。事業承継は、多くの企業にとって大きな節目となりますが、潜在的なリスクを見逃さないことが、最良の選択肢をとるためのポイントです。
事業承継のメリット
ビジネスを継続できる
事業承継は、これまで企業が長期に渡って運営してきたビジネスを継続することができます。業績が悪化していたとしても、廃業するのでなく経営を引き継ぐことで、新経営者による新しい風や、事業売却(M&A)による他業界の知見が、新たな成長に繋がるケースもあります。
従業員の雇用を保障できる
社内的には、事業承継を選択すれば、従業員の雇用を保障できるメリットがあります。優秀な社員は、企業にとっての資産となり、承継後の新たな発展が見込めることもあります。一方で、廃業する場合の突然の解雇やリストラは、納得を得ながら進めなければ企業の信用を悪化させます。
顧客との信頼関係を維持できる
事業承継を円滑に進めれば、顧客との信頼関係を維持できます。このことは、経営者が承継後に次のビジネスを起こすときや、今後の人間関係にとって大きなプラスとなります。
家業の価値を維持できる
家族経営の企業だと、廃業してしまえば家族の収入が永続的に絶たれてしまいます。事業承継によって経営を別の人に任せれば、自分が経営しなかったとしても家族の資産は維持できます。
事業承継のデメリット
後継者の選定が難しい
事業承継では、最適な後継者が成功の鍵となりますが、そう簡単にみつかるとも限りません。誤った選択は、承継後の未来にとって悪影響です。親族や社内に適任者がいないとき、早めに後継者育成に着手するか、事業売却(M&A)の活用も検討すべきです。
相続トラブルを引き起こす
家業やオーナー一族の承継などの場合、経営者の死亡によって始まる相続と密接に関わります。このとき、後継者の選定、株式の奪い合いや資産の取り合いといったトラブルが、事業承継に影響します。感情的な対立が大きいと、スムーズな継承が難しくなってしまうおそれがあります。
経営の継続性に支障が出る
事業承継において、現経営者と新経営者とは、全く同じ考えを持っているわけではありません。新しいリーダーが、新たな経営方針や理念、ビジョンを持ち込んだ場合、社風や古株の社員などとの間で衝突が起こり、継続性をもった経営ができないリスクがあります。
財務状況の悪化が立て直せない
事業承継の場合は、廃業と異なり、法人として連続性を持っているため、これまでの負債を引き継ぎます。業績悪化によって事業承継か廃業かを選択しなければならない場面では、その影響が尾を引くと、経営者を変えても、財務状況の悪化を立て直せない危険があります。
廃業のメリットとデメリット
次に、廃業を選択した場合のメリットとデメリットを比較し、そのビジネスへの影響を理解しましょう。廃業はできれば避けたいという経営者が多いでしょうが、長期的な目線で理解すれば、メリットも十分にあります。
廃業のメリット
財務的負担を解消できる
廃業をすれば、基本的には会社はなくなるため、これまでの業績悪化や損失、借入金の返済に悩む必要はなくなり、財政的な負担から解放されます。承継する価値のあるビジネスがなく、後継者もいつ借りづらい場合には、廃業は有効な選択肢となります。
新たなスタートを切れる
廃業は、経営者にとって「人生の終わり」ではありません。確かに長く続けてきた経営に一旦終止符を打つのは辛いでしょうが、新たなキャリアや事業の機会を得るチャンスでもあります。廃業すれば、次の道は、現在のビジネスモデルにこだわらずに探すことができます。
廃業を怖がるのでなく、長期的な視野に立って検討することが大切です。
廃業のデメリット
従業員に悪影響がある
廃業は従業員にとっては失業を意味し、その生活に大きな影響を及ぼします。特に、社会的な責任のある大企業にとっては、解雇は重大な決断です。
顧客の信頼を喪失する
廃業によって市場から撤退すれば、長年にわたり構築してきた顧客との信頼関係は失われます。認知度の高い企業の場合には、ブランドイメージを失い、金銭以上の価値が損なわれる可能性もあります。
清算手続きが複雑である
廃業時に行う清算の手続きは、負債を清算し、残った債務を免責するといったプロセスを含むもので、不利益を受ける債権者の保護の必要性などから、煩雑な手続きが要求されます。また、経営者が個人保証している場合には、個人としても破産しなければ債務を免れられません。
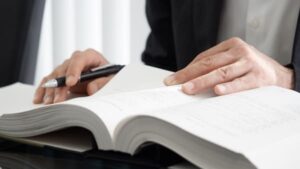

事業承継か廃業かを決める判断基準
事業承継と廃業、それぞれのメリット、デメリットを理解したところで、現在の状況にあわせてどちらが将来のためになるか、その判断基準を解説します。
経営者にとって、どちらを選択すべきかを一概に決めるのは難しく、市場環境や会社の財務状況、承継者の有無、ビジネスの将来性とおいった様々な考慮要素があります。
会社を継続できるか
企業の財務状況を分析し、事業を継続することが可能かを評価してください。負債が多すぎる場合や、収益性が低い場合には、廃業が適切な選択肢となります。このとき、市場における自社の地位が参考になります。
自身で経営を続ける前提の検討だけではなく、事業売却(M&A)などによって追加の投資をしたときに期待されるリターンなどもあわせて検討しましょう。社外への承継も含めて検討しても、会社の継続が困難ならば、廃業の選択が適切です。
事業価値が高いか
次に、事業の将来性についても検討してください。その市場全体が成長しているのか、それとも既に飽和しているのか。成長市場であれば、あるいは、自身のビジネスに競合優位性があるのであれば、事業承継によって再浮上し、成長することができる可能性があります。
一方で、縮小市場であったり、競合がひしめくレッドオーシャンの場合、廃業して新たな戦略を立て直すのも有効な手となります。
相続トラブルの危険がないか
会社の株式は、財産的価値を有し、一方で、企業経営について重要事項を決める決定権を表しています。そのため、経営者の保有割合が大きいとき、その死亡によって開始される相続が争いとなると、企業経営が危ぶまれる事態となってしまいます。
株式が、相続によって分散すれば、決定権が思わぬ親族に渡り、経営に口出しをしてくる可能性もあります。このような相続トラブルのおそれがあるなら、事業承継ではなく、廃業を選択すべき場面もあります。家業であっても親族内承継がうまくいく場合ばかりではありません。後継者がいなかったり、決まっていても資質が不足していたり、ビジョンの共有がうまくいっていない場合、承継は難しいでしょう。
経営者の遺言書について

事業承継か廃業かを選択するときのよくある質問
最後に、事業承継か廃業かを選択するときに、よくある質問について回答しておきます。
事業承継か廃業かは、いつ決めるべき?
事業承継の計画は早期に始め、期間をかけて準備するのを推奨します。そのため、まずは事業承継に向けて動き、難しい場合に廃業するのが正しい流れです。そうすると動き始めるのは早い方がよいですが、最終決断は廃業の直前でも構いません。
廃業の決断を下す前のステップは?
事業承継に向けて進め、それでも廃業せざるを得ないとき、その分析は詳細に行いましょう。財務状況を再評価し、市場でのポジションを分析するなど、戦略的な検討が必須です。これにより、廃業が最善の選択かどうかを再検討できます。
事業承継か廃業か、従業員の意見を取り入れるべき?
従業員は企業の重要な資産です。そのため、事業承継または廃業を決定する際にも、従業員の意見に耳を傾けるのは大切です。ただ、最終的な責任は経営者がとるので、社員個人の利益を尊重するような意見は、全てを反映しない方がよいこともあります。
まとめ
今回は、会社の将来を考えるにあたり大切な、事業承継と廃業の比較について解説しました。
経営者として会社運営をしていると「自分の会社」という思いが強いかもしれませんが、実際には、事業承継か廃業かを決断すると、家族や従業員、取引先といった多くの関係者に多大な影響を及ぼします。メリットとデメリットを知り、慎重に決める必要があり、基本的には後戻りはできません。
相続トラブルが起こってしまうと、事業承継にしても廃業にしても、悪影響を及ぼし、選択肢を狭めてしまう危険があるため、経営者にとって生前対策は必須となります。


