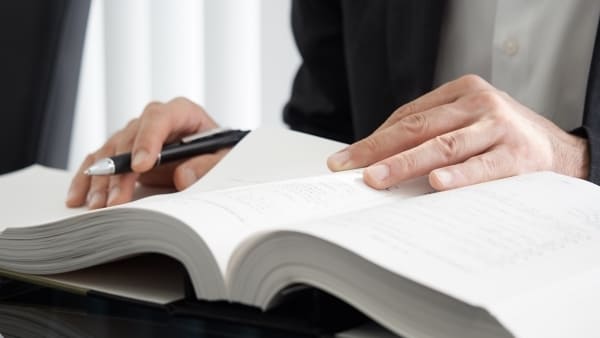特別清算は、財務状況が複雑だったり、債務超過の可能性があったりする起業で、解散する際に選択される清算手続きの1つです。通常清算のプロセスでは対応できない状況において有効であり、業績が悪化した場合の、企業の債権者や株主への公正な分配が主な目的です。
特別清算では、残余財産はないことが多く、株主とて分配を受けられないおそれがあります。また、債務も全て返済し終えることができるか微妙なケースで利用します。その分、その手続の流れは複雑で、法的な注意点も、通常の清算手続きにも増して多くあります。
今回は、特別清算の手続きや注意点について解説します。事業を運営する上では不測の事態もあります。リスクに備え、特別清算という選択肢について正確な知識を理解してください。
特別清算の基本
まず、特別清算の基本的な法律知識について解説します。
特別清算の定義
特別清算は、債務超過や財務状況が複雑であるなど、特殊な状況にある企業の解散と清算を目的とした法的手続きです。このプロセスを利用する場合には、債務の全てを返済しきれない可能性もあるため、通常清算手続きよりも詳細な手続きを守り、債権者全体の公平と利益を保つことが要求されます。
特別清算が利用される場面は、例えば次のケースです。
- 清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合
- 債務超過の疑いがある場合
特別清算は、解散と清算の手続きでありながら、業績が悪化している状況で用いられることが多く、民事再生や破産などの手続きと選択が必要となります。また、裁判所の監督の下に進む点ではこれらの手続きと近しい部分が多いです。
特別清算の手続きの流れ
特別清算は、まず法人の解散決議を株主総会で行って開始される点は、通常清算と変わりません。ただ、その後には、清算人ではなく、特別清算人を選任して進めます。特別清算人は株主総会によって選ぶことができ、取締役がその任に就くことが多いですが、裁判所によって指名されることもあり、弁護士が特別清算人の職となることもあります。
特別清算人の手続きにおける役割は、財産の調査、評価及び処分、債権者への通知、債権の届出期間の設定、そして最終的に債権者への配当を行うことです。特別清算の手続きは、通常清算に比べて時間がかかることが多く、複雑なために法的知識や専門性を求められます。
他の手続きとの違い
特別清算と、他の似た手続きとの違いを知ることは、どのような手続きかを具体的に理解する助けとなります。
特別清算は、通常清算と破産の中間に位置する手続であり、通常清算に比べて裁判所の監督のある点で公平性が担保されるものの、破産手続きよりは簡易かつ迅速な手続きです。
通常清算との違い
通常清算は、会社の財産を換価して債権者に返済を行い、残余財産を株主に分配します。この手続きは、債務超過の可能性があるケースのように、会社の財産では債務が払いきれない場合には利用できません。その分、通常清算では債権者の公平を強く意識することまでは不要で、裁判所の監督なく柔軟に進められるのが特徴です。
通常清算の手続きについて

破産との違い
破産もまた、特別清算と同じく、会社の債務円学を返しきれない場面で用いられることは変わりませんが、破産の方が裁判所の関与の程度が強く、手続きが厳格です。法人破産では、裁判所が破産管財人を任命し、会社の財産が適正に換価され、債権者が害されないよう、強力に監督します。
以下、よく似た破産手続きとの区別のため、特別清算のメリット、デメリットを、破産との比較で説明します。
【特別清算のメリット】
- 破産より周囲に与えるイメージが良い
- 手続きが破産より厳格ではない
- 費用(弁護士報酬や管財人費用)を抑えることができる
【特別清算のデメリット】
- 債権額に争いがある場合に進められない
- 流出した財産の取り戻しが必要な場合には利用できない
- 債権者の協力を得る必要がある
- 株式会社でしか利用できない
特別清算の手続きの流れ
次に、特別清算の手続きの流れについて、詳しく解説します。
会社の財産状態を調査したり、財産を換価し、債務の弁済をする点は通常清算と変わりませんが、会社に十分な資産がなく債権者間の公平性を確保しなければならないことから、債務の弁済について債権者の同意が必要となります。
株主総会による解散決議
まず、株主総会において解散決議をします。会社にとって、解散決議は非常に重要な決定であり、特別決議で行われます。つまり、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行う決議です(会社法309条2項)。
特別清算の申立て
通常清算の遂行に支障があるか、債務超過の疑いがある場合に、会社は裁判所に対し、特別清算の申立てをすることができます。この申立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に行います。裁判所における特別清算手続きの決定をもって、プロセスが開始されます。
清算人の選任
特別清算では、手続きを進める清算人は、株主総会の決議で選ぶことができます。特に支障がなければ代表取締役が清算人となるケースが多いです。特別清算を利用することがあらかじめ決まっている場合は、解散の決議と同時に清算人の選任決議をすることができます。
特別清算人は裁判所に指名してもらうこともでき、この場合には弁護士などがその任に就きます。特別清算人の主な役割は、財産の調査、評価、処分を行い、債権者全体の利益を最大化することです。また、債権者との交渉や法的な争いを解決するための、会社の代理人としての機能も有します。
債権届出の公告と催告
特別清算開始後、会社はその債務額を確定させる必要があります。
具体的には、特別清算人が債権者に通知し、債権の届出を求めます。この通知の方法は、公告と催告(直接の通知)の双方を進める必要があります。まず、知れている債権者には個別に催告をし、債権の届出を促します。また、それ以外にも官報などで公告し、債権の届出を待ちます。これらの手続きは、債権者の権利を保護するため、とても大切な意味を持ちます。
清算人は、会社の財産状態を調査して財産目録を作成し、株主総会の承認を受けた上で裁判所に提出します。
協定案や和解案に基づく債務の弁済
特別清算人は、企業の財産を評価し、可能な限り高い価値で売却します。この売却から得られた資金は、債権者への配当に充てられます。このとき、特別清算では、債権者間の公平を守るため、債務の弁済について債権者の同意が必要となります。
債権者の同意を得る方法に、和解型と協定型の2つがあります。
- 和解型
各債権者との間で個別に弁済額や弁済方法を話し合って和解する方法。 - 協定型
債権者集会の決議によって弁済額を決める方法。協定案を裁判所に提出し、債権者集会において債権者の承認を受け、裁判所の認可決定を受けます。
いずれの方法も、弁済できない分については債権者に放棄してもらう必要があります。和解型では、会社が各債権者と交渉して合意に至る必要があるのに対し、協定型では、債権者全員の同意を得る必要はないという点が異なります。
債権者の数が少なく、全員の同意が得られそうなら和解型で、そうでなく債権者が多い場合や和解に応じない個人や法人が含まれているなら協定型で進めることになります。このとき、協定型では、債権者間を平等に扱う必要があります。いずれも、弁済できない債務は免除してもらうことを内容とします。
清算結了の登記
全ての債権の弁済が終わり、会社の財産も債務もなくなると、清算は終わりです(清算結了)。清算結了になると、裁判所の決定により特別清算手続は終了し、その旨の登記が行われます。
まとめ
今回は、特別清算の重要性と事業主が知っておくべき手続きのポイントを解説しました。
特別清算は、財務的に困難な状況にある企業が利用する重要な手段です。このプロセスを通じて、負債を清算して会社を終えるとともに、その際の債権者の公平を図ることができます。そのためには、特別清算を適用できる条件、手続きで遵守すべきことなど、注意すべき法的なポイントを理解しておかなければなりません。
手続きは複雑なので、特別清算を利用すべき難しいケースでは、弁護士への相談が有益です。申し立てから債権者との交渉まで、弁護士に依頼することができます。