通常清算は、法人が解散した際に行われる一連の手続きです。しかし、多くの経営者は、その具体的な流れや必要な手続きについて知らないことが多いものです。また、社長にとっては清算によって会社を終了することは考えたくない将来かもしれませんが、相続や事業承継のタイミングではやむを得ないこともあります。
会社が解散決議をし、債務が支払い切れる場合には、破産や特別清算をする必要はなく、通常清算の手続きがよく用いられます。
今回は、通常清算の基本的なプロセスについて、順に解説していきます。
通常清算の基本
会社の清算は、法人の資産を全て換金し、債務を支払い、会社を閉じることです。株式会社の清算には、通常清算と特別清算の2つの方法があります。
- 通常清算
裁判所の監督なしに清算人によって行われる解散手続き - 特別清算
裁判所の監督下で、債務の完済を目指す解散手続き
清算を完了することを「清算結了」と呼び、株主総会などで清算結了の報告をすると会社は終了します。この清算手続きを担当するのが清算人です。
通常清算とは
通常清算とは、裁判所の監督なしに、清算人が行う解散手続きです。通常清算では、会社の経営者であった代表取締役が、清算人と名称を変えて、会社の終了業務を担当するのが特徴です。
通常清算を担当する役職のことを清算人といい、津城清算では、会社の代表取締役だった人が担当する例が一般的です。清算人は、通常清算において、債権の取り立て、資産の換価、債務の支払いや残余財産の分配といった多岐に渡る職務を担当します。
通常清算では、特別清算や破産と異なり、会社の財産を換価し、全ての債務を支払いきることが可能だからこそ、裁判所の監督が不要とされているのです。
特別清算との違い
通常清算と特別清算の違いは、通常清算が裁判所の関与を伴わないのに対して、特別清算では裁判所が監督して進める点です。債務を全て完済可能なのであれば通常清算が選ばれますが、そうでない場合に特別清算となります。いずれの手続きも、株主総会で会社の解散を決議して開始される点は共通します。
なお、破産の手続きは、債務を支払うことが難しい場合に選択される手続きであり、通常清算とは全く異なる手続きです。
特別清算の手続きについて
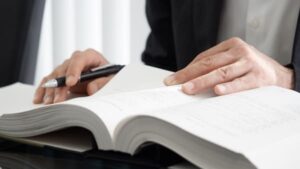
通常清算の手続きの流れ
次に、通常清算の手続きの流れについて解説します。
通常清算は、会社の財産をすべてお金に換えた結果、債務を払うことができる場面で利用する手続きなので、特別清算や破産ほど厳しいルールはありませんが、手続きの流れには決まりがあり、遵守して進める必要があります。
法人解散の決議
法人解散の決議は、株主総会において行われます。株主総会は、会社の重要事項を決める、再考意思決定機関です。株主総会における解散決議は「特別決議」とされており、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行う決議です(会社法309条2項)。
解散決議をするとき、解散日はできるだけその総会当日、もしくは、総会に近い日に設定します。
清算人の選任と現務結了
解散決議の次に、通常清算を担当する清算人を選定します。清算人は、法人の解散後に財産の清算を行う責任者です。清算人の選任後、解散と清算人について登記する必要があります。通常清算における清算人の数は、監査役会がある場合は3名必要であるなど、組織の構成によってルールがあります。
清算人は、まずは現在行っている事業をストップさせ(現務結了)、会社の財産を把握すると共に、債権債務関係を把握して清算を進めます。清算人の役割は、財産の管理、評価、売却、債権者への支払い、残余財産の分配といったこの後に必要なプロセスの大部分が含まれます。
清算手続き中の会社の行為について

債権者への通知と債権届出期間
法人解散後、清算人は債権者に対して通知を行い、債権の届出を求めます。この通知は、公告と直接通知の両方を用いて行うことが一般的です。つまり、清算人は、知れている債権者に対しては個別に催告をする必要があり、あわせて官報などによって公告を行います。
また、債権者が債権を届け出るための期間(債権届出期間)を設定し、この期間内に届出がない場合、その債権者の権利は消滅する可能性があります。
財産の換価
清算人は、法人の財産を適切に評価し、必要に応じて売却します。会社の保有していた資産の種類によって、不動産や有価証券の市場価値の調査、買い手の探索や販売契約の締結といった作業が必要となります。在庫などが存在する場合には、適正に売却しなければなりません。
債務の弁済と残余財産の分配
財産の売却から得られた資金は、債権者への支払いや残余財産の分配に充てられます。
解散の決議後は、通常清算であっても、債務を個別に返済することはできません。公告と催告によって全ての債権を把握した後に、平等に返済する必要があるからです。たとえ特別清算や破産をするほどに業績が悪化しておらずとも、債権者間の公平は守られる必要があります。
また、全ての債権を支払い終えた後に、会社に残った財産は、株主に分配されます。通常清算の場合には、残余財産の分配は、その保有する株式数にしたがって按分されます。
決算報告と株主総会の承認
清算事務が終了した後、清算人は決算報告書を作成して株主総会に報告をします。この報告書には、清算の過程で行われた財産評価の詳細、債権者への支払い状況、残余財産の分配方法などが記載されます。
この決算報告書について株主総会の証人がえられると、清算手続きが正式に終了します(清算結了)。清算人はここまでの手続きを、関係者の権利を守りながら進める責任があります。
清算結了の登記
株主総会による決算報告の承認から2週間以内に、清算結了の登記をする必要があります。この登記の完了をもって、通常清算の手続きは終了します。
その後に、法人登記を抹消し、最終決算についての税務申告を行うといったことをして、会社は正式に終了となります。
通常清算における注意点
通常清算は、企業が法的手続きを通じて自身の財産を処分し、債務を清算するプロセスです。このプロセスを円滑に進めるためには、いくつかの重要な注意点があります。
法定期間を遵守する
通常清算においては、法律によって定められた複数の期間が存在します。例えば、債権者への公告期間や、清算結了の登記の期限といったものです。各ステップで遵守すべき期間を守らなければ、清算が無効となるリスクや、遅延して追加の出費が生じるおそれがあります。
したがって、清算人がこれら法定の期限を正確に把握し、適時に手続きを進める必要があります。
債権者保護を遵守する
通常清算の目的の一つは、債権者の権利を保護することにあります。これは、通常清算がそもそも、会社の債務を全て支払いきれることを前提としているからです。
そのため、清算人は知れている債権者への通知を適切に行い、債権者を保護する必要があります。また、公告に対して債権者からの届出があったときにも、清算人が慎重に検討し、適切な支払いを公平に行わなければなりません。
清算財産を適切に管理する
清算の間、清算人は企業の財産を管理し、価値を減らさないよう注意しなければなりません。
また、財産の評価を正しく行い、適切な売却方法を選定し、できるだけ高い価値で換価できるよう努力します。不適切な財産管理は、債権者や株主への支払い額を減少させることにつながり、清算人はその法的責任を問われる可能性があります。
まとめ
今回は、会社の解散と清算の手続きでもっともよく利用される通常清算について解説しました。
通常清算の手続きの流れと注意点を知ることは、円滑に会社を終わらせるのに有効です。通常清算は、特別清算や破産といった他の手続きとは異なり裁判所の管理がありません。手続きについて柔軟に進められる分、むしろ、しっかりと経営者が管理しないと、誤ったプロセスとなってしまうので、専門家の助けを借りるべき場面だといえます。


