もう会社をやめてしまいたいと考えたとき、会社をたたむ方法には「解散」「清算」「破産」という3つの異なる専門用語が登場します。
いずれも身近な一般用語としても使われますが、法的には厳密に区別されています。そのため、違いを理解し、使い分けなければなりません。そして、どの方法で会社をたたむかによって、残った財産や債務をどのように処理するかなど、細かい手続きが異なります。3つの会社をたたむ方法のうち、適切な方法を選択しないと、会社に見切りをつけるタイミングを見誤り、事業承継をすることも、経営をやめることも難しくなる危険があります。
今回は、会社をたたむ3つの方法(解散、清算、破産)の違いと、それぞれのメリット・デメリットの比較について解説します。
会社の解散とは
解散とは、最も広い意味で、会社をたたむ全ての場合にあてはまる用語です。
会社を解散する理由には、まだ余力があって自身の引き際を決められるケースと、もはや余力がなく、裁判所に申立てすることによって法的手続きを利用して会社を閉める方法の2つに分かれます。取引先などの債権者のためだけでなく、経営者自身のためにも、できるだけ余力の残っているうちに解散する方法のほうが、再出発が容易です。
会社自身の力による解散
会社自身の力による解散には、次の4つの方法があります。いずれも、会社が自分の力で閉じることができ、その判断も、会社自身で検討して決めることができるので、円滑に進めば紛争化しません。
- 定款上の会社の存続期間の満了
- 定款上の解散事由の発生
- 株主総会の決定
- 合併による消滅会社の解散
定款で、存続期間や解散事由を定めている企業には、そもそも数年しか事業活動しない法人や、特定の事業のためにしか継続しないことを予定する法人などもあり、いわば「計画通りの解散」のケースも少なくありません。
株主総会は、会社の所有者による意思決定機関であり、株主総会で解散が決定された場合には、次章に解説する清算に進みます。
裁判手続きによる解散
会社の意思によらない解散は、次の3つの方法です。いずれも、会社に余力がなく、資金も尽きた後に、裁判所などの公的機関の助けを借りて行うものです。手続きが複雑なこともあり、弁護士に相談すべきケースです。
- 裁判所による破産手続き開始決定
- 裁判所による解散を命じる裁判
- みなし解散
破産手続きは、資産が少なく、債務を返済しきれないときに、残余財産を債権額に応じて分配し、残った債務の支払いを免除するという裁判所の手続きです。免責をすることとなるので、公平性、公正性を担保する必要があり、裁判所の選任する破産管財人となった弁護士が、財務状況をチェックし、免責相当かどうかを調べます。
また、次の場合、裁判所は、会社を解散することを強制的に命令できます。
- 解散命令
公益を確保するため会社の存続を許すべきではないと認める一定の事由があるとき - 解散判決
議決権または発行済株式総数の10分の1以上を有する株主の訴えがあったとき
一定期間の間、役員変更登記などがなされずに放置された会社について、休眠会社のみなし解散の制度が設けられています。
会社の清算とは
清算とは、解散の後に、債権債務や資産などを法的に整理するための手続きです。
なお、破産の場合には、管財人が調査し、換価作業などを行うため、清算手続きは、解散のなかでも自身の力で会社を閉じることができた場合に行われるものです。清算期間中は、原則として取締役が清算人となり手続きを進めます。清算中も会社は存続しますが、清算の目的の範囲内の行為しかできません。
通常清算
通常清算とは、会社の解散決議をした後で、法律の規定に従って行う清算です。通常清算は、特に支障がなくスムーズに進む場合に行われる手続きなので、破産や特別清算と違って、裁判所の監督はありません。
逆に、債務超過の疑いがあるなど、特別清算が適切だと考えられる場合、通常清算の手続きによって処理することはできません。
通常清算の手続きについて

特別清算
特別清算とは、清算手続きのなかでも、裁判所が監督する方法です。特別清算は、債務超過の疑いがあるなど、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情のある場合に行われます。会社が破綻しかかっている点で破産と似てはいますが、管財人による財産調査、否認権の行使といった制限が不要な点で、より簡便な手続きです。
したがって、債権者が協力してくれる場合でも、不正経理の疑いがあるなど、債務をが多い場合には、特別清算ではなく、破産の申立てを行うこととなります。
特別清算の手続きについて
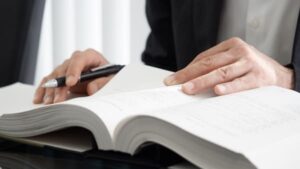
会社の破産とは
破産とは、会社を継続することができず、現在ある債務を支払いきることもできないときに、裁判所に申し立てて法的に清算する制度です。この場合、裁判所から管財人という弁護士が選任され、財産についての監督を受けます。
破産と似た用語に「倒産」がありますが、「倒産」はより広い意味で使われます。すなわち、破産だけでなく、特別清算、民事再生、会社更生などを含めて「倒産」と呼ぶことが多いです。そのなかの代表的な手続きである破産は、「破産法」という法律に基づいて行われます。
破産手続きは、会社の資産をすべてお金に換え(換価)、債権者に対して債権額に応じて配当し、残った債務を免責して会社を閉じる、という流れで進みます。
まとめ
今回は、事業承継と比較して検討されるであろう、会社の廃業の際に、適切な選択肢を選べるよう、解散、清算、破産という似通った言葉の違いと、使い分けについて解説しました。
事業承継やM&Aの可能性がなくなれば、廃業は選択肢に入ってきます。しかしその手続には多くの種類があり、それぞれ一長一短で、正しい選択をしなければ損するおそれもあります。


