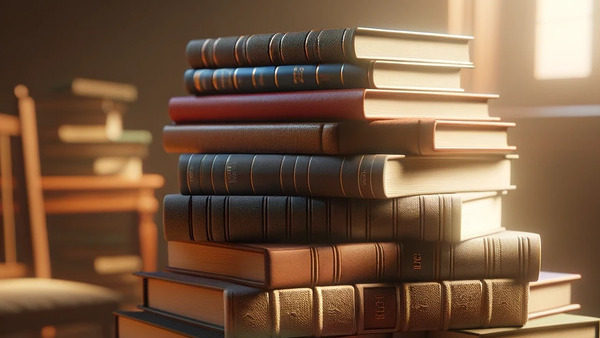相続手続きがスタートすると、相続人調査や確定のために、亡くなった方(被相続人)、相続人の戸籍を収集する必要があります。
戸籍には多くの種類があります。現在はデータ化されている戸籍ですが、古い戸籍になるほど紙でしかないなど、手続き上の困難がつきまといます。不慣れな人にとっては、相続に必要な戸籍をスピーディに集めるのは大きな負担となります。そのなかでも名称を聞き慣れないのが、「改製原戸籍」です。
今回は、改製原戸籍の意味と入手方法、相続手続きにおける利用法を、弁護士が解説します。
相続手続きに必要な戸籍の種類
相続手続きには、多くの戸籍が必要となります。その理由は「誰が相続人なのか」を客観的に証明し、特定するためです。
民法では、「配偶者(夫または妻)」「子」「直系尊属(父母など)」「兄弟姉妹」のように、その続柄によって相続人になれるかどうかが定められています。そして、法定相続人のうち、先順位の続柄がいない場合にはじめて、後順位の続柄が相続人となる、という関係にあるため、それぞれの続柄の人が「存在しているのか」を調べる必要があります。そのことを端的に示すのが、戸籍なのです。
相続における調査の過程では、被相続人の「出生から死亡までの連続した全戸籍」が必要となります。全戸籍を取得して調べることで、抜けもれなく相続人を確定できるのです。このなかには、通常の戸籍だけでなく、除籍や改正原戸籍が含まれます。
相続で必要な戸籍の収集について

改製原戸籍とは
戸籍は、法改正の都度、改製(作り直し)されています。改製原戸籍とは、現在の戸籍が作り直される前の古い戸籍のことです。「かいせいげんこせき」とも「かいせいはらこせき」とも読み、単に「原戸籍」と呼ぶこともあります。
法改正による戸籍の改製は何度か行われていますが、特に、紙の戸籍がコンピュータ化され、データ化された時点のものが最重要です。前章で解説した相続手続きに必要となる「出生から死亡までの全ての戸籍」には、当然ながら改製原戸籍も含まれており、必ず取得しなければなりません。
改製の時点で、既に結婚や離婚、死亡などのライフイベントが起こって除籍されていた場合に、改製後の戸籍にはそれが引き継がれず省略されるため、改製後の戸籍のみでは判明することができません。この場合、改製原戸籍を確認しないで相続を進めると、昔の身分関係の変動によって生じた相続人を見逃すおそれがあり、相続人の特定に失敗してしまう危険があります。
改製原戸籍を入手する方法
改製原戸籍の取得は、戸籍謄本の取得よりも大変な場合が多いです。例えば、法改正による戸籍の改製(作り直し)の前に、結婚や離婚、死亡などのライフイベントが起こっていたり、転居して本籍地を移転していたりすると、その回数だけ取得すべき戸籍が増えてしまいます。
改製原戸籍もまた、市区町村役場の窓口で取得することができます。ただし、過去のライフイベントによる改製原戸籍を取得しなければならない場合には、市区町村の統廃合を調べ、管轄の役所を調査する必要があります。
相続人の数が多い場合や、度重なる身分変動によって複雑になっている人の場合、改製原戸籍を含めた全戸籍を取得するのに数ヶ月の期間を要することもあります。手間と費用がかかる場合には、戸籍の収集を全て弁護士に代理で任せることもできます。
改製原戸籍はいつまでに取得すべき?
改製原戸籍の取得には、手間と時間がかかることも多いですから、悠長に構えていると、相続手続きの期限を過ぎてしまうおそれがあります。そこで最後に、改製原戸籍の取得をいつまでに終えればよいかについて解説します。
具体的には、相続税の納税期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月」とされているため、遅くともこのときまでには改製原戸籍が手元に揃っていなければなりません。
一方で、改製原戸籍が必要な家庭では、結婚と離婚を繰り返しているなど、家族関係が複雑化している可能性もあります。このとき、相続税の手続き以前に、「誰が、どの財産を受け継ぐか」について争いとなり、遺産分割協議が長引く可能性も高いケースだといえます。この場合でも、話し合いがまとまり、遺産分割協議書を作成する段階では、改製原戸籍を取得しておかなければなりません。

まとめ
今回は、相続手続きの際によく必要となる「改製原戸籍」という専門用語について解説しました。
相続人を確定するためにも、相続手続きの際には改製原戸籍の取得が必要となるケースが多いです。しかし、戸籍の収集は、慣れない人にとっては大きな手間となりますから、できるだけ早く準備しておかなければなりません。改製原戸籍の取得はハードルが高いと感じる場合、相続のプロにご相談ください。