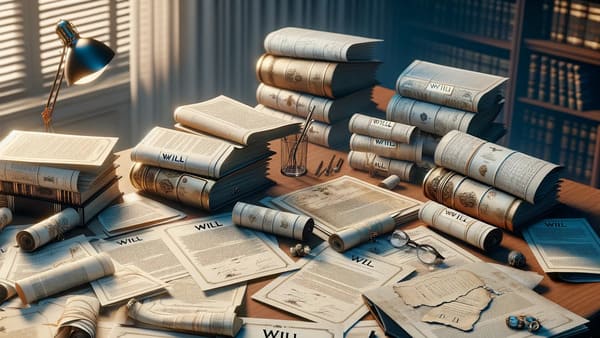亡くなった方が遺言書を複数枚残しているケースは実際にあります。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、そもそも相続人が遺言書を見つけられず、後になって発見される事態もあり得るでしょう。
スムーズな遺産分割を進めるためにも、遺言書が複数枚見つかったときの法的なルールを把握することが重要です。遺産分割における遺言書の効果が強力だからこそ、複数あると、どの遺言書に従うべきか、優先順位によって結論が異なってしまいます。遺言書を書く方は、相続人の混乱する事態を防ぐためにも1通の遺言書にまとめることをお勧めします。
本解説では、遺言書が複数枚見つかった状態における、法的効力や優先順位の判断について解説します。なお、複数の遺言がそれぞれ法的な有効要件を備えているかどうかにも注意を要します。
遺言書は複数書くことができる
まず前提として、遺言書は複数書くことができます。
遺言の内容はいつでも撤回できるため、何度でも書き直すことが可能です。遺言を撤回できる回数や時期について、法律上の制限はありません。遺言書は、遺言者が死亡してはじめて効力が生じます。そのため、遺言者が亡くなって相続が開始されるまでは、いつでも遺言を撤回でき、更にその後に新しい遺言に変更することも何度でも自由にできます(なお、遺言の撤回は「全部」でも「一部」でも可能で、遺言の全部を撤回すると遺言そのものがなくなる一方で、一部を撤回した場合は当該部分だけ遺言の効果がなくなります)。
極端な話、遺言書を書いた翌日に気が変われば、新しい遺言書を書くことができます。
このように、遺言は死ぬまで何度でも作ることができるため、相続が発生した後になって「遺言書が複数枚見つかった」という状態が発生する可能性があるのです。遺言を書いた後に、遺言者の気持ちや心境に変化が起こる可能性は往々にしてあり得えます。そのため、複数枚の遺言書が見つかる事態は、どの家庭でも想定しておくべきで、対策を理解しておかなければなりません。

複数の遺言書の優先順位を確認するステップ
実際に複数の遺言書が見つかった場合は、順を追って有効な遺言がどれかを判断する必要があります。まずは基本的なルールを押さえましょう。
具体的に、どのような流れで有効な遺言を判断すべきか解説します。
最新の日付の遺言が優先される
複数の遺言書が見つかった場合、まず、最新の日付で書かれた遺言が優先されます。例えば、「令和4年5月1日」に書かれた遺言書と「令和5年1月1日」に書かれた遺言書が見つかった場合、「令和5年1月1日」に書かれた遺言書を有効なものとして扱います。
ただし、あくまで複数の遺言のそれぞれが民法の定めた有効要件を満たしているものであることが大前提です。もし、最新の日付の遺言書が民法で定める形式に不備がある場合、その遺言は無効であり、この場合には古い日付の遺言を有効なものとして扱います。例えば、新しい遺言が自筆証書遺言であるものの、「全文を自署する」という要件を満たしていない場合には無効となり、古い遺言にしたがって遺産相続を進めることになります。
矛盾しない複数の遺言はいずれも有効
遺言書が複数見つかった場合も、矛盾しない内容であれば、それぞれが有効な遺言書となります(なお、矛盾する部分がある場合、当該部分については前章の通り、後の日付の遺言書を有効なものとして扱います)。このことは、民法1023条に次のように定められています。
民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
民法(e-Gov法令検索)
つまり、前の遺言と後の遺言が抵触するとき、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされるのであり、矛盾や抵触のないときは、前の遺言も後の遺言もそれぞれ有効として扱われます。
具体的な事例で説明します。例えば、「預金はすべて配偶者Aに相続させる。自宅は長男Bに相続させる」という遺言を書いた後に「自宅は長女Cに相続させる」と遺言を残した場合、自宅についての遺言は矛盾するので、後に書いた遺言書にしたがって長女Cに相続されますが、預金についての遺言は矛盾しないので、先に書いた遺言書にしたがって配偶者Aが取得することとなります。
後に書かれた遺言書には、預金に関する言及がありません。しかし、特段撤回する文言や抵触する内容が書かれていなければ、内容に矛盾は生じません。この場合、書かれた日付が古い遺言書でも、依然として有効な遺言として取り扱うため注意しましょう。
日付のない遺言は無効になる
作成日の記載されていない遺言書は無効です。遺言者が書いた日付の有無は、前章の通り、その先後によって遺言書の優先順位を判断する、重要な基準となるからです。
例えば、「令和4年5月1日」に書かれた遺言書と、日付が書かれていない遺言書が見つかった場合、日付の書かれていない遺言書は無効となる結果、「令和4年5月1日」に書かれた遺言書を有効なものと判断します。このとき、仮に、日付が書かれていない遺言書が、実際は令和4年5月2日以降に書かれていたとしても効力を有しません。また、「令和4年5月吉日」「令和4年5月某日」のように日付が特定できない場合も無効となります。
このような形式不備によって無効となるリスクを避けるには、公証人の関与によって形式面のチェックのできる、公正証書遺言の形式で遺言を残すのがお勧めです。
公正証書遺言の書き方について

遺言の種類は優先順位に関係しない
一般によく用いられる普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。これらの遺言書の種類は、優先順位には関係しません。そのため、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の遺言書がそれぞれ見つかった場合でも、最新の日付で書かれたものを有効な遺言と扱います。
遺言を書く段階でも、遺言の種類にこだわる必要はないので、公正証書遺言を撤回したい場合にも、自筆証書遺言や秘密証書遺言の方式で撤回することも可能です。
なお、優先順位には無関係だとしても、それぞれの遺言の種類には特徴があり、メリットとデメリットがあるため、状況に応じた最適な遺言の種類を選ぶ必要があります。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 作成の費用がかからない いつでも手軽に書ける 遺言の内容を秘密にできる | 発見されない可能性がある 形式不備で無効になりやすい 改ざん、隠蔽の危険がある |
| 公正証書遺言 | 公証人のチェックあり 改ざん、隠蔽の危険がない 検認が不要 | 証人が2人必要 費用や手間がかかる |
| 秘密証書遺言 | 遺言内容を秘密にできる 改ざん、隠蔽の危険がない | 証人が2人必要 形式不備で無効になりやすい 検認が必要 |
遺言書の基本について

遺言書が複数ある場合の対応
次に、実際の相続において、遺言書が複数見つかってしまった場合の対応について解説します。
まずは時系列に並べて優先順位を決める
複数の遺言書が見つかったら、まずは日付順に整理してください。日付が新しい遺言書を有効として取り扱うというルールが基本となる以上、時系列の把握は欠かせません。
ただし、複数の遺言同士が矛盾しないときには、複数の遺言のそれぞれ一部ずつが有効になる可能性もあるので、日付の古い遺言だからといって安易に破棄してはいけません。各遺言書を丁寧に読み解き、内容を吟味することが大切です。
複数の遺言の有効性を見極める
その上で、各遺言書の有効性を判断します。民法の定める書き方のルールを逸脱している場合は無効となるため、無効な遺言書の内容は無視して構いません。「遺言書のように見える書類」が発見されたとしても、全てが遺言として有効に機能するとは限りません。故人の下書きや書き損じ、草稿やメモといったものが、遺言書としての法律の様式にあてはまっているか、慎重に検討してください。
特に、特定の相続人だけが被相続人の介護をしていたなどの理由で多額の生前贈与を受けていた場合など、不平等な遺言書があると、その有効性をめぐってトラブルになりやすくなります。
遺言の有効性に疑問があるなら、専門家である弁護士に相談しましょう。相続に関する知識と実績が豊富な弁護士に依頼すれば、解決に役立つアドバイスが得られます。相続についての無料相談を実施している法律事務所もあるため、トラブルになりそうなときは早めの相談をご検討ください。
相続に強い弁護士の選び方について

複数の遺言があるとは気付かず執行した場合の対応
複数の遺言があることに気付かず遺言を執行し、後々になって有効な遺言書が見つかった場合、遺言の執行をやり直す必要があります。複数の遺言があることに気付かず遺言を執行すると、面倒な対応を強いられます。
実際に遺言を執行して財産の移転を済ませてしまっていたとしても、やり直しをしなければなりません。分割して取得した預金を返還するのはもちろん、不動産の相続登記もやり直す必要があるので、かなりの手間と労力を要します。無効な遺言内容で相続税の申告を済ませていた場合、修正申告を行う必要が出てきて、計算が異なると追加の納税が必要となります。
遺言執行者の役割について

生前に気づいたら1通の遺言書にまとめる
生前に遺言書が複数枚あることに気づいたら、1枚にまとめておきましょう。本解説の通り、複数の遺言書があると、相続人は各遺言書について「どの部分が有効なのか」「そもそも有効なのか無効なのか」を判断しなければならず、混乱し、手間がかかります。その結果、遺産分割が長期化すると、争続に発展してしまいます。
生前に考えが変わり、複数の遺言書を書くケースは往々にしてあり得ます。しかし、相続人の負担を考えると、1通の遺言書にまとめて遺産分割の意向を伝える努力を生前にしておくべきです。
相続が起こると、遺産分割や役所への各種届出、葬儀の準備など相続人は慌ただしく過ごすことになります。相続人の負担を少しでも軽減するためにも、複数の遺言書を出現させてしまって混乱させるのは避けなければなりません。遺言内容の変更や追加を行うときには、新しく有効な1通を作成することを強くお勧めします。
なお、遺言書を書き直すときは遺留分にも配慮すべきです。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められていた、遺産を相続できる最低限の割合を指します。
具体的な遺留分の割合は、以下のとおりです(兄弟姉妹には遺留分がありません)。
- 配偶者のみが相続人の場合:1/2
- 子のみが相続人の場合:1/2
- 直系尊属のみが相続人の場合:1/3
- 配偶者と子が相続人の場合:配偶者が1/4、子が1/4
- 配偶者と父母が相続人の場合:配偶者が1/3、父母が1/6
例えば、長男に1円も相続させないような遺言書を書くと、長男の遺留分を侵害します。この場合、長男が遺留分侵害額請求権を行使すると、他の相続人に対して、最低でも遺留分を渡すよう請求できます。遺留分をめぐって、相続人同士がトラブルになるケースは少なくないので、遺言書を書き直す際には、遺留分にも意識を向けなければなりません。

複数の遺言があるときのよくある質問
最後に、複数の遺言があるときのよくある質問について回答しておきます。
複数の遺言書は有効となる?
複数の遺言書が全て有効となることもあります。民法の定めるルールに従い、要件を充足している複数の遺言であって、かつ、内容が矛盾していない箇所については、複数の遺言書の全てが有効なものとして取り扱われます。
遺言書は何通まで書ける?
遺言書を書ける回数や通数には、制限がありません。つまり、遺言は何度でも書くことができますし、何枚でも書いてよいです。本解説の通り、何通も書いた場合には、その内容や順番を管理し、生前のうちには意思を固めて1枚にまとめるべきです。
遺言書は何枚まで書ける?
遺言書の枚数に制限はなく、何枚でも書けます。1枚の遺言書でも問題なく有効となりますし、50枚や100枚であったとしても、民法に定める要件さえ満たしていれば全てのページが有効な遺言として機能します。
ただし、あまりに大部な遺言書は、ミスが生まれやすくなったり、無駄な記載が争いを生みやすくなったりするので注意してください。
まとめ
本解説では、遺言書が複数ある場合の対応について解説しました。
複数枚の遺言書が見つかった場合は、基本的に、書かれた日付が新しい遺言書を有効なものとして取り扱います。時系列に並べた上で、有効性を判断しましょう。場合によっては、複数枚の遺言書をそれぞれ有効なものと扱うケースもあります。このとき、書かれた内容を精査して「どの部分が有効か、無効か」を判断しなければなりません。相続人のみでは判断できない場合は、相続に強い弁護士に相談することを検討してください。
生前に遺言書を書く場合は、可能な限り1通にまとめることをお勧めします。相続人の負担を軽減し、スムーズに遺産を分けるための心配りをすることが大切です。