公正証書遺言は、遺言の種類のなかでも特に確実性が高く、偽造や改ざん、紛失をしにくい点で最もお勧めの形式です。公証人の立会いのもと、法律の定める形式にしたがって作るので、自筆証書遺言に比べ法的な安全性が高いのがポイント。弁護士など専門家がサポートする場合は、公正証書遺言を作成するのが原則で、他の遺言を進めることはあまりありません。
遺言を残すのは、自らの大切な財産を次世代に引き継ぐためです。内容には最大限の注意を払い、間違いのないようにしなければなりません。公正証書遺言では、その手続きや必要書類が、自身のみで作る自筆証書遺言よりは、少し複雑です。
今回は、公正証書遺言の基本と、書き方や手順、必要書類について解説します。多くのメリットのある遺言形式ですが、公証役場に行くなど、手間もかかります。デメリットの多くは、専門家のサポートを得ることで解決できます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言を作成する方法の1つです。法的な保護が厚く、確実性の高い形式として、真剣に相続対策を考える方にはよく利用されています。以下ではまず、公正証書遺言の基本を解説します。
公正証書遺言の定義
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人の前で遺言の内容を述べ、それを公証人が文書化し、遺言者と証人が署名・押印することで成立する遺言の形式です。
遺言の種類にはほかに、自筆証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、公正証書遺言はそのなかでも法的に強く保護され、文書の紛失や偽造、変造のリスクが低いという特徴があります。これによって、将来の遺産分割のトラブルを避けることにも繋がります。
遺言書の基本について

自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言と公正証書遺言の最大の違いは、作成のプロセスと法的な安定性にあります。
自筆証書遺言の作成は、遺言者が全文を手書きし、日付と氏名を記入し、署名する必要があります。これに対して、公正証書遺言では公証人が文書化をし、完成してくれます。そのため、公正証書遺言のほうが作成がスムーズですが、その分少し手間がかかります。
法的な争いになりづらいため、相続対策として遺言を残すなら、やはり公正証書遺言のほうがよいでしょう。
自筆証書遺言について

公正証書遺言の法的効力
公正証書遺言の法的効力は非常に高く、遺言の内容についての争いが生じた際の証拠としての価値も、自筆証書遺言よりも高いです。
公正証書遺言は公証人の作る文章であり、公正証書となるからです。公証人は、法務局に所属し、公証役場で公正証書の作成、認証を担当する公務員です。その事務は、公証人法という法律で定められています。また、公証人が関与することで、遺言者の意思が正確に反映されているという信頼性が保たれ、遺言の有効性を確実なものにしてくれます。
公正証書遺言の保存期間は20年とされており、その間は、公証人のもとで保管されるため、破棄されたり紛失したりするリスクなく、遺産分割に必ず反映されます。
これらの特性から、特に財産が多い場合や相続人間の関係が複雑な場合に適しています。
公正証書遺言の作成方法
次に、公正証書遺言の作成方法について、手順を追って解説します。
遺言内容を準備する
公正証書遺言の作成は、まず遺言内容の準備から始まります。公証人が完成させてくれるとはいえ、文案は遺言をする人が自分で考える必要があります。このとき、遺産の詳細や相続人の情報を正確に誤りなく記載し、誰にどの財産を相続させるか、明らかにしておかなければなりません。
このとき、財産を明確に特定できるようリストアップして相続財産目録を作り、かつ、遺留分を侵害しないような分割方法を検討することが大切なポイントです。
公証役場に相談し、日程を予約する
次に、公証役場に連絡し、遺言の作成に関する相談と、日程の予約を行います。公証役場では公証人は遺言作成の手続きについてアドバイスしてくれますが、どのような内容が適切か、トラブルを避けられるか、といった踏み込んだ検討まではしてくれません。
そして、必要な準備が整ったら、公証人に遺言を作成してもらうための面談を予約します。
証人2名を選定する
公正証書遺言の作成には、証人を2名選定し、立ち会ってもらう必要があります。証人は、成年であり、かつ、遺言内容に直接的な利害関係がない者を選ばなければなりません。遺言内容を知ることとなるので、秘密を守れる信用のおける人を選んでください。つまり、相続について中立的な立場の人が、証人としてふさわしいのです。
証人の主な役割は、遺言作成時の遺言能力や、遺言者が自由意思によって作成したという事実を証明することです。作成日には、公証役場に立ち会い、遺言書に署名押印します。
公正証書遺言を作成する
予約日になったら公証役場に出向き、公証人、証人の立ち会いのもと、遺言を作成します。公正証書遺言では、遺言者は公証人から遺言の趣旨を聞いて、公証人に筆記してもらって作成します。作成が終わると、誤りがないか読み聞かせ、閲覧をした上で、遺言者と証人それぞれが署名押印し、最後に公証人が署名をします。
作成を依頼した弁護士にも、誤りのないよう立ち会いを依頼しておくのがよいでしょう。以上の手順を経て、公正証書遺言は正式に作成されます。遺言者の意思が正確に反映されたものとなるよう、慎重に進めてください。
公正証書遺言のメリット
次に、公正証書遺言のメリットについて解説します。公正証書遺言には、自筆証書遺言に比べて多くの利点があります。
公正証書遺言のこれらのメリットは、遺言の確実性と安全性を増すものであり、遺言者の意思を正確に反映するためにも、公正証書遺言を選択することが強く推奨されます。
遺言が無効となるリスクが低い
公正証書遺言の最大のメリットは、遺言が無効となるリスクが非常に低いことです。これは公証人が遺言の作成プロセスに関与し、少なくとも形式的には、法的な要件が満たされることを確認してくれるからです。
公証人は遺言者の意思を確認し、遺言の内容が明確であること、遺言者の精神が健康であり、遺言能力を備えていること、強制や詐欺などの事情がないことを保証してくれます。これにより、遺言の有効性を確実なものとし、その点についての将来のトラブルを予防できます。
紛失や偽造を防止できる
公正証書遺言ならば、紛失や偽造のリスクを軽減され、遺産分割のタイミングになって遺言書を見つけることができないといったトラブルを防止できます。特に、遺言によって相続財産を減らされるなど不利な立場に置かれる人ほど、遺言を隠したり、破棄したりといった行為をしがちです。
公正証書遺言は公証役場に保管されるため、自筆証書遺言のように家庭内で紛失するリスクはありません。また、データベース化されるため、遺言書がどこにいったかわからないという事態も起こりません。
検認手続きが不要
検認とは、遺言者が死亡した後で、遺言書の方式に関する事実を調査し、現状を明確にするもので、主な目的は遺言書の偽造の防止にあります。そのため、自筆証書遺言では検認が必要ですが、そもそも公証人が保管する公正証書遺言では偽造の危険は少なく、検認手続きは不要とされています。
これにより、遺言の執行はスピーディに進めることができ、遺族の手間を大幅に削減することができます。
遺言書の検認について

公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言には多くのメリットがあり、それに対してデメリットは非常に限定的です。しいていえば、公証役場まで出向かなければならず、時間や手間がかかること、公証人に支払う費用など、一定の出費があること、といった程度でしょう。
ちなみに、公証人がチェックしてくれるのは遺言の形式面のみで、内容面について精査してくれるわけではありません。そのため、その遺言が相続トラブルを避けるのに十分なものか、公証人にはアドバイスができません。公正証書遺言が役立つかどうかは、家庭や財産の状況によってケースバーケースであり、遺言のみに関わる公証人にはそこまでの情報や知識がそもそもないのです。
そのため、方式不備を超えて、公正証書遺言の内容が事案に即した適切なものとなっているかどうかは、事前に弁護士に相談するのが効果的です。
公正証書遺言作成に必要な書類と費用
公正証書遺言を作成する際には、必ず集めておくべきいくつかの書類があります。次に、公正証書遺言作成に必要な書類と、費用について解説します。
必要書類の一覧
公正証書遺言を作成するためには、以下の書類が必要です。
- 身分証明書
遺言者の身元を証明するために、運転免許証やパスポートなど、公的身分証明書が持参してください。 - 戸籍謄本
遺言者の家族関係を証明するために、戸籍謄本が必要となります。 - 不動産登記簿謄本
遺産に不動産が含まれる場合には、正確な情報を記載するためにその登記簿謄本を入手しておきます。 - 遺言書案
遺言の内容を事前に草案として準備します。公証人は、遺言者が作成した草案をもとに完成してくれるだけであり、最初の案は遺言者が用意しなければなりません。
これらの書類は、公証人に提出する前に集め、整理する必要があります。戸籍や登記は最新のものである必要があるので、遺言を作成する直前に取り直しておきましょう。
公正証書遺言に必要な費用
公正証書遺言作成のための公証人の手数料は、遺言の内容によって異なります。遺言に記載された遺産の評価額に応じて、次の通りとなっています。
| 目的の価額 | 手数料額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円超え、200万円以下 | 7000円 |
| 200万円超え、500万円以下 | 11000円 |
| 500万円超え、1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円超え、3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円超え、5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円超え、1億円以下 | 43000円 |
| 1億円超え、3億円以下 | 4万3000円 +超過5000万円ごと1万3000円加算 |
| 3億円超え、10億円以下 | 9万5000円 +超過5000万円ごと1万1000円加算 |
| 10億円超え | 24万9000円 +超過5000万円ごと8000円加算 |
文案の作成や、戸籍の収集を弁護士などの専門家に依頼する場合には、その費用もかかります。
追加費用(出張手数料、証人費用など)
公正証書遺言の作成には、基本の公証人手数料の他にも追加費用がかかる場合があります。例えば、公証人に出張をお願いする場合には、出張手数料や交通費がかかります。また、証人を依頼する人に謝礼を払うケースもあります。
公証人に出張してもらう方法について
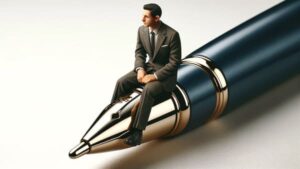
公正証書遺言に関するよくある質問
最後に、公正証書遺言に関するよくある質問について回答します。
公正証書遺言における証人の条件は?
公正証書遺言を作成する際、証人が重要な役割を果たすので、その選定には注意しなければなりません。まず、成年であり、心身が健康で、遺言の意味を理解する人である必要があります。その上で、遺言によって直接の利益や損害を受けない人が適任です。
証人は、遺言の正当性を確認し、公証人を補助するために作成時に立ち会います。家族や友人、職場の同僚など、利害関係がなければ誰でもよいですが、適任者に思い当たらない場合には、弁護士などの専門家を証人とすることもできます。
公正証書遺言の変更や取り消しは可能?
公正証書遺言は、遺言者の意思によっていつでも変更や取り消しが可能です。ただし、そのためには新しい遺言を作成する必要があります。その際にも、公正証書遺言を作成するならば、本解説と同じプロセスで進めることとなります。書き換えは自筆証書遺言でもできますが、形式不備となるリスクがあるため、前の遺言と同じく公正証書遺言で作成したほうがよいでしょう。
遺言を撤回するには、遺言書を物理的に破棄する手もありますが、公正証書遺言は公証役場に保管されるためその方法は用いることができません。次に示す意思が決まっていないときには、単に「前の遺言を無効とする」という遺言を作っておくことでも足ります。

公正証書遺言を作成した後の手続きは?
公正証書遺言の作成後は、その遺言書の正本は、公証役場にて安全に保管されます。遺言者に対しては、遺言書の写しが渡されます。遺言の存在は法務局に登録され、遺言者が亡くなったときには、関係者はどの公証役場からも遺言の存否を調べることができます。
まとめ
今回は、こいう正証書の作成方法とメリット、費用などを解説しました。
公正証書遺言は、他の遺言の作成方法に比べて確実で無効になりにくいメリットがありますが、作成に手間がかかったり公証人とのやり取りが必要であったりなど、デメリットがある部分は、専門家に相談して解決しましょう。


