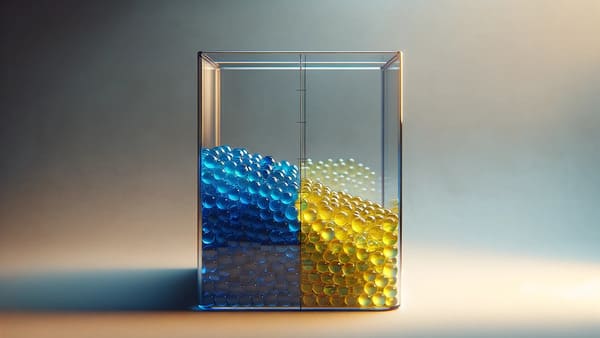多くの人の人生において、数少ない経験である「相続」。そのなかでも特に重要なのが「遺留分」の考え方です。遺留分は、故人が遺した遺言に関わらず、法律で保護された相続人が最低限受け取るべき遺産の割合を指します。
遺留分は、相続人が公平な取り分を確保できるように設けられ、予期せぬ遺言によって不当に遺産を受け取れない事態を防ぐものです。そのため、遺留分の知識が不足していると、相続の過程で、もらえるはずの財産をもらえず、不利益を被ってしまいます。例えば、大半の遺産を他の相続人に渡す遺言が作られたとき、適正な取り分の確保には遺留分を知る必要があります。
今回は、遺留分の基本と、計算方法などの具体的なルールを解説します。遺留分が実際に侵害されて争う方はもちろん、遺留分を侵害しないよう円満な生前対策を実現したい方にとっても重要な知識です。
遺留分とは
遺留分とは、故人の遺言があったとしても、一定の相続人が法律により保障される、最低限度の遺産分配の割合を指します。遺言がある場合には亡くなった方(被相続人)の意思として最優先に尊重されますが、これによって生じる不公平を是正するのが遺留分の役割です。
したがって、この制度は、故人の最終意思に基づく遺産分配を優先する一方で、血縁によって生じる相続人の経済面を一定程度は保護することを目的としています。遺留分の規定は、相続法に定められ、法律が適正と考える範囲と割合が決められています。
遺留分に関する法律の定め
遺留分の具体的な規定は、民法に定められています。
遺留分が保護するのは、相続人としての近しい地位にあることによって、一定の財産を相続できるだろうという期待です。そのため、その認められる範囲は、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分は、被相続人が遺言によって定めた遺産分配の内容を一部変更できる権利といってもよいので、兄弟姉妹は、遺言が自分にとって不公平だったとしても異を唱えることができないことを意味しています。
遺留分の対象となる相続人の範囲
遺留分の対象となる相続人は、次の通り、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の人です。
- 配偶者
故人の法律上の配偶者(内縁は法定相続人には含みません) - 直系卑属
故人の子供や孫など - 直系尊属
故人の両親や祖父母など
このうち、遺留分を主張できるのは、実際に相続する権利のある人に限られます。つまり、相続人には順位があり、先順位の相続人がいるとき、後順位の人は、遺留分を主張することができません。胎児や、代襲相続した人にも、遺留分が認められます。
- 配偶者は必ず相続人となる
- 第1順位:子
子がいるときは、配偶者と共に相続人となる - 第2順位:直系尊属
子がいないときは、直系尊属が相続人となる - 第3順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいないときには、兄弟姉妹が相続人となる
※ 同じ続柄の人が複数いるときには、その人数で等分する
ただし、相続財産を受け取りたくない場合は相続放棄ができ、その場合には初めから相続人ではなかったものと扱われます。
相続人の範囲を知るには、誰が相続人かを調べるため戸籍調査が必要となります。
相続に必要な戸籍の集め方について

遺留分の計算方法
遺留分の計算方法は、相続法によって細かく定められていますが、一般的な計算手順は以下の通りです。
遺留分の対象となる遺産額を確定する
遺留分計算の基礎となる遺産額は、相続開始時に被相続人が有していた財産の額であり、次の計算式で算出します。
- 遺産額 = 相続財産の額 + 贈与財産の額 - 負債の額
注意点として、一定の贈与財産が対象となること、負債を控除することの2点であり、贈与財産のうち遺留分の対象となるのは次の条件を満たすものです。
- 相続開始直前1年に行われた生前贈与
- 贈与の当時者双方が、遺留分を侵害すると知って行った贈与
- 不相当な対価でされた有償による財産の移転
- 特別受益と評価される贈与
遺留分の割合を確定する
遺留分の対象となる相続人について、遺留分の割合を法律に基づき確定します。遺留分の割合は、相続人となる人の続柄によって次のように定められています。
| 続柄 | 遺留分割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:2分の1 |
| 配偶者と子 | 配偶者:4分の1、子:4分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の1、直系尊属:6分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:2分の1、兄弟姉妹なし |
| 子のみ | 子:2分の1 |
| 直系尊属のみ | 直系尊属:3分の1 |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
具体的な遺留分を計算する
以上の通りに算出した項目にしたがい、遺産の総額に対して法定相続分、遺留分の割合をかけ、実際に請求できる具体的な遺留分の額を算出します。
- 遺留分 = 遺産総額 × 法定相続分の割合 × 遺留分の割合
侵害の有無を調べる
ここまでの計算で遺留分が分かると、自分がいくらの相続財産を保障されているか理解でき、実際に取得した財産がこれを下回るなら遺留分侵害があることが明らかになります。どの生前贈与や遺贈によって侵害されているかを明らかにし、請求先を決めたら、遺留分侵害額請求書を内容証明で送付します。
交渉が決裂する場合には、調停、そして遺留分侵害額請求訴訟に発展します。
遺留分の計算にあたっては、遺産の総額を正確に把握することが重要です。遺産には、不動産、預貯金、株式など、故人が生前に所有していたあらゆる資産が含まれ、あわせて借金やローンなどの負債を控除しなければなりません。
また、遺留分を請求するには、その侵害となる生前贈与や遺贈(遺言による贈与)があったことを証明する必要があります。
遺留分侵害額請求について

遺留分が侵害される具体的なケース
次に、遺留分が問題となる、相続における具体的な場面を、例を挙げて解説します。以下の状況において遺留分の保護を求める相続人は、遺留分侵害額請求権を行使できます。
不公平な生前贈与の例
亡くなった方(被相続人)が生前贈与をしたとき、その金額が遺留分を侵害する例があります。生前贈与は、生きている間の贈与であり、その相手は相続人だけでなく第三者なこともあります。
生前の相続対策として、誰かにある財産を承継したいという希望を叶える目的や、相続税対策といった目的で生前贈与が行われるケースは多いですが、贈与を受けなかった相続人にとっては遺留分をしっかりもらえているかよく確認が必要な場面となります。
なお、公正な相続のために、遺留分侵害額請求の相手方の順序、負担額には民法の定めるルールがあります。
遺留分侵害者について

不公平な遺言の例
被相続人が遺言を残していた場合、遺産分割は遺言を優先して行われます。ただし、その遺言が遺留分を侵害している場合には、その範囲で遺留分侵害額請求権を行使できます。
これには遺贈の場合や、遺言によって相続分を指定されていた場合などがあります。
不公平な相続への対応策について

遺留分請求の時効について
遺留分を守るための、遺留分侵害額請求権には時効があります。いつまでも請求できるのでは、請求される側にとっても酷であり、承継した財産の有効活用を妨げます。そのため、期限があるのです。
遺留分侵害額請求権の期限は、次の2つです。
- 消滅時効
遺留分が侵害されることを知った時から1年 - 除斥期間
相続の開始時から10年
時効の進行を止めるには、権利行使の意思表示を、内容証明で証拠に残して進めるのが効果的です。速やかに行動を起こさなければなりません。遺留分を侵害されているかどうか、権利行使をどのように進めたらよいか、迷っているうちに時間が経ってしまわないよう、早めに弁護士に相談ください。
遺留分侵害額請求の期限について

遺留分を確保するために注意すべきポイント
遺留分の問題は、相続の過程でしばしば紛争の原因となります。争続を避けるには、遺留分のあることを踏まえた事前計画と、家族間の密なコミュニケーションがポイントとなります。
遺言書の作成時に遺留分を考慮する
遺留分の問題は、家族が亡くなってから初めて気づくのでは手遅れになりかねません。遺留分の対象となる人は、そのことに早く気づき、生前から対策しておくべきです。具体的には、被相続人となる人が遺言を作成するときには、遺留分に配慮してもらえるように交渉しましょう。
遺言を残す側でも、遺留分を侵害することがトラブルにつながると理解し、遺留分を害さないようにする、あるいは、どうしても遺留分を与えないようにしか分けられないなら、そのような分割に不満を感じる人の納得感を高める努力をすべきです。遺言に、不公平な分割となってしまった理由や思いを伝えたり、代わりの財産を用意したりといった方法が考えられます。
遺言書の基本について

相続計画を事前に家族で共有する
遺留分を守るには、相続計画を、生前に家族で共有しておくことが大切です。これによって、遺留分を侵害するような生前贈与をあらかじめ記録し、万が一に侵された遺留分を正確に計算できることにもつながります。
相続人と被相続人とがコミュニケーションをとり、遺言内容や相続計画を共有することで、遺留分に関する将来の争いを未然に防ぐことができます。このとき、遺留分は、公平な解決策の1つの指針として役立てることができます。
遺留分についてよくある質問
最後に、遺留分についてのよくある質問に回答します。
遺留分の放棄は可能?
遺留分の放棄は、生前でも死後でも可能ですが、生前に放棄するためには、家庭裁判所に申し立てをし、許可を受ける必要があります。詳しくは「遺留分の放棄」を参照ください。
遺留分を確保するにはどうしたらよい?
遺留分は、自動的に保護されるわけではなく、その権利を確保したいなら、遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。請求権の行使をせずに黙っていると、たとえ法律で保護された相続人でも遺留分をもらうことはできません。
まとめ
今回は、遺留分に関する基本的な知識を解説しました。遺留分をあらかじめ理解し、配慮して進めることは、争いとなる場合はもちろんですが円満な相続の解決にも貢献します。
想定していたよりもらえる財産が少なかったときは、必ず遺留分を計算し、侵害されていないか確認してください。
遺留分は、公平性を確保し、紛争を予防するのに役立ちます。また、法律に定まったルールなので、解決策の1つの指針ともなります。相続で守られるべき最低限の権利なので、相続人としては必ず遺留分を理解しておかなければ、損してしまいます。遺留分の確保は、個々の相続人だけでなく、家族全体の安定と調和を保つ上で極めて重要です。