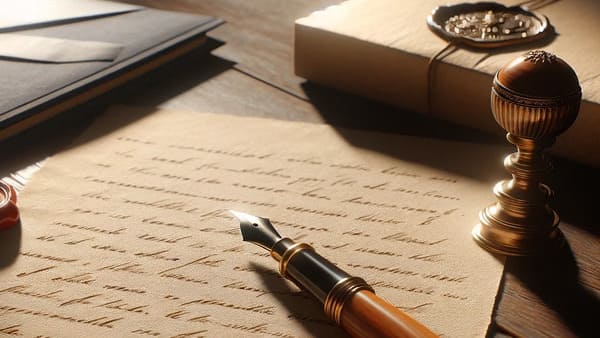遺留分とは、民法の定める法定相続人のうち兄弟姉妹以外(つまり、配偶者、子・孫、直系尊属)の持つ、遺言などによっても侵害されずに相続できる遺産の割合のことです。
生前贈与や遺贈によって遺留分より少ない財産しか相続できなくなってしまった方は、遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)を行使して救済を求めることができます。このとき、権利行使を相手に伝えるのが通知書であり、その意思表示を確実に証拠化する目的で利用されるのが内容証明による方法です。
今回は、遺留分侵害額請求の通知書の書き方と、内容証明の注意点を、書式と共に解説します。
遺留分侵害額請求の通知書【書式ダウンロード可】
早速、遺留分侵害額請求の通知書の書式を示します。遺留分を侵害されるケースに応じて、文面をアレンジする必要がありますので、いくつかのパターンを紹介します。
なお、内容証明によって意思表示を確実に到達させるのが重要であり、書面の題名は「通知書」「遺留分侵害額請求書」など、特に決まりはありません。
遺留分の基本について

通常ケースの文例
遺留分侵害額請求書
20XX年XX月XX日
〒XXX-XXXX
東京都中央区銀座〇丁目〇番〇号
相続A子 殿
〒XXX-XXXX
東京都中央区銀座◯丁目◯番〇号
相続B男
父 相続一郎(20XX年XX月XX日死亡)の相続につき、次の通り、遺留分侵害額請求を通知します。
父は、20XX年XX月XX日付公正証書遺言にて、全財産を長女である貴殿に相続させる旨の遺言をしました。しかし、同遺言は父の子である私の遺留分を侵害します。したがって、私は本書面をもって、貴殿に対して遺留分侵害額を請求します。
以上
遺言無効を主張するケースの文例
遺留分侵害額請求をするときに、そもそも遺留分を侵害する原因となった遺言そのものの無効を主張すべきケースがあります。例えば、認知症の家族が、同居の親族に強要されて遺言書を作成したことが疑われる事案です。
このとき、遺留分侵害額請求の通知書に、遺言の無効の主張もあわせて記載します。
通知書
20XX年XX月XX日
(…当事者表示は上記と同じ…)
父 相続一郎(XXXX年XX月XX日死亡)の相続につき、貴殿に対し、次の通り通知します。
父は、20XX年XX月XX日、自筆証書遺言を作成し、全ての財産を長女である貴殿に相続させる旨の遺言をしました。しかし、同遺言は、作成日時時点で重度の認知症にかかっていた父の遺言能力が皆無であったと考えられること、貴殿に著しく有利な内容であること等の事情から、無効であることが明らかです。
なお、仮に上記遺言が有効だったとしても、同遺言は父の子である私の遺留分を侵害するので、本書面をもって貴殿に対して遺留分侵害額請求をします。
以上
遺留分侵害額請求の通知書に必ず書いておくこと
遺留分侵害額請求の通知書は、文章に特に決まりはないものの、権利行使をする意思が明確に伝わる文章とする必要があります。したがって、「遺留分侵害額請求権を講師する」と断定的に記載してください。通知書に必ず記載すべき内容は、次の通りです。
- 誰の相続を対象とするか(被相続人の氏名と、死亡日)
- 誰の遺留分を侵害するか(送付者の氏名)
- 送付者が遺留分を有すること(被相続人との関係、続柄など)
- 遺留分を侵害した方法(生前贈与の年月日、内容、遺言書の作成年月日など)
- 遺留分侵害額請求権を行使する旨
具体的に、侵害の理由となった生前贈与や遺贈の内容、金額が判明していれば、より具体的に記載しておくのが有益です。この際は、相続分の割合に関する法律知識が必要です。
なお、内容証明で送付する場合は、郵便局の定める様式に従う必要があります。文字数や行数に細かいルールがあるため、下記を参考に作成ください。なお、オンラインで出せる「e内容証明(日本郵便)」には文字数や行数の制限がなく便利です。
- 用紙
用紙サイズ、種類の定めはなく、便箋やコピー用紙、原稿用紙などが利用できます。なお、パソコンで印字する場合やe内容証明の利用には、A4用紙がお勧めです。 - 筆記具
筆記具も特に定めはなく、手書きでもパソコンでも可能ですが、手書きの場合はボールペンで記載してください。鉛筆やシャープペンでは消えてしまうので、内容証明という重要な書面には不向きです。 - 文字数・行数
縦書き、横書きいずれの場合も、1行20文字以内、1枚26行以内で作成します。句読点や記号も1文字とします。内容証明は、文字数と行数に厳格な定めがあります。 - 使用できる文字
内容証明は、使用できる文字に制限があり、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、句読点、カッコ、一般的な記号の利用はできるものの、英字は固有名詞以外には使用できません。 - 用紙の枚数
用紙枚数に制限はないものの、枚数に応じて料金が加算されます。2枚以上のときは、同一の通知書であることを示すためにホッチキス止めして全てのつなぎ目に契印を押します。
遺留分侵害額請求の通知書を内容証明で出す理由
遺留分侵害額請求をするのに、その方法の定めは法律上も特にありません。つまり、確実に意思表示が到達するなら、普通郵便でも書留でもよく、メールやLINE、更には口頭であったとしても権利行使そのものは可能です。
しかし、遺留分侵害額請求は、相続のなかでも大きなトラブルに発展する可能性が高いケースです。権利行使された相手は、得られる遺産が減ることになるので、徹底的に争ってきて、紛争が激化します。
このように、トラブルの発端となり、遺産分割の争いにつながりやすい遺留分侵害額請求権の行使は、証拠に残るよう必ず内容証明を利用すべきです。内容証明なら、送付した通知書の内容を、郵便局が証明してくれます。これと共に配達証明を付することによって、発送日と到着日を証拠に残すことができます。
内容証明の出し方は、書面案を3通作成し、郵便局の窓口に提出します。3通のうち1通が相手に送付され、1通は郵便局に保管、1通は差出人の保管となります(カーボン複写タイプの内容証明郵便作成セットも市販されています)。
書面案と封筒には、差出人、受取人の住所、氏名を記載してください。修正を要する場合には「加除訂正」の記載をして押印する必要があるため、印鑑を忘れず持参しましょう。
遺留分侵害額請求は、相続開始を知ったときから1年以内、かつ、相続開始から10年以内に行使しなければなりません。そのため、権利行使を争う相手が「そもそも意思表示が到着していない」と反論したときには、請求した側がその到達を証明しなければならず、この際に内容証明が役立ちます。
遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求の通知書を送る相手方は?
遺留分侵害額請求の通知書を送るとき、その相手方にも注意が必要です。通知書を送るべき相手方を知るには、相続財産調査をして、誰が、いくらの遺産を相続したか調べ、遺留分を計算する必要があります。自分の承継した遺産が遺留分に不足する場合に、余分に財産を相続した人が、請求の相手方になります。
相続財産の調査では、不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書など、多数の資料を取り寄せる必要があります。また、遺留分を確定させるには被相続人の戸籍収集をして、相続人の調査をしなければなりません。
各調査には時間がかかり、遺留分侵害額の期限(1年)までに調査が終わらない場合は、相続人となる人など、とりあえず考えうるすべての相手に対し内容証明で通知書を送付し、時効中断しておく方法が適切です。なお、公正な相続のために、遺留分侵害額請求の相手方の順序、負担額には民法の定めるルールがあります。
遺留分侵害者について

通知書の受け取りを拒否された場合の対応
最後に、遺留分侵害額請求の通知書を、相手が受領拒否した場合の対応を解説します。
内容証明は、受取が必要となるため、受領拒否された場合には送付者に返送されてしまいます。しかし、遺留分侵害額請求権の行使は、内容証明が到達した時点で意思表示の効果が生じるものとされています。つまり、受領拒絶に遭ったとしても、権利行使がなかったことにはなりません。内容証明が返送されても、受取を拒否した時点で内容を知ることができたならば、意思表示は到達したものと評価するのが裁判例の考え方です。
なお、内容証明の受取にはサインが必要ですが、本人が受け取る必要はなく、家族が代わりに受領しても、意思表示は到達したものと扱われます。
したがって、受取拒否が予想される場合にも、内容証明で送付する方法が有効です。
まとめ
今回は、遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)の権利行使をする際の通知書の書き方と、内容証明の送り方について、注意点を踏まえて解説しました。書式を示しておきましたので、ダウンロードしてお使いいただけます。
遺留分侵害額請求の争いにおいて、通知書の送付はあくまでスタート地点です。受領後に相手から連絡があると、いよいよ交渉が始まります。交渉を有利に進めるには、法律知識を有した弁護士に相談するのがよいでしょう。