家族の死に直面したとき、はじめに着手すべき課題が「故人がどのような財産を持っていたか把握する」ということ。相続財産の調査は相続手続きを正確に進めるのに不可欠であり、すべての財産を見落とさず把握しないと、後のトラブルにつながりかねません。
相続財産には、預貯金や現金、不動産、株式など多くの種類があります。財産だけでなく、借金やローンなど負債もまた相続されます。見逃しやすい動産、貴金属や貴重品、デジタル遺品も忘れてはなりません。重要なのは、どのような相続財産があるかを徹底して調査すること。相続が開始したら速やかに調べる必要があります。
本解説では、相続財産調査の重要性と方法、進め方を解説します。相続財産の調査は、自分でもできますが、抜け漏れがあったときのリスクを考えると専門家に依頼するのがお勧めです。
相続財産調査の基本
まず、相続財産調査の基本と、見落としがちな重要なポイントを解説します。
故人が遺した財産を公平に分割するため、相続財産調査が必須です。このプロセスを正確に進めることが、相続人全員が納得のいく遺産分割をする大前提となります。
相続財産調査とは
相続財産調査とは、相続のために故人の財産を詳しく調査することであり、わかりやすくいえば生前に保有していた全試算と負債をリストアップする作業です。
亡くなった方(被相続人)がどのような財産を有していたかを知ることは、遺産分割を公正かつ円滑に進めるための大前提となります。調べる財産は、不動産、銀行預金、株式や生命保険といった全ての財産と、借金やローンなどの債務など多岐に渡ります。目に見える試算だけでなく、経営していた家業の株式やデジタル遺品、海外不動産のように見落としがちな隠れた資産も含みます。
相続財産調査は、故人の意思を尊重するとともに、遺産を公平に分配するのに非常に重要です。遺産分割の最初のステップとして必ず行わなければなりません。その重要性を理解し、必要な場合には専門家のサポートを受け、手順についてアドバイスを受けるべきです。
相続財産調査の重要となる理由
相続財産調査の重要性は、以下の通り3つの大きな理由があります。相続財産調査は相続手続きの大前提であり、その後の財産分割や税務申告に大きく影響します。
相続財産の調査が正確でなかったり、抜け漏れがあったりすると、遺産相続そのものの正確さと公平さが保てなくなり、相続税の申告を誤ってしまうといったリスクがあります。正確な財産の把握なく相続を進め、相続人間で不公平が生じれば、争続に発展する可能性があります。
公平な遺産分割を実現するため
第一に、相続財産調査は、公平な遺産分割を実現するために必須となります。
相続財産の調査が不十分だと、いざ遺産分割の場面になっても、もらえる財産が少ないと感じる相続人から「まだ遺産があるのではないか」「他の共同相続人が財産を隠して独占しようとしているのではないか」といった不満が生じ、話し合いがスムーズに進みません。
遺産分割を行う前にこれらの財産調査を徹底すれば、遺族間のトラブルを最小限に抑え、公平な遺産分割を達成することができます。全ての関係者にとって納得のいく分割を実現するためにも、透明性を確保して調査を進める必要があります。
遺産分割の基本について

相続放棄をすべきか判断するため
第二に、相続財産調査は、相続放棄をすべきかどうかの判断基準を得るのにも重要です。
相続手続きを進める上で、故人が残した借金への対応は重要。相続人は、財産だけでなく借金も引き継ぎますが、このとき財産より借金が多い場合は、相続放棄によってその負担から逃れる選択をすべき場面もあります。相続財産調査が不十分で、財産全体の価値と借金の総額を正しく知れないと、本来なら相続放棄すべき場面で、選択ミスをするおそれがあります。その結果、相続によって承継した故人の負債は、相続人個人の財産から返済していかなければなりません。
相続放棄は期限があり、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければ、単純承認したものとみなされ、その後の相続放棄はできません。速やかに財産と借金のリストアップを進める必要があります。
相続放棄の手続きについて

相続税申告を確実にするため
第三に、相続税申告を確実に進めるにも、相続財産の調査が肝要です。
相続税は、遺産から負債を引いた額が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。財産の総額の把握が不十分だと、いくらの相続税を申告・納付すべきか正しく計算できません。
また、不動産や株式など、評価に争いの生じやすい資産が存在する場合、相続財産の所在を調査するだけでなく、価値の調査も専門家に依頼する必要があります。相続税の申告漏れや、過少申告申告があると、税務署から指摘を受け、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税や、悪質な場合は重加算税といったペナルティが科され、負担が増加してしまいます。
相続財産調査の期限は死後2ヶ月
相続財産調査に、法律に定められた期限はありません。
ただ、その調査の重要性からして、被相続人の死後2カ月以内には完了しておくことを推奨します。相続手続きの期限を考えると、まず到来する重要な期限が、相続放棄の期限(相続開始を知ったときから3ヶ月以内)。これに間に合わせるには、2ヶ月程度で相続財産調査を終え、専門家に相談をし、アドバイスを踏まえて判断する時間の余裕を確保すべきです。
「2ヶ月」というと長いように感じるかもしれませんが、家族の死亡後はすべきことが多く、時間はあっという間に過ぎます。焦って財産を見誤ったり、見落としがあっては本末転倒ですが、注意深く丁寧に、しかしながら速やかに、調査を進める必要があります。相続財産調査にかかる期間はケースによりますが、家族に共有された財産はごく一部で、実際は思いも寄らないものを相続されることも多いもの。予想外に長期間かかると考え、調査は早めに着手した方がよいでしょう。
ミスなく、スピーディに進めるには、専門家に相続財産調査そのものを一任する手が有効です。調査のプロセスのなかで、予期せぬ情報や資産が発見されることがあります。これを手がかりとして、更に調査をしていかなければならないとき、収集すべき必要書類が多岐に渡り、複雑なステップを踏まなければならず、自分で調査をする方法では迅速に進められないおそれがあります。
相続の専門家について

相続財産調査の方法と調べ方
次に、相続財産を調べる方法と、財産ごとの具体的な流れを解説します。
相続財産を見落としなく調べるには、思い込みは禁物です。ここで解説する全ての種類の財産について、「存在しないだろう」と思っても必ず順番に検討してください。相続財産の調査は、正確性と効率を両立させなければならない難しい作業です。
預貯金の調査方法
預貯金は、全ての人の資産のなかに含まれている可能性の高いものであり、必ず調査をする必要があります。亡くなった人が家族のために残していた預貯金の調査は当然ですが、それ以外にも隠された口座がある可能性もあり、全ての口座を特定して、適切に分配しなければなりません。
預貯金を調査する手順は、次の通りです。
資料の収集
故人の遺品を整理し、銀行の通帳やキャッシュカード、ネットバンキングの情報が記載された書類を探し出すことから始めましょう。
金融機関への申出
他の口座も調査する
1つの口座を特定できたからといって安心せず、複数の銀行にいくつか口座があるのではないかと疑い、それぞれの金融機関や支店に問い合わせるようにしてください。金融機関によってはインターネット上で口座照会サービスを運営している機関もあります。
預貯金の調査について
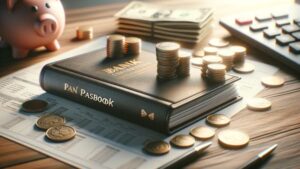
株式・有価証券の調査方法
次に、株式・有価証券を調査します。株式や有価証券は、種類によって調べ方が異なりますので、相続財産の調査方法において特に注意が必要です。家業があったり、経営者や個人事業主であったり、投資運用をしていたりといった故人の生前の働き方、暮らし方によって、株式や有価証券を保有している可能性の高い場合、次の手順にしたがって進めてください。
また、株式の存在がわかったら、評価についても重要です。株価は日々変動するため、正確な評価額を出すには専門家である税理士、会計士のアドバイスを求める必要があります。
上場株式の場合
上場株式が相続財産に含まれる場合には、次のステップで調査してください。現在では、多くの株式会社において株券が発行されていないため、調査は証券口座を特定する必要があります。
証券会社との取引を行っている場合は、年に1度は書類が届く可能性が高いです。そういった書類が故人の遺品に残っていないか確認してください。
過去の銀行の取引履歴から、配当や売却についての記載がないか確認します。
以上の情報から、証券会社が特定できたら、故人名義の証券口座が存在するかどうか、証券会社に照会します。
株式や投資信託などの有価証券は、証券保管振替機構(ほふり)が一括管理しているため、照会によりどこの証券会社・信託銀行に財産を保有しているか確認をすることができます。ただし、照会には1か月ほど時間がかかるため、1.~3.の手続きを先に進めておくことをお勧めします。なお、ほふりからの開示が得られても、各金融機関への照会は別途必要となります。
非上場株式の場合
非上場株式は、相続手続きにおいては特に見逃されやすいので注意が必要です。また、非上場株式には市場価格がないため、株式の評価についても遺族間の争いの種となりやすいです。
非上場株式の調査は、次の手順で進めてください。
- 1株主総会招集通知や確定申告書の控えに記載がないか確認する
- 通帳の入出金記録を確認する
- 株式譲渡契約書、引受書、出資契約書などがないか確認する
非上場株式は上場株式とは異なり検索が困難です。会社によってもどの程度管理しているか異なるため、相続財産に含まれる可能性がある場合、早めに故人に届いた郵便や資料を確認するようにいたしましょう。非上場株式を発見した場合には、会社側との協議も必要となります。株式には譲渡制限が付いていることが多く、相続したといってもすぐに現金化するのは難しいこともあります。
株式の相続税について

国債・投資信託その他の有価証券の場合
相続手続きでは、国債、投資信託、その他有価証券も重要な財産となり、調査が必要です。相続財産の調べ方は、基本的に、上場株式と同じになります。
不動産の調査方法
相続手続きにおいて、重要性が高いのが不動産の調査です。不動産は、価値が高いことが多く、相続財産に占める割合も高くなってしまいます。その分、調査を失敗して見逃したときのリスクも大きいです。また、2024年4月より相続登記の義務化が始まり、相続する不動産があるときは調査によって速やかに見つける必要があります。
不動産の情報は、登記簿謄本や固定資産税評価証明書など、関連する書類に記載されていることが多く、手がかりは見つけやすいです。しかし、その境界や評価が争いになるなど、見つかった後も遺産分割においてはトラブルの原因となります。価値が高いからこそ、取り合いになるため、適切な手順で素早く調査しなければなりません。
不動産の調査は、次の順序で進めてください。
権利証や売買契約書の確認
権利証や売買契約書を確認することで、故人所有の不動産の確認を行いましょう。遠隔地の不動産を所有していると見逃す可能性があるので、注意してください。
登記簿謄本の取得
自宅の所在地の土地建物など、故人の所有となっている可能性の高い不動産に心当たりがある場合には、必ず登記簿謄本を取得して、その所有者を確認してください。
不動産の所在の市役所への名寄帳(課税台帳)・評価証明書の請求
不動産は各市役所で資料を取得することが可能です。特に名寄帳は、すべての物件の一覧図となりますので必ず取得しましょう。自治体によっては免税点未満の物件や共有物件が記載されない場合があるので、必ず【共有も非課税も含むすべての物件】として請求を行うようにします。
公図の取得・周辺土地の確認
故人所有の土地が見つかったとき、周辺地を道路などで所有している可能性もあるので、公図・地図の確認を行いましょう。

生命保険の受取人の調査方法
遺産そのものには含みませんが、相続においては生命保険の受取人の調査も重要です。なお、生命保険があまりに高額で、公平を損なう場合には例外的に遺産に含まれ、遺留分侵害額請求の対象となると判断した裁判例もあります(最高裁平成16年10月29日決定)ので、調査を漏らすと公正な遺産相続が実現できません。
生命保険の調査は、生命保険契約照会制度を利用します。この制度によって、加入している生命保険会社を照会することができます。この照会だけでは、保険内容は分かりませんので、別途保険会社への照会が必要となります。すべてオンラインで完結可能です。
借金の調査方法
相続財産調査では、故人が残した財産の調査と共に故人の借金についても正確に把握することが重要です。負債についての調査は、次の順番で進めてください。相続手続きにおいて故人の借金は見落とされがちですが、相続財産を正しく公平に分配するためには避けて通れません。
自宅に置かれた書類の確認
信用情報はあくまで金融機関からの借入のため、これでは網羅できない個人間の借入を探す必要があります。遺品整理をし、借用書や金銭消費貸借契約書といった書類がないかどうかを確認してください。また、通帳や金融機関の利用履歴を確認し、不自然に多額の入出金がある場合、その用途が借入や返済でないかを確認しましょう。
抵当権などの担保権の確認
不動産を所有している場合には、登記簿を確認し担保が残っていないか確認しましょう。抵当権などの担保が残っている場合には、住宅ローンなどの債務がある可能性が高いです。
債権者への確認
最後に、ここまでの調査によって債務の存在が判明したら、債権者に確認をします。この際、返済額と残債についても調査してください。
相続する借金の調べ方について

相続財産調査の進め方と流れ
次に、相続財産調査の進め方と流れについて解説します。
相続財産の調査には、法律や税務の専門的な知識を求められる場面もありますが、まずは基本的な流れを理解するだけでも、調査を大幅にスムーズに進めることができます。専門家に相談する場合にも、だいたいの財産の所在や価値をリストアップしておくことが役立ちます。
相続財産調査は、故人の財産の「棚卸し」であり、遺産として分配すべき財産の全容を明らかにすることができます。
遺言書を探す
まず、遺言書を探してください。遺言書は、故人の意思を示す書類であり、遺産分割に反映すべき重要なものです。相続財産についての情報が記載されており、今後の調査の指針となるため、必ず発見しておかなければなりません。
【自筆証書遺言の探し方】
- 自宅などの心当たりのある場所を探しましょう。
- 「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合は法務局に保管されているので、法務局への照会を行います。必要書類を準備の上、遺言書保管事実証明書の交付請求を行いましょう。
【公正証書遺言の探し方】
公証役場へ問い合わせましょう。公証役場で遺言を保管している場合には、公証役場に問い合わせを行うことが確認可能です。全国どこの公証役場でも問い合わせは可能ですが、原本の発行ができるのは、遺言を行った公証役場のみになります。
【秘密証書遺言の探し方】
公正証書と同様に、公証役場で遺言を保管している場合には、公証役場に問い合わせを行うことが確認可能です。
遺言書の基本について

必要書類を収集する
相続財産調査を行う際、書類の調査から始めるようにしてください。
相続財産の多くは、書面で記録が遺されています。例えば、預貯金であれば銀行の通帳や明細、不動産であれば登記簿謄本、株式であれば証券口座の明細など、財産の額が大きくなるほど、客観的な証拠にその痕跡が残っています。
相続財産調査の段階で収集しておくべき必要書類には、次のものがあります。
- 通帳、キャッシュカード
- クレジットカード
- 不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)
- 金融機関からの通知書
- 生命保険証券
これらの書類は、それぞれ財産を示す証拠になるだけでなく、お金の流れを判別して、他の遺産を発見するための手がかりとしても機能します。
よくある財産の保管場所を調べる
故人の自宅や、生活拠点、職場といった場所には、重要な財産が隠されている可能性が高いです。よくある財産の保管場所について調べることが、相続財産調査の初動として重要です。現金や貴重品など、財産そのものが保管されている場合に限らず、重要な書類や貴重品などから、意外な財産が発覚することもあります。
デジタル遺品も忘れず調査する
デジタル時代の相続手続きにおいては、デジタル遺品も調査も忘れてはなりません。
誰もがインターネットに接続できる現代において、オンライン上に蓄積された財産や、SNSアカウント、電子マネーやネットバンキング、仮想通貨(暗号資産)など、財産的価値の大きい、いわゆるデジタル遺産が存在することも多いものです。そして、このように近年登場した新しい資産ほど、調査の方法がまだ確立されておらず、相続財産調査が難しい場合があります。
故人のデバイスへのアクセスがパスワードでロックされていたり、プライバシー保護のために情報が得られなかったりするとき、相続財産調査は困難を極めるので、適切に対応するには専門家の力が必要となります。
デジタル遺品について

相続財産目録を作成する
調査の最後に、調べ上げた財産をまとめて記録します。相続財産目録とは、遺産についてリストアップし、その所在や情報を記録した書面です。
相続財産目録を作成すれば、遺産分割や相続税の申告での財産の漏れを防ぐとともに、関係者の共通理解を得られます。これによって、全ての相続人の納得のいく、公平な遺産分割を目指す助けになります。相続財産目録では、不動産、預貯金、株式などの有形資産から、著作権や商標権などの無形資産、負債に至るまで、相続に関わるあらゆる財産の詳細を洗い出し、その価値を正確に評価し、文書に記載しておきます。目録を作成しているうちに、新たな財産に気付く機会となることもあります。
相続財産目録の作成は、相続によるトラブルを未然に防ぐため、調査の精度を高めるために必須といってよいでしょう。
相続財産目録について

法定相続情報証明制度を活用する
法定相続情報証明制度を活用するのも有効です。この制度では、法務局に、必要な戸籍謄本の束と、法定相続情報一覧図を提出することによって、登記官がその後の手続きに利用できる相続関係を証明する書面を発行してくれます。これにより、相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。

相続財産調査は専門家に依頼すべき
相続財産調査によって故人の財産を明らかにすることは、簡単に見えますが、実際には大きな労力と時間がかかり、専門的な知見を要します。網羅的にミスなく調査するには、経験も必要となりますが、相続は人生で何度も起こるものではなく、何度も経験している専門家に依頼すべきです。
自分で相続財産調査をするリスク
相続財産調査は、故人の保有していた財産を調べることですので、これを行うのに特に資格が必要なわけではなく、相続人自身ですることもできます。
しかし、自分で相続財産調査をするのにはリスクが伴います。最も大きなリスクが、財産の見落としです。本解説の通り、簡単にわかっている財産も多くあるでしょうが、不動産や株式、外国にある資産などは、見つけるのが難しいこともあります。また、評価には専門的な知識を要する場合も多く、発見してもなお、結局は専門家の助けを借りなければ分割できないことも多いものです。
これらの遺産の調査ができておらず、見落とすと、相続人間で不公平感が生じ、最悪の場合、家族間の争いや遺産分割のトラブルに発展してしまいます。
専門家による相続財産調査のメリット
専門家に相続財産調査を依頼することによって、適切な知識と経験をもとに、見落としや評価のミスを減らすことができます。安心して相続を進めるためにも、その最初の一歩である相続財産調査を専門家に依頼することを検討してください。
相続手続きを豊富に取り扱う専門家のサポートがあれば、相続財産調査だけでなく、相続手続きの全般について助けを借りることができます。例えば、相続財産調査によって発見された不動産の相続登記については司法書士、遺産に課される相続税の申告・納付には税理士、そして、多くの手を尽くしてもなお遺産分割に争いが生じてしまったときには弁護士といった専門家の力を借りることが、最小限にリスクを押さえて手続きを円滑に進めるのに最良の選択だといえます。
専門家に相続財産調査を依頼する費用
相続に関する調査を専門家に任せれば、ミスなく正確に進められますが、このときいくらの費用がかかるかが不安になるでしょう。そこで最後に、相続財産調査を専門家に依頼するときに必要となる費用について解説します(なお、実費は別途かかります)。
| 業務内容 | 費用 |
|---|---|
| 相続登記基本報酬 | 5万円/1申請につき (筆数や金額により加算がありうる) |
| 銀行口座/証券会社残高証明書 | 1行につき5万円 |
| 銀行口座/証券会社取引履歴 | 1行につき5万円 |
| 戸籍取得 | 1件につき1,500円 |
| 謄本取得 | 1件につき1,000円 |
| 法定相続情報一覧図作成 | 2万円 ※相続関係図のみ作成は1万8,000円 |
| 死後手続き (諸契約解約・年金・健康保険等) | 12万円(12時間まで) |
| 金融機関の解約手続き | 1行につき8万円 |
相続に強い司法書士の選び方について
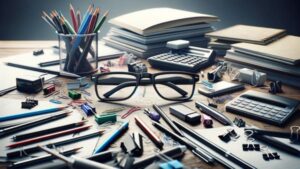
まとめ
本解説では、相続手続きにおける相続財産調査の重要性と、正確な調査のための方法について解説しました。
相続財産の調べ方を知り、正確に遺産を把握することは、公平でトラブルのない遺産分割に資するだけでなく、相続放棄の判断や、相続税の計算を誤らないためにも重要なことです。プラスの財産を取り合うだけでなく、マイナスの財産、つまりは負債も正確に把握するようにしてください。
相続財産が多数あったり、調べ方が複雑だったりする場合、専門家のアドバイスが有用です。弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを行うことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。また、財産調査は時間と労力が要るため、早めに着手し計画的に進めるようにしてください。


