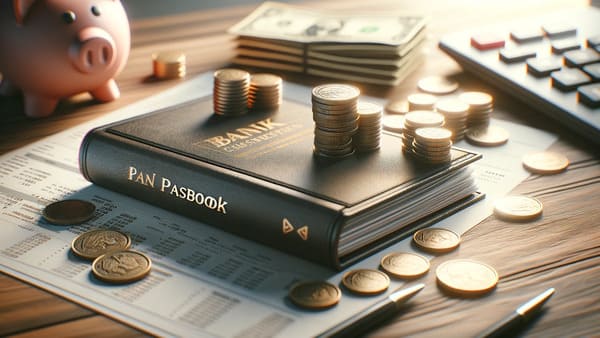ほとんどの場合、家族が亡くなった際には、何らかの形で預貯金が存在します。遺産の一部となるこれらの預貯金について、どの金融機関にいくらくらいあるか、知っておかなければいけません。
もし遺産となる預貯金の存在を見落としてしまうと、名義変更や引き出しの機会を逃したり、相続税の申告を漏らしたりするリスクが生じます。これらの問題を防ぐためにも、相続財産の調査、特に、遺産となる預貯金の金額とその所在をしっかりと把握しておくことは重要です。
今回は、相続財産となる預貯金の所在と金額を調査する方法について解説します。
まず、通帳・キャッシュカード・振込明細を探す
まず、通帳、キャッシュカード、振込明細といった身近な手がかりを探しましょう。
銀行など金融機関に、亡くなった方(被相続人)の預貯金が存在するなら、必ず持ち主の手持ちにあるであろうものだからです。被相続人が大切にしていた財布やバッグに入っていることが多く、遺品整理の際に部屋から見つかることもあります。
また、通帳やキャッシュカードを大切に保管する方には、デスクやタンス、人によっては仏壇や金庫、冷蔵庫などに保管している方もいます。銀行の貸金庫に預けている方もいます。通帳は、その履歴が財産の流れを知る大きな手がかりになりますから、必ず見つけてください。
残高証明書を取得する
次に、預貯金が存在する可能性のある金融機関をしれたら、残高証明書を取り寄せることで、どれだけの預金が残っているかを調べます。残高証明書は「相続開始時(死亡時)の解約価額(既経過利息込み)」の金額を知る必要があります。
「家族が亡くなり相続を開始したので、残高を知りたい」と銀行などの窓口に伝えれば、上記内容を含んだ残高証明書を出してくれます。
なお、1つの銀行の通帳が発見されたときは、そこに記載された支店だけでなく、取引支店すべてに存在する口座の残高証明書を要求するようにしてください。このような調べ方を「全店照会」と呼びます。ゆうちょ銀行の場合、かんぽ保険も含めた網羅的な調査が必要です。
隠れた預貯金を発見する方法は?
次に、隠れた預貯金を発見する方法を解説します。
通帳やキャッシュカードなどがわかりやすいところに保管されていればすぐに発見できるでしょうが、実際は、相続財産のなかには隠れていて見つかりづらい口座もあります。
- 特定の用途の引落しにのみ利用する口座
- 過去に利用していたが現在は利用していない口座(前職の給与口座など)
- 長期間の貯蓄を目的とする口座
- 隠し口座(へそくり、愛人用、脱税用など)
- 被相続人すら存在を忘れている口座
これらの口座は、通常の方法では発見が困難ですから、発見しやすい探し方を知る必要があります。
口座間の資金移動から発見する
亡くなった方(被相続人)が、複数の金融機関に口座を持っているときには、口座間で資金移動をしていることがあります。このとき、出金元、出金先のいずれの口座にも、振替に関する情報が記載されるため、一方を見つければ、他方も特定することができます。
銀行は、過去10年程度の取引履歴を保存しているため、開示を求めることで、資金移動先の預貯金口座を調査し、発見することができます。
遺品整理で発見する
被相続人の使用していた部屋を遺品整理するときに、通帳やキャッシュカードを見つけることがあります。また、通帳などの口座を明らかに示すものでなくても、何気ない所持品がヒントとなって預貯金を発見できることがあります。
- 銀行の封筒
- 金融機関のカレンダーや手帳、ボールペンなど
- 金融機関からの郵送物
- パンフレット、案内状
少しでも預貯金の存在する可能性があれば、照会をかけてみましょう。
貸金庫から預貯金を発見する
被相続人が貸金庫に財産を保管している場合、その中身は預貯金の調査においても大きな手がかりとなります。貸金庫を開けてもらうには、相続人全員が立ち会うのが原則であり、立ち会えない相続人からは委任状をもらう必要があります。
貸金庫を利用しているかどうかは、次の資料によって判明することが多いです。
- 貸金庫の利用契約書
- 通帳から貸金庫の利用料の引き落としがあった
また、相続人間の公平のために公証人が同席することもあります。詳しい手続きや必要書類は、金融機関ごとに確認してください。
遺言から預貯金を発見する
遺言書の内容に、預貯金口座の分割方法が記載されていることがあります。「○○銀行の預貯金は、妻に相続させる」といったイメージです。このとき、遺言書に記載されているが通帳やキャッシュカードが手元にない預貯金があるなら、その金融機関に残高証明、取引履歴の開示を求めるべきです。
遺言書の基本について

パソコンから発見する
最近では、ネットバンキングを利用し、通帳やキャッシュカードを持っていない方も増えました。インターネット銀行ではそもそも通帳を発行しないこともあります。このような口座を見つけるには、故人のパソコンの調査が必要となります。
パソコンの利用履歴やブックマークを調査し、金融機関にアクセスしていないか調べてください。生前に家族が使用していたパソコンの履歴が、預貯金発見の手がかりとなります。
デジタル遺品について

手がかりを得たら全店照会する
以上のヒントから預貯金の手がかりを得たら、金融機関に、残高証明書と取引履歴の開示を求めます。このとき、1つの支店だけでなく、他の支店にも口座がある可能性を考え、全店照会するのが基本です。
1つの手がかりから、その金融機関の管理する全ての口座を探し出すのが、全店照会の方法です。全店照会は、1つの支店に問い合わせることで実行することができます。全店照会の際の必要書類は、次の通りです。
- 被相続人の亡くなったことが分かる戸籍
- 被相続人と相続人の関係の分かる戸籍
- 相続人の身分証明書
- (代理人が請求する場合)委任状
口座の有無の問い合わせには印鑑証明書の添付を要求する金融機関もあるので、事前に問い合わせましょう。全店照会でわかるのは、預貯金口座の存在のみなので、その後に更に残高証明書、取引履歴の開示を求める必要があります。口座の有無の問い合わせでは、開設時から死亡までの間に住所や氏名を変更している場合には、その変更の履歴がわかる住民票や戸籍の附票を求められることがあります。
なお、いわゆる休眠預金の場合は、被相続人の住所氏名だけでは調べられない場合がほとんどで、その休眠預金の支店、口座の種別、口座番号が必要になってしまいます。
名義預金に注意する
預金の出資者と名義人の違うものを、名義預金といいます。例えば、孫名義で、実際には祖父がためている口座が典型例です。名義預金は、その名義人の財産ではなく、実際に支出している人の財産と評価されますので、相続財産となるものを見逃してはなりません。
特に、定期預金の場合には、子供名義、孫名義など、複数の名義を活用して貯蓄している人は少なくありません。被相続人の子供や孫が、若年で収入がさほどないのに多額の預金を持っているような場合には、名義預金の可能性を疑い、慎重に調査しなければなりません。
預貯金の調査・発見に失敗したときのデメリット
預貯金の調査を怠り、本来なら相続財産となるはずだった口座を見逃すことには、大きなデメリットがあります。発見に失敗したリスクは「預貯金が利用できない」というに留まりません。
税務調査で課税漏れを指摘される
税務調査において、預貯金に対する相続税の課税漏れは非常によく指摘される事項です。名義預金を見逃したことで支払うべき税額に漏れがあるケースは少なくありません。
申告漏れの相続税を税務署に指摘されると、追徴税、重加算税といった支払いが必要となる結果、より多額の税金を支払わなければならず、相続で損してしまいます。国税庁の調査によると、相続税の申告漏れのうち約33%(1070億円)もの割合が、預貯金の申告漏れだったという統計もあります。
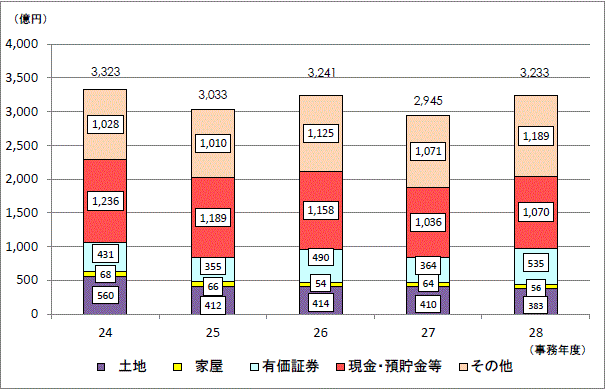
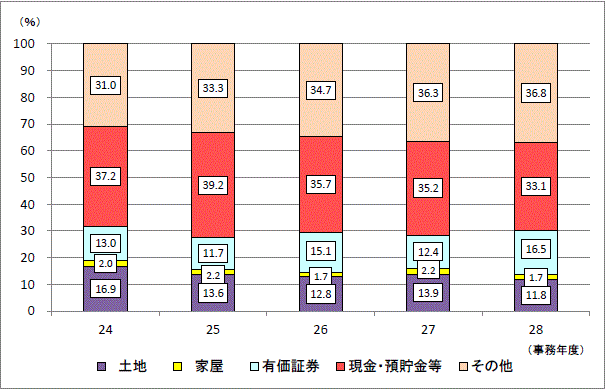
相続税の税務調査について

預貯金の現金化を見逃す
通帳や取引履歴を入手できたときは、その記載内容もよく吟味してください。特に、直近数年内に大きな引き出しがないかに注意しましょう。現金化された預貯金が、相続財産として手元に残っている可能性があるからです。
定額預金や積立金が満期となって解約されている場合には、その金額がどの口座に振り込まれたか、どんな用途に費消されたかを調査し、現金としてタンス預金になっている可能性も疑ってください。その資金使途を追うことで、不動産などの新たな相続財産が発見されることもあります。
生前贈与を見逃す
預貯金を現金化し、相続人その他の第三者に贈与しているケースもあります。そのため、通帳から大きな金額が引き出されているとき、誰かに贈与していないかも調査します。基礎控除を超える贈与であれば、贈与税を払った記録があるかどうかも確認してください。
生前贈与が多額になると、相続人間の公平を保ちづらくなります。このような不公平を解消するのが特別受益という考え方であり、遺産分割の際に特別な計算方法をする必要があります。預貯金の調査に失敗すると、特別受益を主張する機会も失うこととなります。
預貯金が消滅してしまう
預貯金を発見できず、名義変更したり解約したりしないまま長年放置すると、消滅してしまう危険があります。つまり、相続財産を永遠に失ってしまうリスクがあるのです。
長年放置された預貯金は「休眠預金」と呼ばれます。金融機関は、休眠預金の預金者に連絡し、連絡がとれないときにはサイト上で公告して、預金保険機構に休眠預金を移すことができます。預金者はいつでも払い戻しできるのが原則ですが、既に死亡していると休眠預金の存在を知るのは難しく、払い戻しに必要な資料を集めるのも困難です。つまり、事実上、預貯金の払い戻しを受けられなくなるおそれがあります。
相続財産調査について

まとめ
今回は、相続財産のなかに預貯金があるとき、その調査方法について解説しました。誰しもが関係する可能性の高いケースなので、ぜひ参考にしてください。
通帳やキャッシュカード、クレジットカードなどが手元にあれば、預貯金が存在することは明らかです。しかし、隠れた預金口座を探すには、ノウハウが必要です。預貯金の存在を見逃していると、後から税務署に指摘されて相続税を徴収されたり、預金が消失してしまったりする危険があります。