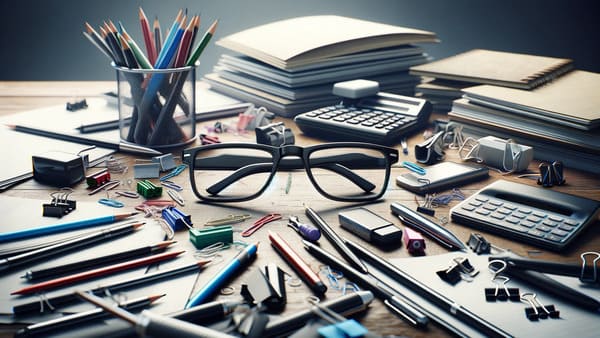相続には複雑な手続きが多く必要となります。そのなかで遺産に不動産を含むケースで重要なのが相続登記であり、これについて支援する専門家が司法書士です。司法書士は、不動産登記、商業登記などの登記の専門家です。
家族が亡くなり、不動産が相続されると、相続登記をして名義変更をします。相続人自身でもできますが、必要書類が多かったり手続きに手間がかかったりするので、専門家に依頼するのがお勧めです。このとき、数多くいる司法書士から、相続を得意とする人を選ぶ必要があります。
今回は、相続において信頼できる司法書士を見つけるポイントと選び方の基準を解説します。
相続における司法書士の役割の重要性
家族が亡くなり、相続が発生すると、様々な手続きが必要となります。おおまかにいうと、次のステップで進行します。
被相続人が死亡すると、相続が開始されます。
相続税が発生する場合、相続税の申告と納付が必要です。
司法書士は、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。上記のステップのなかで、特に重要な司法書士の業務が、相続登記です。ただし、それ以外にも、遺産の調査や戸籍の収集、もめるほどではない遺産分割協議をより円滑に進めるための支援やアドバイス、といった業務を司法書士が担当することもあります。
なお、遺産分割協議がもめるケースでは、司法書士ではなく弁護士に任せるべきです。司法書士では、裁判で争う場合に代理できる訴額に制限(140万円未満まで)があり、弁護士でなければ全てのトラブルの代理を任せることができないからです。
司法書士の重要性は、専門的な知識と経験を持って、相続の手続き面について効率よく進むようサポートすることです。弁護士が争いのある相続の支援であるのに対し、司法書士は平常時の相続がスムーズに進むための支援と考えてください。
相続に強い弁護士の選び方について

相続に強い司法書士の選び方
次に、相続に強い司法書士の選び方について解説します。司法書士の専門分野も様々で、法人登記を主に担当し、相続に関する業務を行わない人もいます。相続問題を任せるなら、得意な司法書士を見極めなければなりません。
必要な資質とスキル
相続に強い司法書士が持っているべき資質とスキルは、次のようなものが考えられます。
- 相続法に関する法律知識
まず、相続法に関する幅広い知識がなければ、相続に対応できる司法書士とはいえません。特に、相続登記を担当する際には、民法だけでなく不動産登記法の専門知識も大切です。 - 経験と実績
相続手続きに関する豊富な実務経験が必要です。特に複雑な遺産分割が絡む事案においては、相続登記を担当する司法書士も、法律や税務の知識を有している必要があります。 - コミュニケーション能力
相続人間の感情的な問題に切り込むため、コミュニケーション能力が必要です。争いのない事案のサポートをするにしても、司法書士が加わりかえって対立を運では元も子もありません。 - 秘密保持の徹底
相続問題は、家族の秘密に関することで、多くの個人情報が含まれます。プロとして秘密保持を徹底し、事務所のセキュリティも万全である必要があります。
選び方の基準とポイント
相続に強い司法書士を選ぶことができるかどうかは、相続手続きの成功に大きく影響します。その判断基準とポイントを理解し、信頼できる専門家を選んでください。
相続に関する豊富な知識
相続に特化した司法書士を選ぶようにしましょう。登記のことだけに限定せず、相続問題を多く解決し、法律知識やノウハウを有する司法書士がお勧めです。相続についての専門性は、サイトにおける情報発信や、初回相談時の質問への回答で確かめるようにします。
良い評判や口コミ
司法書士は、士業のなかでも特に一般の方との接点が少ないことが多く、だからこそ選定の際には口コミが重要です。特に、士業内で高評価な司法書士は、良い司法書士である可能性が高いため、相続を任せる弁護士や税理士に紹介を依頼するのが適切な探し方です。
料金体系の透明性
不明瞭な料金体系はトラブルになりやすいため、依頼は避けましょう。司法書士報酬はもちろんのこと相続登記では印紙や登録免許税などの多くの実費が発生します。その点もわかりやすく説明してくれるのが良い司法書士です。ざっくりとしか説明されないと、予想外の出費となってしまいます。
相続登記にかかる費用について

親身になって話を聞いてくれる
司法書士のなかには、顧客対応があまりなく、事務的な登記手続きを引き受ける人もいますが、相続業務は事務作業ばかりではありません。コミュニケーション力があるかは、初回相談の印象の良さで確認するのがよいです。親身になって聞いてくれる司法書士を選ぶようにしてください。
アクセスとレスポンスの良さ
相続登記の手続きは、法務局に行ったり現地調査したりと移動がつきもの。相続した不動産の近くに事務所があるなど、アクセスが良いに越したことはありません。また、多くの手続書類を集めなければならずやりとりが多くなるので、レスポンスの早い司法書士を選ばないとストレスになります。このような方だと、緊急のトラブルにもスピーディに対処してくれます。
正しい司法書士選びに関するアドバイス
司法書士は、特に都心部であればとても多く存在します。そして、相続を得意分野とする人もいればそうでない人もいます。人間的なタイプも様々です。このとき、良い司法書士を見分けるにあたり、最後に確認するのは結局のところ「相性」です。相性の良い司法書士でなければ、こまめな連絡は逆にストレスとなってしまいます。
このような相性や性格は、会って確認するのが一番です。初回の面談時に役立つ、司法書士のスキルを試す質問リストについても共有しておきます。尋問のようになってしまっては失礼でしょうが、あくまで参考として活用ください。
- 専門性に関する質問
「司法書士として何年目か」「相続に関する資格を有しているか」「相続に関する研修を受けたことがあるか」「複雑な案件の取扱いがあるか」「相続に強い他士業の紹介が可能か」 - 料金体系に関する質問
「相続手続きの司法書士費用はどう定めているか」「相続登記に必要な実費を説明できるか」「追加費用が発生する場合があるか」 - 相続手続きの流れに関する質問
「相続手続きの全体の流れを説明できるか」 - コミュニケーションに関する質問
「手続きの進行状況をどのように報告してくれるか」「緊急時に連絡手段はどのようにしているか」「レスポンスの期限にルールを定めているか」 - 過去の実績に関する質問
「成功例と失敗例を教えてください」「過去のお客さんの評価はあるか」「解決事例で印象に残っているものはあるか」 - 秘密保持と個人情報の取扱いに関する質問
「クライアントの情報をどう保管しているか」
経験値の豊富な司法書士であれば、相続登記に関する知識、ノウハウ的な面だけでなく、顧客対応についても十分な配慮が行き届き、しっかりとお答えしてもらえるはずです。また、相続を多く扱う司法書士なら、他士業とのチーム連携をしており、良い紹介を受けられます。
相続問題の専門家について

相続における司法書士のサポートを得る方法
最後に、依頼する司法書士を決めたら、具体的にサポートを得る方法を解説します。司法書士には、次の方法で相談し、依頼を進めてください。
まずは、問い合わせフォームや電話番号などで、初回相談の予約をとってください。相談前に、サイト上でプロフィールや経歴を調べておきましょう。予約時の事務員の対応が不誠実な事務所には、この段階で相談を取りやめておくべきです。
相談の予約日に実際に事務所にいき、司法書士と対面で相談します。初回相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないわけではないので、資質やスキルの確認の場として活用しましょう。。相続登記業務を依頼するとき、必ず事前に見積書をもらってから委任契約書を結ぶようにしてください。
まとめ
今回は、相続に強い司法書士の選び方を解説しました。司法書士は、相続の場面で、特に遺産に不動産が含まれるときに相続登記を担当する重要な役割を担います。相続のスムーズな解決には、司法書士の働きが不可欠といってよいでしょう。
相続登記をはじめとした相続手続きは複雑であり、戸籍収集などの面倒な作業を司法書士に依頼するほうが解決まで早く進みます。司法書士は、紛争化する事前の準備に力を発揮します。