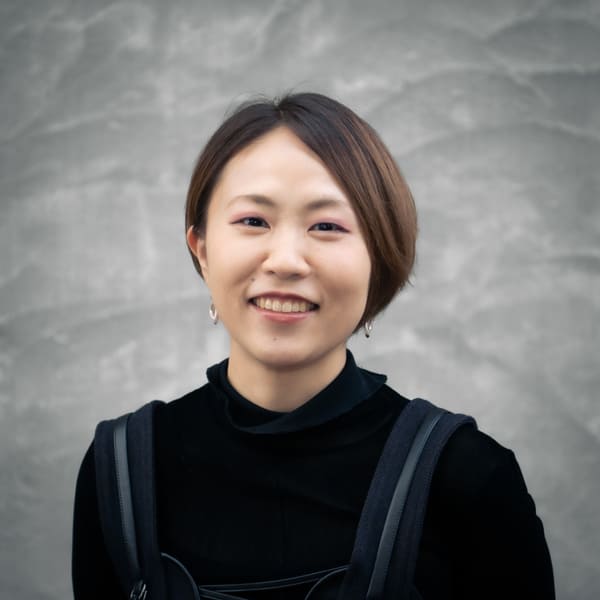遺産に不動産が含まれるとき、遺産分割後にその登記名義を変更する必要があります。これが相続登記です。相続登記は自分でもできますが、複雑な手続きなので専門性の高い司法書士に任せるほうがミスなくスムーズに進み、結果的に費用の節約にも繋がります。
このとき、相続登記を任せることによってかかる費用の相場を知っておくことが大切です。相続登記の手続きには、法務局に支払う実費が複数あります。不明瞭なまま進めると、予想外の出費がかさんでしまいます。司法書士費用も見込んでおかなければなりません。
今回は、相続登記にかかる費用について、詳しく解説します。
相続登記の基本と必要性
まず、相続登記とはどのような手続きか、基本を解説します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続を原因とした不動産所有権の移転を、登記に反映する手続きです。相続による承継について不動産の名義変更をするのが、相続登記の意味です。
令和6年4月1日より相続登記の義務化がされ、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、また、第三者対抗要件となるため、相続で取得した不動産を失わないためにも速やかに進める必要があります。遺産分割後、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合にも、相続登記が終わっていないと進められません。相続登記は自分でもできますが、必要書類を集めて司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記の手続きについて

相続登記にかかる3つの費用
相続登記には主に次の3つの費用がかかります。これらの費用が具体的にいくらになるのかは、不動産の価額や登記の煩雑さによっても変わります。
- 司法書士報酬
相続登記を専門家である司法書士に依頼する際にかかる費用です。 - 登録免許税
不動産の相続登記の際に要する税金であり、不動産の評価額に応じて算出されます。 - 必要書類の取得費用
不動産登記の際に必要書類となる戸籍や登記簿を収集する際の費用がかかります。比較的少額ではありますが、必要な書類が多数ある場合、一定の金額になります。
これらの費用の合計が、相続登記にかかる総費用となります。相続登記の費用は、事前にしっかりと理解し、準備することが重要です。
相続登記の費用の相場
次に、相続登記にかかる3つの費目を知った上で、それぞれの相場について解説します。
なお、司法書士に依頼する場合には、委任前に費用の見積もりが可能なので、納得できるまで質問するようにしましょう。また、見積もりは書面で交付してもらうようにしてください。
司法書士費用の相場
司法書士への報酬は、相続登記について依頼したとき、平均的に2万円から10万円程度が相場です。事務所によって料金体系が異なるので、複数の司法書士から見積もりを取るのがお勧めです。また、相続登記とあわせて戸籍収集を依頼することもでき、1通あたり1000円程度の実費を要します。
なお、上記の費用の相場は、以下のような事情で変動します。
- 不動産の価額
相続登記の対象となる不動産の価額が高いほど、登記に関わる責任とリスクが大きくなるため、報酬が高くなる傾向にあります。 - 対象となる不動産の数
不動産の種類によって費用が異なることはあまりないですが、不動産の数が多いときや、法務局の管轄が複数あるとき、業務量が増えると報酬が加算される傾向にあります。 - 手続きの複雑さ
相続人の数が多い、遺言書がある、遺産分割協議が長期化したなど、手続きが複雑になるほど業務量が多く、報酬が高くなります。
相続登記の費用は、個々のケースによって大きく異なるため、事前にしっかりと相談してから依頼しなければなりません。
登録免許税の計算方法
相続登記にかかる費用のうち、最も大きな割合を占めるのが登録免許税です。相続登記にかかる登録免許税の計算方法は、次のように算出されます。
- 登録免許税 = 不動産の評価額 × 0.4%
不動産の評価額は、固定資産税評価額によって定めます。不動産が複数ある場合には、相続登記の対象となる全ての不動産の合計額が課税対象となります。なお、評価額の1000円未満は切り捨てで計算されます。
なお、評価額100万円以下の土地については、登録免許税が非課税となる免税措置があります(令和7年3月31日まで)。
土地売却にかかる費用について

必要書類の取得費用
必要書類の取得費用については、どのような資料が、何通必要か、といった事情によって変動します。ただ、相続登記を進めるのみでなく、その前後には遺産の調査(相続財産調査)から相続人の確定、相続税の申告など様々な手続きがあり、それぞれの必要資料は重複していて流用可能なものもあります。
ここでは、相続手続き一般に、必要となる書類の取得費用について、相場を紹介します。
- 登記事項証明書
不動産登記についての証明書。取得費用は1通600円。 - 固定資産税評価証明書
固定資産課税台帳に記載された不動産の評価の証明書。取得費用は1通300円前後だが市区町村ごとに異なる。 - 名寄帳
不動産ごとに記録された課税台帳で、所有者ごとにまとめた一覧図。1通につき300円前後。 - 相続関係を証明する戸籍など
戸籍、除籍、改製原戸籍など、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要。1通につき450円〜750円程度で、相続に必要な分をまとめて1万円〜2万円程度となるケースが多い。 - 住民票
不動産の所有権を取得する人の住民票が必要。1通200円〜400円程度。 - 印鑑証明書
遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付する。取得費用は1通300円程度。
相続手続きに必要な資料のなかでも、戸籍は、身分関係の変動の多い人が亡くなった場合にはかなりの通数を必要とすることが多く、収集に手間がかかることがあります。このようなケースこそ、専門家である司法書士に任せるメリットが大きいといえるでしょう。
相続に必要な戸籍の集め方について

相続登記にかかる費用を安く抑える方法
次に、相続登記にかかる費用を、少しでも安く抑える方法について解説します。なお、費用を節約することにはリスクも付きものですので、慎重に進める必要があります。無理な節約をしてトラブルが起これば、かえってコストがかかってしまいます。
自分でできることは自力で行う
相続登記をするには、遺産を調査したり、相続人を確定したりすることが必要となります。これらの手続きは、戸籍や登記簿を取得するなど、必ずしも専門家でなくても入手できる情報から分かることが多くあります。少しでも費用をかけたくないなら、これら事前の調査は自分で行う手があります。
ただし、自分でする手続きにはリスクもあります。極論すれば相続登記も自分でできるわけですが、書類の収集に漏れがあると時間がかかり、法的な誤りがあると、最悪は遺産分割が無効となり、やり直さねばならない危険もあります。手続きが遅延するのは当然、更に無用な時間と労力を負担しなければならなくなります。
相続登記の費用を抑えるためには、自分でできる作業を理解し、そのリスクを考慮して、必要に応じて専門家のサポートを受けるバランスが重要です。
相続登記を自分でする方法について

遺産分割でもめない
遺産分割をスムーズに進め、もめないことは、結果的にかかる費用を低くすることにつながります。そこに関わる専門家も、トラブルになって長期化するようなことなく、円滑に進行するならば、作業の複雑さが小さくて済むからです。
遺産分割がもめる理由と対処法について

複数の司法書士から見積もりを取得する
司法書士によって報酬体系が異なるので、依頼する前には複数の司法書士を比較し、見積もりを取得するのが有効です。ただし、安い司法書士が良いサービスを提供してくれるとは限りません。複雑な相続のケースほど、専門性で選ぶことを推奨します。
相続に強い司法書士の選び方について
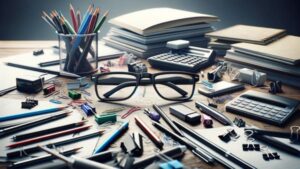
費用対効果を考慮して相続登記を進めるのがポイント
相続登記の手続きは、非常に複雑です。そのため、費用がかかるのは惜しいでしょうが、大切なことは、費用をできるだけ安く済ませることよりも、合理的な費用で、費用対効果を意識して進めることです。要は、コストパフォーマンスが大切になってきます。
そしてこのことは、司法書士選びでも変わります。良い司法書士に依頼すれば、さほど高額でない費用で良いサービスが提供されるでしょうが、悪い司法書士だと、費用を払った割に大した効果を得られないという思いを抱くこともあります。
正しい知識をもって進めなければなりません。専門知識なく進めてしまうと、失敗は取り返しのつかない事態を招きますし、費用が追加でかかることもあります。また、相続登記の提出先である法務局は平日日中しか開いておらず、仕事を休んで出向くのも手間でしょう。相続した不動産が遠方にあるとき、郵送によって対応するなどしても時間がかかります。
これらの手間や負担に対して、司法書士は全てを代わりにしてくれます。また、専門性の高い司法書士なら、相続に関する知識や経験を提供してくれるでしょう。司法書士費用などの相続登記にかかる費用の相場が、高いと感じるかどうか、真剣にご検討ください。
まとめ
今回は、相続登記にかかる費用について、相場感を解説しました。相続登記の際には、司法書士費用と実費の双方がかかります。それぞれ、相場を知り、高くないか検討すべきです。
相続登記は、専門知識を要し、必要資料の収集も煩雑です。司法書士に代行を依頼し、一定の費用を払うのが合理的だと感じる人も多いはずです。自分でやってミスをしたとき、その過ちは相続登記のみに収まらず、遺産分割を含めた相続全体に波及するおそれもあります。
相続登記で司法書士に払う費用は、その過程で得られる安心感と確実性の対価でもあります。