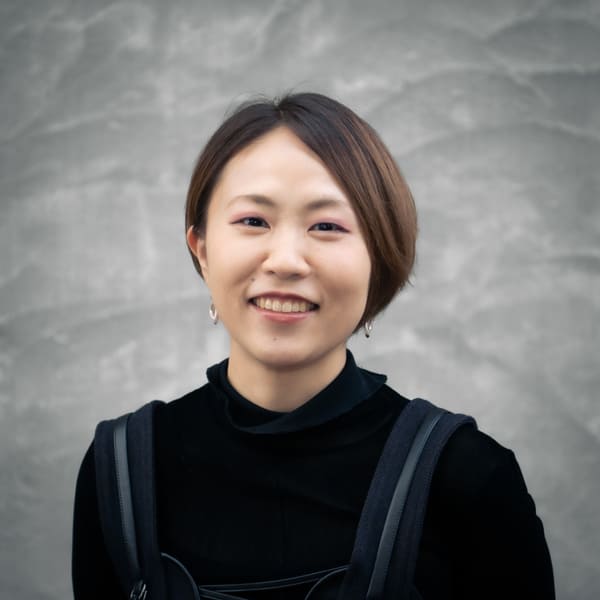相続登記は故人が残した不動産を、相続人に移転するための法的手続きです。複雑なこともあるので司法書士に依頼する人は多いですが、気になるのが費用、つまりは司法書士報酬のこと。費用をできるだけ節約したいなら、自分でやる手もあります。
ただ、相続登記を自分でするには、その手続きについて深く理解する必要があります。自分で相続登記をすることもできるにはできるのですが、必要書類に漏れがあったり、進め方にミスがあったりすると、思わぬ不利益を被るリスクがあります。
今回は、相続登記を自分でする際の手順、必要書類や注意点を解説します。
相続登記の基本
相続登記は、故人の不動産が法的に誰のものであるかを明確にするための登記手続きです。この手続きを通じて、不動産の所有権が亡くなった方(被相続人)から相続人へと移転されます。登記は、売買や贈与だけでなく、相続であっても第三者に所有権を主張する大切な役割を果たし、そのために行う大切なプロセスが相続登記です。
相続登記には、民法や不動産登記法など、複数の法律が関連しています。土地や建物など、不動産が遺産に含まれる相続では、相続登記は欠かせません。相続登記は、遺言か遺産分割に基づいて行いますが、遺言がない限り相続人間の合意が必要です。
相続登記の手続きについて

相続登記は自分でできる?
そもそも相続登記は、本人申請が原則です。つまり、相続登記は自分でできるのが基本となります。相続登記は、相続人本人が申請書を作成し、必要書類を添付して法務局似提出するのが原則だからです。司法書士を依頼するケースは多いですが、あくまで「本人の代わりに」申請しているに過ぎません。司法書士の不動産ではないのですから、当然です。
ただ、相続登記は、ミスなく確実に進める必要があります。登記は第三者対抗要件の役割を果たすために、誤りがあると資産を失う危険があります。法律知識や裁判の知識から、法務局における実務的な扱いを理解しておく必要があります。
相続登記を自分で進めるときの方法と必要書類
次に、自分で進める方に向けて、相続登記の方法と必要書類を解説します。
必要書類
相続登記の手続きを自分で行うには、まず必要書類の準備から始めます。主な書類には、次のものがあります。
これらの書類は、市区町村役場や法務局で取得でき、自分でやる場合でもその手数料は節約できません。また、遠方のものを郵送で取得したり、戸籍について遡って取得したりといった必要があるときには収集には時間と手間がかかります。
なお、令和6年3月1日より運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付身分証があれば、最寄りの市区町村の窓口で全国の戸籍が取得できる「広域交付制度」が始まります。これにより戸籍取得の手間は減りますが、取得できるのは本人の直系(祖父母、父母、子供、孫)のみであり、兄弟姉妹の戸籍や戸籍の附票は必ず窓口の手続きを要します。
手続きの流れ
手続きの流れは、まず遺言を確認し、なければ遺産分割協議を行い、これらの流れによって誰がどの不動産を相続するかを決めます。誰がどの不動産を相続するのかが決まったら、遺産分割協議書を作成し、全相続人の署名と実印による押印を得た後、必要書類を整えて法務局に提出します。
相続登記を自分でする場合には、相続登記申請書を自分で作成する必要があります。相続登記の手続きは複雑であり、不動産や相続人、被相続人の情報を誤りないよう記入しなければなりません。誤記があると受理されないため、注意深く確認してください。
なお、相続登記を自分で完了することができたとしても最後まで油断せず、終了後に交付される登記識別情報通知書(いわゆる権利証の代わりとなるもの)を大切に保管し、紛失しないように注意してください。
自分で相続登記をするメリット
次に、自分で相続登記を行うときのメリットについて解説します。実際に、リスクはあるもののメリットは確かに存在するので、簡易な事案や、ミスなく正確に進められる相続人については、自身で進める手も効果的です。
費用が節約できる
自分で相続登記を行う最大のメリットは、司法書士などの専門家に支払う費用を節約できることです。相続登記にかかる費用は、案件が複雑であったり相続した不動産の数が多かったりすると、数十万など相当な費用となることがあります。これらの費用は、自分でやるのならかかりません。
なお、役所や法務局に払う実費や登録免許税などは、相続登記そのものは自分でできるとしてもかかる費用です。登録免許税は不動産の価額に応じて決定されるため、価値の高い不動産を相続した場合には、自分で登記を進めても出費がかさむ可能性があります。
相続登記の費用について

相続の問題をよく理解できる
自分で相続登記を行うことによって、降り掛かってきた相続問題について、自分ごとととらえ、その理解を深め、良い経験をすることができるでしょう。この経験は、将来に起こる次の家族が亡くなった際の相続においても活かすことができます。
相続登記のために、何度も役所や法務局に足を運んで必要書類を準備しなければならないですが、その時間がとれるなら良い経験ともいえます。
相続に必要な戸籍の集め方について

自分で相続登記するデメリット
一方で、相続登記を自分でやることには、デメリットが多くあります。
手続きが複雑である
相続登記の手続きは非常に複雑で、多くの書類の準備が必要となります。そして、ミスなく進めるためには、正確な手続きの理解が必要です。
このような相続登記を自分で行う場合、書類の準備や提出も、全て自分でしなければならず、誰も代わりにはしてくれません。誤りがあったり、手続きが遅れたりすると、最悪の場合は登記が受理されないこともあります。法律に定められた手続きなので、そのルールは厳格です。
法的なリスクがある
自分で相続登記を行う場合、法律知識が不足していると、法的なリスクを負う可能性があります。
例えば、遺産分割協議書に不備があると、登記ができず、遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまいます。その頃には、相続人の気持ちが代わり、全員の同意がとれなくなってしまう可能性があります。その結果、争続に発展してまとまらず、トラブルが継続してしまいます。これらのリスクを避けるには、法律に関する正確な知識と経験が必要です。
なお、細かなミスであれば、法務局などの窓口で訂正印によって対応できることもあるので、自分で相続登記するときには必ず印鑑を持参するようにしましょう。
相続登記を自分でやるときの注意点
最後に、相続登記を自分でやるときの注意点について解説します。
自分でできる限界を見極める
理論的には相続登記は自分でできるのですが、現実としてできるかどうかは、その相続登記の大変さや、担当する相続人の能力、経験によります。そのため、難しい事例ではやはり、司法書士に依頼するのが賢明です。自分でできる限界を見極めるべきです。
司法書士に任せるべき難しいケースは、次の通りです。
- 相続人が多数いる場合
相続人の数が増えると、相続登記時に必要となる書類が増加し、不備が生じやすくなります。また、相続人の確定や、法定相続分の計算に苦慮するおそれがあります。 - 相続した不動産を売却予定の場合
取得した不動産の売却予定があるとき、決済時までに相続登記を終了する必要があり、少しでも遅れるリスクが大きくなってしまいます。 - 相続税申告に影響する場合
相続税の申告は、相続開始を知った時から10ヶ月以内に行う必要があり、納税資金の確保のために不動産を処分する場合は、相続登記の遅れが相続税の申告・納付に影響してしまいます。 - 相続人間の争いがあった場合
争続となり協議が長期化し、調停や審判に発展したケースでは、その後の相続登記について失敗すると、再度同じ分割方法で相続人全員の合意がとれるとは限りません。
法律知識を理解する
相続登記を自分で成功させることのできる方とは、法律知識がしっかりと理解でき、用意周到に計画し、じっくり進める時間的な余裕のある方です。少なくとも、法律の基礎知識を習得する必要があるため、下記の解説などを参考にされてください。そして、自分で進める際には公的機関の窓口で相談しながら進めるのがお勧めです。
限定的にでも専門家のサポートを受ける
自分で相続登記をしようと考えている人には、費用面など様々な理由があることでしょう。どうしても自分でやらざるを得ないケースもあるでしょうが、このとき、全て任せるのでなくても、限定的にでも専門家に任せる方が、うまく相続登記を進める助けになります。
例えば、次のような解決策を検討してください。
- 法務局の窓口で相談する
- 司法書士による無料相談で疑問を解消する
- 資料の収集は自分でし、その後の手続きを司法書士に任せる
相続登記を全て自分で行うのにはリスクもあるので、少しでもアドバイスを受けるのがお勧めです。司法書士のアドバイスは、適切なタイミングで受ければ効果が高くなります。
相続に強い司法書士の選び方について
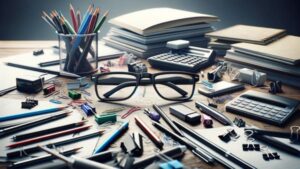
まとめ
今回は、相続登記を自分でできるかどうかについて解説しました。結論として、相続登記は相続人がするのが原則であり、理屈としては自分でできるのが当然です。
しかし、相続登記には多大な労力と、詳しい法律知識を必要とします。やり直しが発生すればかえって長引いてしまいます。これらを事前に理解し、適切な準備をしてミスなく進めるのは、自分自身では難しい方が多く、この場合には事実上自分ではできないとういことになり、専門家のサポートを求めるのが賢明です。
司法書士に相続登記を任せるのは、法律知識に基づく誤りのない登記をする助けとなるメリットがあります。できるだけ安く費用を抑えるポイントは、専門性をもった良い司法書士を選ぶことです。