相続放棄は、予期せぬ負債、複雑な相続トラブルを避けるための法的な選択肢の一つです。相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つがありますが、相続放棄は、遺産を一切承継しない点で、最も重大な決断といってよいでしょう。
それゆえに、法的にも厳格な要件が定められており、デメリットやリスクもあります。特に、相続放棄の期限について、相続開始を知った時から3ヶ月以内にする必要のある点は重要なポイントです。
今回は、相続放棄の基本的な意味から始め、その手続きの全ステップと注意点について詳細に解説します。相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述によって始まりますが、必要書類や準備など注意すべき点が多くあります。相続放棄すべきかどうか、よく理解して、適切な判断をする手助けとしてください。
相続放棄の基礎知識
初めに、相続放棄に関する基本的な法律知識について解説していきます。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)からの相続を一切しないことを選択する手続きです。相続を拒否する意思表示を示すプロセスといってもよいでしょう。このとき、相続人は、故人の相続財産だけでなく、借金その他の負債も引き継ぐことなく、相続権を全て失います。
この手続きは、家庭裁判所に申し立てを行うことによって開始されます。
なお、相続の方法は単純承認、限定承認、相続放棄の3種類あり、他のものも簡単に解説します。
- 単純承認は、被相続人の権利義務を全て承継する、相続の最も原則的なルールです。
- 限定承認は、遺産額を限度としてのみ負債を引き継ぐ方法です。遺産から支払い切れなかった負債は返済を免除されます。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄には、メリットとデメリットがあり、それらを総合的に比較して「相続放棄をすべきかどうか」は状況に応じて検討する必要があります。
相続放棄のメリット
- 負債を回避できる
故人が残した借金やローンその他の負債を引き継がずに済みます。 - 法的紛争を防げる
マイナスの財産を引き継がなくて済むことで、その押し付けあいなどの遺産分割の争いを防ぐことができます。 - 手続きを簡略化できる
相続人がたくさんいると遺産分割が複雑になりもめがちですが、一部ないし全部が放棄して相続人でなくなれば、手続きは簡易に進められます。
相続放棄のデメリット
- 相続財産も放棄される
遺産のなかにある価値ある資産についても承継せず放棄することになります。 - やり直しができない
一度相続放棄をすると、取り消したり撤回したりはできません。 - 共同相続人に悪影響がある
相続放棄すべきケースとは、相続すると不利になってしまう場面でしょう。1人の相続人が放棄すると他の相続人の承継する割合が増加し、放棄が共同相続人の負担を増やすことに繋がります。
相続放棄の法的な効力
相続放棄をすると、その相続人は法律上、故人の財産に対する権利を初めから持っていなかったこととなります。
負債を引き継がないことを目的として放棄するのが通例ですが、その場合、不動産や預貯金、株式など、あらゆる財産も相続によって取得することはできなくなります。また、初めから相続人ではなかったことになるため、相続放棄した人に子や孫がいても代襲相続も生じません。
相続放棄は相続が開始したことを知った時から3か月以内に行う必要があり(熟慮期間)、この期限を逃すと自動的に、相続を承認したとみなされてしまいます。したがって、相続放棄は慎重に検討する必要があるものの、期限があることを意識し、スピーディに必要な手続きを完了させなければなりません。
相続放棄の手続きの進め方
次に、相続放棄の手続きの進め方について、順に解説していきます。
手続き開始前の準備
相続放棄を検討する際、まずは故人の財産と負債の全体像を把握するのが重要です。銀行口座や不動産を確認し、不動産や株式については財産評価を要します。その上で相続財産目録を作成して整理し、相続する価値ある財産が上回るのか、それとも負債の方が多いのかを調べると、相続放棄の正しい判断が下せます。
戸籍や謄本など、相当な通数を要することもありますが、相続放棄には、3ヶ月の期限があるので、時間管理にも注意を払って準備を進める必要があります。
相続に必要な戸籍の集め方について

相続放棄申述の方法
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
この書類には、被相続人と相続人の情報、相続放棄する理由などを記載し、必要な証拠書類とともに提出します。この際、戸籍謄本や除籍謄本などを集めておかなければなりません。
家庭裁判所における手続き
申述書を提出した後、家庭裁判所は出された書類を審査し、必要に応じて追加の書類提出を求めることがあります。全ての書類が揃うと、裁判所が受理します。
相続放棄の受理とその後の流れ
裁判所が相続放棄を受理すると、相続人は法的に相続権を失います。
受理された証拠としての相続放棄申述受理証明書が交付され、これによって相続放棄のプロセスが終了します。相続放棄をした後は、必要に応じて、その事実を関係する金融機関などに通知してください。これによって、故人の借金などを請求されることがなくなり、督促を止めることができます。
相続放棄は複雑な手続きが伴うため、不明点がある場合は専門家の助言を求めるのが有益です。法的な影響が大きく、失敗すると大変なので、慎重に考えてください。
相続放棄後の督促への対応について
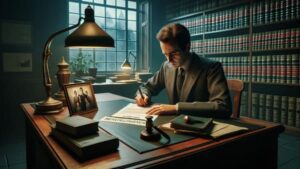
相続放棄に必要な書類とその準備
次に、相続放棄に必要な書類と、それを準備する方法について解説します。
必要書類の一覧
相続放棄の手続きには以下の書類が必要です
- 相続放棄の申述書
相続の放棄の申述書(裁判所)の書式をダウンロードして記入します。 - 戸籍謄本、除籍謄本など
被相続人と相続人との関係を証明するために必要となります - 死亡証明書
被相続人が死亡して相続が開始されたことを証明する書類です。 - 相続関係説明図
相続人として誰がいるかをわかりやすく整理するのに必要です。 - 相続人の本人確認書類
運転免許証やパスポートなどの公的な身分証によって提出者の身元を証明します。
書類作成のポイント
提出書類は、法的な書類なので、正確かつ慎重に記載しなければなりません。作成時のポイントは、次の通りです。
まず、全ての書類は、正確で間違いのない情報を記載します。誤字や脱字などには細心の注意を払い、丁寧に記載しましょう。この際、書式については自分で一から作るのではなく、行政の提供するひな形を利用します。綺麗な文字で、はっきりと書くようにしてください。
提出期限と書類の保存
相続放棄は、故人の死亡を知った日から3か月以内に申述する必要があり、過ぎると単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります。
裁判所に提出した書類は、念のため全てコピーして保存しましょう。将来に問題が生じたときに、相続放棄を申述していたと説明しなければならない場面に備えてのことです。郵送で提出する場合には、書留や配達記録などの記録に残る形で行ってください。
相続放棄の注意点とは
相続放棄には、注意点が多くあります。そのなかでも、期限を過ぎてしまわないよう気をつけるのが最大のポイントです。相続放棄を考える際は、以下の点に特に注意を払って進めてください。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に行う必要があります。この期限を逃すと、相続放棄の権利は失われ、負債を相続することになってしまいます。
共同相続人の影響
相続は個々の相続人ごとに行われます。あなたが相続を放棄したとき、その分の相続は、共同相続人に移ります。その結果、あなたが相続したくなかった負債を、今度は共同相続人が承継することになります。
この問題を避けたいなら、共同相続人にも通知をして、皆が相続放棄できるよう有効的に進めるのが賢明な方法です。
相続放棄後の財産管理
相続放棄をした後は、放棄した財産の管理について原則として関与できなくなります。しかし、相続放棄が受理されるまでの間、財産があるときには放置しておくことはできず、管理はきちんとしなければなりません。
相続放棄の具体的な事例と解説
ここでは、相続放棄の具体的な事例を紹介し、そのケースから学ぶべきポイントを解説します。相続放棄を検討する際には、基礎知識だけでなく、実際にあった事例を参考にすることが有益です。
故人Aは事業を営んでいましたが、業績が悪化して個人でも負債を抱え、多額の借金がありました。その額が遺産の総額を上回っているのは明らかでした。
相続人Bは、事業の後継者となる気持ちもなかったため、相続放棄を選択しました。
このケースでは、相続人Bが故人Aの負債を引き継ぐリスクを回避するために相続放棄を選んだのは良い決断です。事業を営み、それがうまくいっていない場合、負債のある可能性は高いと考えて調査すべきです。
故人Cの遺産には不動産が含まれていたが、共同相続人間での遺産分割協議は困難を極めていました。
不動産はそれなりの価値になりそうでしたが、生活に余裕ある相続人Dは、複雑な対立のストレスを避けるため相続放棄を選択しました。
このケースから分かるように、相続放棄は遺産分割の対立や争いを避ける手段としても利用されます。この場合、全ての相続人にとって相続するのが損なわけではないので、放棄するかどうはか人によって判断が分かれます。
相続人Eは初め、故人Fの遺産が少ないと考えて相続放棄をしました。しかし、後に価値のある財産が見つかりましたが、相続放棄は取り消せませんでした。
この事例では、相続放棄の決定が不可逆であり、取り返しのつかないことを学ぶことができます。そして、放棄をする前に遺産の全体像を把握しておくことの重要性を理解してください。
相続放棄を考えたときのチェックリスト
次に、相続放棄を決める際に、その判断の根拠を簡単に知るためのチェックリストをお示ししておきます。相続放棄しようかと考えはじめたら、これらのチェックポイントを参考に、適切な判断をしてください。
【故人の財産と負債の調査】
- 相続財産の額を把握しているか
- 預貯金、不動産、株式など漏れなく把握しているか
- 故人の負債の額を把握しているか
- 負債が相続財産を超えているか
【相続人の範囲】
【相続放棄の期限の確認】
- 相続開始日(死亡日)はいつか
- 自分が相続開始を知ったのはいつか
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内か
- 期限を過ぎたことにやむを得ない理由があるか
【相続放棄による長期的な影響の検討】
- 放棄後の自身の財産計画
- 自分の家族の関係性への影響があるか
- 親族の信頼に影響しないか
- 共同相続人とのコミュニケーションは十分か
【専門家のアドバイス】
- 弁護士に法的なアドバイスを受けたか
- 税理士に税務面の計画を立ててもらったか
- 法的な観点から、相続放棄が最善の方法か
- 戸籍などの必要書類に漏れはないか
- 記載した書類に不備がないか
相続に強い弁護士の選び方について

相続放棄後のその後はどうなる?
相続放棄をすると、その後はどうなるか、理解しましょう。相続放棄前に、もし手続きをしたらどうなるかといった不安を払拭することができます。相続放棄後の財産状況の変化と、今後の生活についても解説します。
相続放棄後の財産状況の変化
相続放棄をすると、故人の負債は承継しなくなります。全相続人が放棄すれば、借金の返済が免除されたのと同じような効果を持つことになります。相続放棄を行う主な理由の一つは、故人の負債を引き継がないためなので、この変化が最も重要です。
ただし、負債だけでなく、故人が残した資産も放棄することになります。これに対し、相続人自身の財産には、全く変化はありません。
法定相続人の変更
これらの財産状況の変更だけでなく、相続放棄をすると、相続権が他の相続人に渡ります。最初から、自分がいなかったものとして法定相続人の範囲を考えるのがよいです。その結果、本来であれば相続しないだろうと想定していた人が、相続人となることがあります。
そのような人に予想外の負債を負わせないためにも、あなたが放棄することによって相続人になる次順位の人には通知しておくのがお勧めです。
今後の財産計画について
相続放棄によって、放棄した人の財産には変化はないものの、本来なら財産を相続できると思っていたものがもらえなかったことにより将来の計画が狂う可能性もあります。このようなとき、家族とも相談して、将来の財産計画を練り直す必要があります。
家庭によっては、貯蓄や投資を切り崩したり、新たな投資や贅沢をあきらめなければならないこともあります。老後の資金計画や子供の教育資金に無理が出てしまっては大変です。このような変化が、家庭に亀裂を生まないためにも、相続放棄をすることもありうると想定して、家族と日常的に密なコミュニケーションをとるべきです。
相続放棄についてよくある質問
最後に、相続放棄について、よく寄せられる質問に回答していきます。相続放棄は難しい法的な手続きなので、多くの疑問が生じるでしょう。しっかりと解消して、ミスのないように進めてください。
相続放棄を撤回や取消しすることはできる?
原則として相続放棄は撤回できません(民法919条1項)が、民法総則の規定の適用により例外的に、要件を満たすと取り消すことができます(民法919条2項)。ただしあくまで例外で、簡単に認められるわけではないので、後から欲しい遺産があったことが判明したといった事態にならぬよう相続財産調査を徹底し、慎重に決定する必要があります。
相続放棄の撤回について

相続放棄後に新たな遺産が発見されたらどうなる?
相続放棄をした後に財産が見つかったとしても、放棄した相続人はその財産を受け取ることはできません。後悔しないよう、放棄前に徹底的に財産調査をしておきましょう。
遺産の一部だけ相続放棄できる?
遺産の一部のみ相続放棄することはできません。相続放棄は全て相続するか、一切相続しないかの二者択一のみとなります。
まとめ
今回は、相続放棄の基礎知識と、他の方法との違い、メリットやデメリットなど、注意点を解説しました。相続放棄は、全て相続しなくなる点で単純に見えますが、実際にはリスクやデメリットもあり、慎重に進める必要があります。
特に、財産調査が不十分なままに、相続放棄をする、しないといった判断をすると、誤って損な相続を選択してしまう危険があります。後戻りのできない手続きなのでやり直しは効きません。負債の大きさや資産の種類、家族構成などによっても判断が異なるので、心配なときは事前に弁護士にご相談ください。


