遺産のなかに不動産が含まれる場合、その評価額が高く、占める割合が多いことはよくあります。一方で、不動産は、預貯金などと比べて所有していない家庭もあるため、亡くなった方(被相続人)が土地や建物を持っているのかわからないことが多く、調査して探さなければなりません。
今回は、被相続人の重要な財産の1つである不動産について、亡くなった後の調査方法と、探す時の注意点を解説します。
相続不動産の調査が必要となる理由
不動産を相続していたとしても、発見できなければ自分のものにはなりません。不動産の金額は、他の遺産に比べて高額となることが多いため、調査せず放置しては影響が甚大です。
相続税の申告ミスが起こる
相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税を払う必要があります。しかし、相続した不動産を見逃していると、本来ならかかるはずの税金を放置するおそれがあります。相続税は、相続人が調査して計算し、納付しなければなりません。税務署がミスを指摘するのは後日であり、その際には次のような追加の費用がかかってしまいます。
- 延滞税
相続税の納付が遅れた場合 - 過少申告加算税
誤って少なく相続税を申告した場合 - 無申告加算税
期限までに相続税の申告を行わなかった場合 - 重加算税
財産を隠したり証拠を偽装したりなど悪質な行為があった場合
悪質な行為を行った場合に課される重加算税は、追加納付すべき税金に対して更に35〜40%も課されるとても重い負担です。相続した不動産を過失によって見逃すリスクはもちろん、故意に隠すのはもってのほかです。
意外な不動産が見つかる
不動産の相続というと真っ先に思いつくのは自宅不動産でしょう。自宅が亡くなった方(被相続人)名義であるとき、その相続を見逃す方はあまりいません。しかし、自宅以外にも、思ってもいないところに不動産が見つかることがあるため、調査方法を知る必要があります。
- 先祖代々相続されてきたが、相続登記を怠っていた田舎の土地
- 所有しているが、他人に貸したまま長期間が経過したマンション
- 駐車場、倉庫などに利用したまま放置していた土地
- 愛人用に購入したまま放置していた別荘地
調査の結果、被相続人よりも前の世代の名義のまま放置されていることが判明するケースもあります。

相続における不動産の調査方法
不動産を調査する必要性を理解したところで、早速、相続における不動産の調査方法について解説します。
預貯金を手がかりに調査する
相続財産で特に金額が大きくなりやすいのが不動産ですから、その手がかりはしっかりと探せば見つかることがほとんどです。まずは、誰しもが遺産として持っているであろう預貯金の調査からはじめ、その履歴を手がかりにしましょう。
不動産を有していることは、次のような預貯金の動きに表れるので、過去の通帳を細かくチェックしていきます。
- 住宅ローンの貸付、返済履歴がある
- 賃料の入金が記録されている
- 固定資産税の支払いが記録されている
以上の場合には、口座のある銀行などの持つ情報から、法務局や市区町村役場に照会し、被相続人所有の不動産の詳細を判明させることができます。通帳は、亡くなった方のあらゆるお金の流れを知れる重要な資料なので、真っ先に調査してください。
預貯金の調査について
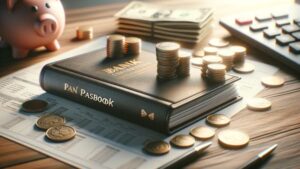
郵便物を手がかりに調査する
被相続人宛てに届く郵便物を調査すれば、有力な手がかりを得られます。ポストをのぞくだけではなく、遺品整理をし、そのなかに封筒やはがきなどがないかチェックしてください。例えば、次の資料は、不動産を所有していたことを強く推認させます。
- 固定資産税通知書
毎年5月頃、不動産の所有者に宛てて、市区町村役場・都税事務所から届きます。固定資産税評価証明書が手元にある場合にも同様です。これらの書類には不動産の所在地など、特定できる情報が記載されているので、この情報をもとに登記簿を取得できます。 - ローン返済の明細書
銀行など金融機関から届きます。 - 運用履歴の明細書
信託銀行・証券会社から届きます。
なお、不動産が共有名義のときは注意が必要です。共有名義の不動産の固定資産税は「連帯納税」となっており、所有権割合によらず共有者全員が連帯して払う義務があり、納税通知書が代表者1名にしか送付されません。
法務局で登記簿謄本を取得する
固定資産税関連の書類などを発見したら、そこに記載された不動産の情報をもとに、法務局で登記簿謄本を取得し、所有者を確認してください。登記簿謄本はデータ化されており、オンラインでも申請できます。
登記簿謄本は、「表題部」「甲区」「乙区」に分かれており、甲区の部分に所有者が記載されます。なお、遺産に債務が含まれる場合には相続放棄が適している場合もありますが、借金があるかどうかは、登記簿謄本に抵当権の記載があるかどうかによっても知ることができます。
権利証を探す
不動産の所有権を示すのが、権利証です。権利証は、所有権を取得し、登記した際に発行され、再発行はされません。現在は登記識別情報がその代わりになっていますが、従来からあった権利証が保管されていればそれも有効です。
権利証や登記識別情報は、登記を任せた司法書士が預かっているケースもあるので、故人とつながりのある司法書士に連絡することで遺産が判明することもあります。
名寄帳を取得する
遺産のなかに不動産が存在するかを調査するのに、名寄帳を取得する方法があります。名寄帳は、市区町村役場の管轄している課税対象となる不動産が全て記載されています。不動産には、固定資産税は課されていても登記がされていないものもあります。そのため、登記を調べるだけでなく、名寄帳の取得が必要となるのです。
名寄帳は、管轄内の不動産の一覧です。未発見の不動産がないと言い切れないのであれば、念のため名寄帳を調査しておいたほうがよいでしょう。名寄帳は相続人であれば請求できるので、必要な戸籍を収集し、役所の窓口で申請してください。
なお、名寄帳を用いても、非課税の不動産は発見できません(例えば「私道」など)。このようなケースは、隣接する不動産と一体活用されている場合が多く、現地調査が必要となります。
遺言書の記載から探す
遺産分割をする際には、遺言が重要な役割を果たします。遺言が存在する場合には、遺産分割協議を経ずして、まずは遺言に従って分けるのが原則となるからです。不動産の相続登記をするにも、必要書類を大幅に省略できます。
相続人の全く知らなかった不動産が、遺言に書かれていたことで発見できる場合があります。遺言に記載されている不動産は、全て登記簿謄本を取得し、所有者を確認する必要があります。
相続財産調査について

まとめ
今回は、遺産のなかでも特に価値が高く、大きな割合を占めることの多い不動産について、その存在を調査する方法と、探し方の注意点を解説しました。
調査した結果をもとに、登記や固定資産税を調べて評価額を明らかにし、公平な分割や相続税深刻に活かす必要があります。不動産の調査は非常に手間がかかり、相続人自身で実行するのは難しいため、弁護士など相続の専門家に依頼するのが有益です。


