相続が発生し、葬儀費用や当面の生活費を工面するのに利用できるのが「預貯金の仮払い制度」です。預貯金の仮払い制度を利用すれば、遺産分割協議がまとまる前でも、被相続人(亡くなられた方)の銀行預金から所定の金額を引き出すことができます。
被相続人に扶養されていた方の生活費を用意したり、被相続人の借金を返済したりするとき、預貯金の仮払い制度の利用をご検討ください。
本解説では、預貯金の仮払い制度の内容や具体的な手続きの方法について詳しく解説します。
預貯金の仮払い制度とは?概要を解説
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議がまとまらない場合でも、被相続人の預貯金を引き出せる制度です。まずは、基本的な遺産分割のルールから確認します。
- 遺言書がある場合
遺言書の内容通りに遺産を承継する(相続人全員の反対がない限り) - 遺言書がない場合
相続人全員が遺産分割協議を行ったうえで遺産を分ける
遺言書の内容に相続人全員が反対している場合と、相続人が遺言書を残していない場合には、相続人が相続財産を取得するのには遺産分割協議を行わなければなりません。
そして、相続が発生すると、不正出金を防ぐために被相続人名義の口座は凍結されます。そのため、被相続人名義の口座から出金や振込を行うには、有効な遺言書か遺産分割協議書が必要となるのが原則です。つまり、遺産分割協議がまとまらないと、いつまで経っても被相続人の口座からお金を引き出すことができません。
このことによる不都合を解消するのが、預貯金の仮払い制度です。この制度を活用すれば、条件を満たす限りにおいて、例外的に相続人が被相続人の預金を一定額まで引き出すことが許されます。ます。家族が死亡すると、葬儀費用など様々な費用がかかります。相続発生後に現金が必要な状況に迫られた場合は、預貯金の仮払い制度の利用を検討するとよいでしょう。
相続した預貯金の手続きの流れについて

預貯金の仮払い制度が始まった理由
次に、預貯金の仮払い制度が始まった理由について解説します。
遺産分割協議が長期化し、被相続人の預貯金を引き出せないと、被相続人に扶養されていた配偶者や子は生活ができなくなってしまう可能性があります。また、葬儀費用を支払うためにお金を用意しなければならない場面も考えられるでしょう。
遺族の経済的な不安を解決し、安心して生活できるようにするために、預貯金の仮払い制度が設けられました。仮払いの請求は、各相続人が金融機関に対して行えます。
平成28年の判例変更
最高裁平成28年12月19日判決は、預貯金は遺産分割の対象財産になるため、各相続人による単独の引き出しはできないと判示しました。この判例は、それ以前は、預貯金は遺産分割の対象とはならないとしていた最高裁平成16年4月20日判決を判例変更したものです。
相続人による単独の引き出しを制限する理由は、預貯金の不正利用を防ぐためです。相続人が勝手に預貯金を引き出して、不当に遺産を受け取る事態を防ぐために、相続人といえども「単独で」の引き出しはできないルールとなったのです。ただ、家族の死後にはどうしても緊急で金銭を要する事態も想定されるため、すぐに引き出せないのでは相続人の生活が困窮するリスクもあります。このような背景から2018年相続法改正で導入されたのが、預貯金の仮払い制度です。
相続法改正前の預貯金の扱いの問題点
相続法の改正が行われる前のルールでは、相続人がお金を必要としている場合でも、有効な遺言書か遺産分割協議書がなければ被相続人の預貯金を降ろすことができませんでした。生前にあらかじめ準備をしていなければ遺言を残していない人も少なくなく、そして、遺産分割協議は相続人の利害が対立すると相当長期化することもあります。
相続人が、自身の資金で当面の生活費や葬儀費用を工面できれば生活を維持できますが、被相続人に扶養されていた場合には、お金に困ってしまうおそれがあります。葬儀費用や家賃が支払えなくなり、葬儀社や家主とのトラブルになる事態が問題視されていました。
預貯金の仮払いは、相続をきっかけにして相続人の生活に悪影響を及ぼす問題点を解消するために設けられました。遺産分割がまとまる前でも、被相続人の口座から一定額の引き出しを認めることで相続人の生活の保護を図っています。
相続財産となる預貯金の調査について
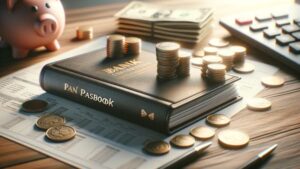
預貯金の仮払い制度の要件と手続きの流れ
預貯金の仮払い制度は、家庭裁判所が判断する場合と、家庭裁判所の関与のない場合の2つに分かれます。それぞれ、どのような流れで進んでいくかを解説します。
家庭裁判所が判断する仮払い制度
遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所に対して遺産分割の審判や調停が申し立てている場合、仮払いを受けるには家庭裁判所の判断を経なければなりません。仮払い制度を利用したい相続人が各自家庭裁判所へ申立て、裁判所の審判を得ることで金融機関から単独で払戻しを受けられます。
仮払いを受けるには、生活状況を鑑みて裁判所より「相続預金の仮払いを行う必要性がある」「他の共同相続人の利益を害しない」と認められる必要があります。なお、裁判所が許可する限りにおいて、払い戻しを受けられる額の上限は特に決められていません。
家庭裁判所の判断を経ない仮払い制度
家庭裁判所の判断を経ない仮払い制度もあります。この場合、相続人が各自で、被相続人が口座を保有していた金融機関に仮払いの請求を行います。被相続人の口座残高を調査するには、金融機関で「預貯金照会」や「残高証明書の発行」の手続きを行います。なお、被相続人がどこの金融機関で口座を有しているか、通帳や郵便物、スマホアプリなどをもとに調査が必要です。
家庭裁判所の判断を経ずに直接金融機関へ申請できる方法なので、手続きの流れが簡易的で審判に関する費用がかかりません。ただし、家庭裁判所が判断するケースとは異なり、引き出せる金額に限度が設けられています(次章「預貯金の仮払い制度によって出金できる金額の上限」参照)。
なお、仮払いの請求は各金融機関に対して行えます。つまり、複数の金融機関から仮払いを受けられます。ただし、同じ金融機関の異なる支店で口座を開設している場合は、支店ごとに請求できず一つの金融機関として取り扱う点に注意しましょう。
預貯金の仮払い制度によって出金できる金額の上限
前章で解説の通り、家庭裁判所の判断を経ない仮払い制度には金額の上限が設けられています。以下では、家庭裁判所の関与しない仮払い制度によって出勤できる金額の上限や、具体的な計算方法について事例を紹介しながら解説していきます。
出金できる金額の上限
家庭裁判所の判断を経ない預貯金の仮払い制度によって出金できる金額は、以下のいずれか小さい金額を上限とします。
- 死亡時点での預貯金残高 × 法定相続分(相続人の取り分) × 3分の1
- 金150万円
上限が設定されており、被相続人の預貯金を全て引き出せるわけではない点に留意しましょう。
計算の具体例
具体的な事例で、預貯金の仮払い制度によっていくら出金できるか計算します。例えば、次の事例をもとにシミュレーションをします。
【被相続人の預貯金】
- A銀行:1,500万円
- B銀行:300万円
【法定相続人の構成】
- 配偶者と子2人
この場合、法定相続分については配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。これらの条件を踏まえて、各相続人が仮払い制度によって出金できる金額を次のように計算できます。
【A銀行から出金できる金額】
妻:1,500万円×2分の1×3分の1=250万円 →150万円
子:1,500万円×4分の1×3分の1=125万円
妻の場合は、法定相続分の3分の1が、150万円よりも多くなるため、出金できる上限額は150万円となります。一方で、子は150万円よりも少ないため、出金できる上限額は125万円となります。
【B銀行から出金できる金額】
妻:300万円×2分の1×3分の1=50万円
子:300万円×4分の1×3分の1=25万円
いずれも150万円より少ないため、妻が出金できる上限額は50万円、子は25万円となります。
妻が出金できる金額はA銀行とB銀行を合わせて200万円、子が出金できる金額はA銀行とB銀行を合わせて150万円です。
預貯金の仮払い制度を利用する際の流れ
預貯金の仮払い制度の手続きの流れ
預貯金の仮払い制度を利用する際の流れは、以下のとおりです。
【家庭裁判所が判断する場合(遺産分割の審判や調停が申し立てられている状態)】
- 相続人が単独で家庭裁判所へ払い戻しの申し立てを行う
- 家庭裁判所から審判を得る
- 家庭裁判所から審判書の謄本を得る
- 金融機関に対して「審判書の謄本」と「相続人本人の印鑑証明書」を提出する
- 実際に払い戻しを受ける
【家庭裁判所が判断しない場合(金融機関に直接申請する場合)】
- 相続人が単独で金融機関へ「被相続人の除籍謄本」「戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)」「相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書」「相続人本人の印鑑証明書」を提出する
- 実際に払い戻しを受ける
預貯金仮払い制度の必要書類の一覧
預貯金の仮払い制度を利用するにあたって用意すべき必要書類は次の通りです。
【家庭裁判所が判断する場合(遺産分割の審判や調停が申し立てられている状態)】
- 家庭裁判所から得た審判書の謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
- 相続人本人の印鑑証明書
【家庭裁判所が判断しない場合(金融機関に直接申請する場合)】
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人本人の印鑑証明書
家庭裁判所の判断する仮払いについては、家庭裁判所の審判を経て、確定していることを要するので、審判書が必要書類となります。また、金融機関に払い戻しの申請をする際に、審判書のほかに預金の払戻しを希望する相続人本人の印鑑証明書が必要です。
家庭裁判所の関与なく直接金融機関に申請する方法では、被相続人との関係を証明する書類や相続人全員の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書を用意しなければなりません。
ただし、金融機関によって必要書類が異なる場合があります。スムーズに手続きを進めるためにも、あらかじめ金融機関に問い合わせておくと安心です。
相続に必要な戸籍の集め方について

仮払いされた額は遺産分割で調整される
預貯金の仮払い制度によって払い戻された金額は、後日に行われる遺産分割において払戻しを受けた相続人が取得する遺産として調整が図られます。
例えば、100万円の仮払いを受けた相続人が300万円を相続する形で遺産分割協議がまとまった場合、仮払いを受けた100万円を差し引くため協議後に受け取ることのできる金額は200万円となります。100万円の仮払いを受けた後に50万円を相続する遺産分割協議がまとまった場合、他の相続人に対して50万円を支払う必要があります。
遺産分割の基本について

預貯金の仮払い制度を利用する際の注意点
最後に、預貯金の仮払い制度を利用する際の、よくある疑問と注意点を解説します。
仮払いを受けた金額では足りないときは?
預貯金の仮払いの金額だけでは生活費をはじめとした費用の支払いが不足するケースも想定されます。仮払いのみでは葬儀費用や生活費を工面できない場合、家庭裁判所で「仮処分」の手続きを行いましょう。状況を総合的に判断して、裁判所に仮処分を認めてもらえば、「法定相続分まで」の仮払いを受けられます。
仮処分の流れは、次の流れで進みます。
- 裁判所に保全命令の申立てを行い、必要書類を提出する
- 債権者の裁判官面接(数回にわたる場合がある)
- 担保決定
- 立担保証明提出
- 家庭裁判所より保全命令が発令される
仮処分を認めてもらうには、権利保全の必要性を裁判所に説明する必要があり、法律に詳しくない方にはハードルの高い手続きです。そのため、仮処分の手続きを検討する場合は相続問題に強い弁護士への相談をお勧めします。
相続に強い弁護士の選び方について

仮払いを受けると相続放棄できなくなる?
預貯金の仮払い制度を利用すると単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。単純承認をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続するため、被相続人に借金があると、相続人にとって負担となります。
単純承認にあたるかは、具体的な事情を勘案して判断します。例えば、仮払いを受けた全額を葬儀費用に充てた場合は単純承認とみなされませんが、生活費として費消すると単純承認となります。
相続放棄の手続きについて

預貯金以外の金融商品は仮払いの対象になる?
預貯金以外の金融商品(投資信託の受益権や個人向け国債)に関しては、預貯金の仮払い制度の対象ではありません。貸金庫契約についても、相続開始に伴って契約上の地位が相続人全員に継承されるため、仮払い制度の対象外です。
なお、満期を迎える前の定期預金のような約款で払戻制限がある金融商品は、金融機関から仮払いを拒否される可能性があるため注意しましょう。
金融機関から仮払いされるまでにどれくらいかかる?
仮払い制度の申請を行ってから実際に金融機関から仮払いされるまで、おおむね1週間から2週間程度の期間がかかります。金融機関によって異なるため、支出の必要性があるときには事前に相談しておくとよいでしょう。
預貯金の払戻しについての遺言執行者の権限は?
遺言執行者は、相続人に代わって遺言の内容通りに遺産分割を行う人で、相続財産の管理や遺言の執行に必要な行為をする権利義務を有します。
遺言執行者は、預貯金の払戻しをする権限を有しており、請求や預貯金に係る契約の解約を申し入れができます。
以前は遺言書に遺言執行者の預金払戻権限が明記されていない場合、金融機関ごとに対応が異なっていました。しかし、相続法が改正されてからは遺言書に遺言執行者の預金払戻権限が明記されていなくても、遺言執行者が預貯金の払戻しを行えるようになりました。
遺言執行者の役割と選任方法について

まとめ
相続人の生活を守るうえで、預貯金の仮払い制度は大切な役割を果たします。被相続人が遺言書を残さず、遺産分割協議が長引いてしまったときは、預貯金の仮払い制度の活用を検討しましょう。
預貯金の仮払い制度の存在を知っていれば、もし遺産分割協議が長期化して相続人が経済的に困った状況に陥っても冷静に対処できます。「生活費が不足している」「家賃が払えないかもしれない」という状況を回避するのに有用な制度といえるでしょう。
家庭裁判所を預貯金の仮払い制度を行う場合は、煩雑な手続きを要するため相続に強い弁護士と相談するのがお勧めです。


