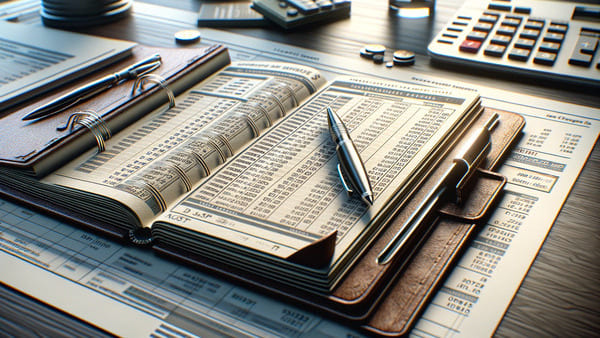相続財産には様々な種類がありますが、多くの人が有しておりわかりやすいのが預貯金です。そして、預貯金はとても重要な資産ですが、被相続人が死亡すると口座は凍結されます。
凍結は、使い込みや悪用を防ぐ目的があるものの、そのために相続開始後に凍結を解除し、口座の名義変更をしたり、払戻ししたりするのに、必要書類を準備して手続きしなければなりません。このプロセスは、単に遺産となる預貯金を守るのみでなく、納税資金を確保したり、争いない遺産分割の準備をしたりといった副次的な効果もあり、適切な承継において大切な手続きです。
金融機関の手続きがわかりづらく必要書類が数多くあるとき、窓口の対応に困難が伴うこともあります。今回は、相続した預貯金の名義変更について、手続きの流れをステップで解説します。
預貯金の相続の基本
相続が発生すると、被相続人名義の金融機関の口座は凍結されてしまいます。
遺産となる預貯金を手元に保持するには、払戻しの手続きをするか、被相続人の所有していた口座の名義を変更する必要が生じます。納税資金としても想定している場合、相続税の支払い期限(相続開始があったことを知った時から10カ月以内)に名義変更の手続きを終える必要があります。
相続開始時に口座が凍結される理由
そもそも、相続開始時になぜ口座が凍結されるのでしょうか。その理由は、相続人間の争いの防止にあります。
相続が発生すると、被相続人名義の口座は「相続人全員の共有」となります。そのため、特定の相続人が勝手に引き出さないよう、金融機関でも制限をかける必要があるのです。
むやみに請求に応じれば二重払いや、実は相続人でなかった人に払ってしまう危険があるため、金融機関が相続争いに巻き込まれないよう、このような対応が浸透しています。
「自分の相続分だけでも早く現金化したい」という気持ちは理解できますが、金融機関としてもそれには応じてくれず、遺言があるか、遺産分割協議が成立するか、いずれかの時点まで凍結され、名義変更はできません。
少なくとも、相続の開始から遺産分割協議までは約1カ月はかかります。争続となり長期化する場合、調停や審判に発展してもっと長くかかることもあります。したがって、近い将来の死亡が予想される場合には、凍結による弊害を回避するために、葬儀費用や実家の片づけ費用などは、事前に引き出しておくか、そうでなければ相続人が建て替えて払う方法が現実的です。
預貯金の相続は名義変更と払戻しの2種類
銀行口座の相続には2つの種類があります。
- 名義変更
亡くなった方(被相続人)が保有していた口座の名義を変更して引き継ぐ - 払戻し
口座を解約して預貯金の払い戻しを受ける
一般には、上記2つの手続きを総じて「名義変更」と呼びます。金融機関によっては預金は特定の本人に紐づくものだと考え、払戻しのみ受け付ける銀行もあります(特に、預貯金以外の有価証券や信託権などは、相続に際しては解約のみしか受け付けない対応も少なくありません)。具体的な手続きは、利用していた金融機関に直接問い合わせるのが賢明です。
なお、2018年の相続法改正で、凍結のデメリットを解決すべく、預金の仮払い制度が新設され、利用が拡大しています。詳しくは「預金の仮払い制度の活用を検討する」参照。
口座の名義変更をする手続きの流れ
相続における銀行口座の名義変更手続きの流れをまとめます。
相続財産に預貯金が全く存在しない方は少ないでしょう。近い将来に家族の死亡が予想される場合には、相続開始後速やかに名義変更の手続きを進められるよう、早めに準備しておきましょう。
口座を調査する
まず故人の所有していた口座を調査します。銀行に問い合わせるのは手早いですが、死亡の事実を伝えると口座は凍結されますので注意しましょう。
どの金融機関かもわからない場合、次の探し方も参考にしてください。
- 遺言のなかの記載を手がかりにする
- 貸金庫の中を探す
- 遺品整理時に通帳、キャッシュカードや証書を探す
- 利用明細に新たな口座がないかたどる
銀行口座がわかれば、前述の仮払い制度によって当面のお金の心配は無くせます。そのうえで金融機関に対し、名義変更の手続きをする準備をします。その場の判断で動くのではなく、本解説を参考に、どのような手順で手続きすればリスクが最小限になるか、長期的な視野を持って検討するのがポイントです。
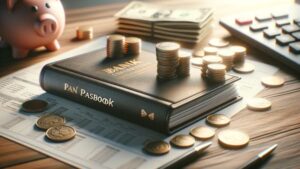
必要書類を収集する
名義変更の申請には様々な書類が必要です。遺言がある場合とない場合、相続人が1人の場合と複数の場合によって異なるため、ケース別に解説します。
【遺言がある場合】
遺言がある場合には、その指定が優先されるため、遺言書によって預金を相続すると記載された人は、単独で名義変更の手続きできます。必要書類は一般に、次のものです。
【相続人が1人の場合】
相続人が1名の場合には、その人が預金を含めた全遺産を相続するのが明らかであり、単独で名義変更をすることができます。必要書類は一般に、次のものです。
- 相続届(銀行ごとの所定の書類)
- 被相続人の戸籍謄本
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図) - 口座を引き継ぐ相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
【相続人が複数の場合】
相続人が複数で、遺言もないとき、遺産分割協議を経て相続人全員の同意がなければ、預金を分配できません。そのため名義変更時は、相続人全員の同意を示すため、遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
- 相続届(銀行ごとの所定の書類)
- 被相続人の戸籍謄本
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図) - 相続人の全員の戸籍謄本、印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- (協議が不成立の場合)調停調書または審判書の謄本
相続に必要な戸籍の収集について

預金の仮払い制度の活用を検討する
2018年の相続法改正にて、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(いわゆる預金の仮払い)がスタート。この制度は、相続の開始から遺産分割の完了までに、故人の医療費や葬儀費用、相続人の当面の生活費など、すぐにでも必要な支払いに困らぬように設けられたものです。
預貯金の仮払い相続の開始から遺産分割完了までのあいだ、故人の医療費や葬儀費用の支払い、相続人の当面の生活費など、預金の引き出しがすぐに必要な支払いも多いです。この制度を使えば、名義変更を待たずして、次の金額を仮に引き出すことができます。
- 家庭裁判所の審判を得た場合
家庭裁判所が仮取得を認めた金額 - 家庭裁判所の判断を経ない場合
相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
(ただし、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限)
仮払い制度の利用の必要書類は、一般に次通りですが、金融機関によって追加資料を求められる場合もあります。
- 申請者が法定相続人であることが確認できる書類
- 法定相続人全員が確認できる書類
(一般的には戸籍謄本か法定相続情報一覧図) - 申請者の身分証明書、印鑑証明書
- 金融機関所定の申請書
ただし、仮払い制度にはデメリットもあり、この制度によっていずれ受け取る相続分を先に受け取ることを意味するため、引き出したお金を自分のために使うと、相続を単純承認したこととなり、その後に相続放棄することができなくなってしまいます(葬儀費用など故人のために使う分には単純承認とはならないので、使途を示す領収書などを残しておきましょう)。
預貯金の仮払い制度について

遺産の分け方を決める
前述の通り、遺言がある場合にはその指定に従って分けるので、指定された相続人は単独で名義変更できますが、そうでないとき、相続人が複数いるなら、名義変更の前に、遺産の分け方を決める必要があります。
遺産の分け方を決める、遺産分割のプロセスは、まずは協議から始まり、決裂するときは調停、審判へと進みます。協議がまとまるときに作成する遺産分割協議書も、相続人全員の合意が必要となり、完成しなければ口座の名義変更はできません。
遺産分割の基本について

銀行に名義変更を申請する
必要書類が揃った時点で銀行に名義変更を申請します。
目安として申請後、2週間から1カ月程度で手続きが完了します。名義変更であれば変更後の通帳を受け取り、解約であれば相続人が指定した銀行口座に払い戻し金が振り込まれ、手続きが完了します
なお、解約済みとなった被相続人の通帳は郵送で返却されます。
預貯金の分け方について

ゆうちょ銀行の特殊性に注意する
ゆうちょ銀行は書類の提出と、名義変更の方法が一般の銀行とは異なるので注意を要します。ゆうちょ銀行における相続手続きの流れは、次の通りです。
- 相続の申し出
- 照会書の提出
口座があるかどうかの確認に必要となる。口座があると判明している場合は不要。 - 相続確認表の記入と提出
亡くなった人や相続人の氏名、遺言書の有無、貯金の書類、口座の記号番号などを提出。窓口役になる代表相続人を決めて提出します。 - 必要書類の準備
戸籍謄本、印鑑証明書など - 貯金等相続手続請求書の提出
一般の銀行の手続きよりも煩雑で手続きの回数も多い印象です。名義変更にかかる時間も多くなる傾向がありますが、ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方向は多いですから、相続発生後すぐに動き出すようにしましょう。
手続きの結果、名義変更の有無および入金は代表相続人がゆうちょ銀行の口座を開設しているか否かによって変わります
- 代表相続人がゆうちょ銀行口座を持っている場合
→代表相続人の口座に入金される。 - 亡くなった人の口座を引き継ぐ場合
→名義書き換え済みの通帳を受け取る。 - 代表相続人がゆうりょ銀行口座を持っていない
→→払戻証書を受け取り、現金化する。
口座の名義変更をするときの注意点
次に、口座の名義変更をするときの注意点を解説します。
遺産の使い込みに注意する
相続前後の遺産の使い込みに注意しましょう。預金の仮払いによって引き出された金額を自身のために使用した場合、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。また、生前の使い込みも、遺産分割の際に「他の相続人の許可なく使った」と指摘されるリスクがあります。
これらのことは相続人間のトラブルの原因となり、遺産分割がまとまらなくなる原因です。相続の前後に出金すること自体がリスクとなることを認識しておきましょう。


引き落とし先を変更しておく
名義変更まで、少なくとも約1カ月は要するなか、賃料やローンの支払いなど、重要度の高い出費は、引き落とし先を変更しておくのがお勧めです。預金が凍結されても支払いは先延ばしにはなりません。相続人の負担にならぬよう、生前から、引き落とし先を変更するのが相続リスクの軽減策です。
相続税申告に配慮する
預貯金は、原則として相続開始日時点の残高で評価され、相続税の課税対象となります。
相続時の証明には、金融機関の発行する残高証明書を用います。定期預金など利息が多額の場合は特に、しっかり計算したものを参照しましょう。外貨については日本円に換算し、相続開始日時点のTTB(電信買い相場)により評価します。
名義変更と同時並行で対策しなければならないのが、相続税の納付です。相続税は相続の開始を知った時から10カ月以内に、最寄りの金融機関もしくは税務署に納付する必要があるので、早めに税理士に依頼し、動き出すようにしましょう。また専門家に依頼することによって、節税対策や相続トラブルの回避も期待することができます。
被相続人が実際に亡くなってしまってからでは出来ない対策もあるため、早めに依頼したい専門家を見つけ、コンタクトすることが一連の作業をスムーズに進めるポイントです。
口座の名義変更についてよくある質問とその回答
最後に、口座の名義変更に関するよくある質問について回答します。
口座の名義変更に期限はある?
口座の名義変更に期限はありません。ただ、相続発生から10か月後には相続税の期限があり、原則は現金納付のため、口座が凍結していると支払う資金が確保できないおそれがありますから、この時点までには名義変更を終わらせた方がよいです。
口座の名義変更にかかる期間は?
金融機関によりますが、必要書類をすべて提出してから2週間から1カ月程度としているところが多いです。この期間はあくまで目安なので、早めに手続きを開始することで次のステップに向けて迅速に動けるようにしていきましょう。
口座の名義変更をせずに放置するリスクは?
口座の名義変更をせず、被相続人名義のまま放置してもなくなるわけではありません。実際にかなりの預貯金が名義変更されず、手つかずのまま休眠口座となっています。とはいえ、遺産を活用できない点は大きな損失だといえます。
まとめ
今回は、相続の開始にともなって預貯金が凍結された場合に、凍結を解除して口座の名義変更をするための手続きと注意点を解説しました。
亡くなった方の口座を速やかに名義変更し、預貯金を利用するには、円満に遺産分割を終える必要があります。また、突然に家族が死亡してしまったとき、資金に困らないよう、生前対策をしっかり行っておくようにしましょう。