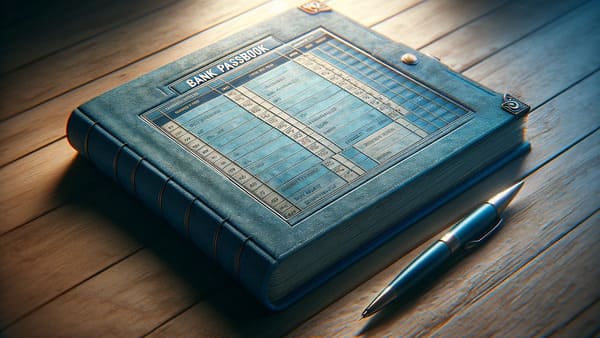生前に行われる多額の預金引き出しが、相続トラブルの火種となることは少なくありません。特に、亡くなる直前に大金が引き出されていて、その後に死亡してしまうと、それが不正な引き出しだったのかどうか、本人に確認することはできなくなってしまい、家族間の争いの原因になります。
生前に大きな資金の移動があると、それが果たして本当に故人の真意だったのか、解釈に争いが生じてしまいます。金銭の問題は、家族の信頼関係や絆にも影響します。平穏だった家族に亀裂が入ることのないよう、生前の預金引き出しのリスクを知り、多額の引き出しはトラブルのもとだと肝に銘じておく必要があります。
今回は、生前の預金引き出しによって紛争の起こったケースと、その対処法を解説します。
生前の預金引き出しによる法律問題
生前に、自身の預金を引き出すのはその人の自由です。家族の口座から大金が引き出されていたとしても、その人の意思によるなら全く問題ありません。
日常取引の範囲でも予想外に大金を要することがあります。金融機関も、不正出金やマネーロンダリング対策で、大きな出金時は身分を確認し、引き出し目的を聞くなどのプロセスを踏みます。高齢者や認知症の方だと親族に確認する場合もあります。そのため、通常は法律問題は起こりません。
それでもなお相続で問題となるのは、生前の大きな資金の引き出しが、完全にその人の意思だとは言い切れないケースがあるからです。生前とはいえ、死の直前の場合は特に、そのタイミングになって大きな出金があると遺産が減少してしまうので、相続人にとっても大きな関心事となり、その使途や行き先に対する疑念は深まります。
なお、死亡後の預貯金の問題は、下記を参照ください。
死亡後の預金引き出しについて

生前の預金引き出しがトラブルの原因となるケース
家族の死後に、生前における預金の引き出しが判明し、それについて相続人間の意見や利害が異なるとトラブルが激化します。そのため、生前の預金引き出しは、相続の場面においてよくトラブルの原因となります。
次に、生前の預金引き出しがトラブルの原因となるケースを、具体例で解説します。
生前に引き出して被相続人のために費消した場合
生前に引き出された預金が、被相続人のために費消された例を考えてください。例えば、家族が預金通帳を預かり、そこから引き出したお金で生活費を出したり、介護費用を引き落としたりしていたケースです。この場合、生前に引き出された預金のメリットを受けるのは、その預金の名義人自身であり、家族が利を得ているわけではありません。
身体の不自由や高齢など、自分では預金を下ろせない理由のあるとき、家族に委託することはよくあります。このとき、将来の相続トラブルを避けるには、次のような証拠を準備するのが大切です。
- 預金の引き出しに関する依頼書
- 引き出した預金の使途を示す資料
(通帳、入出金明細、家計簿、領収書など)
生前に無断で引き出して自分のために費消した場合
これに対して、生前の家族の預金を無断で引き出して、自分のために使ってしまった場合には、問題は更に深刻です。権限なく預金を引き出せば、たとえ家族といえど、不当利得であり、不法行為が成立する可能性があるからです。これによって、引き出された預金の名義人は、勝手に引き出した人に不当利得返還請求ができるほか、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
そして、口座の名義人からの2つの請求権はいずれも、相続によって承継されます。その結果、相続開始後に、生前の無断での引き出し行為を発見したら、その人に対して、返還を請求することができます。
生前の被相続人の許可を得て費消した場合
生前に、被相続人の許可を得てその預金を引き出し、費消した場合には、生前贈与されたものとして扱うことができ、返還の必要はありません。
このとき、それによって生じた不公平は、その生前贈与が、特別な利益といえる場合は、特別受益として遺産分割のプロセスで考慮されます。また、その生前贈与が遺留分を侵害している場合には、侵害された相続人は、それによって得をした人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
この遺留分の計算において、算定基礎に含まれる生前贈与は、相続開始前1年以内のものに限られますが、特別受益に該当する贈与は10年以内に行われた全てが算定の基礎に含まれます(2018年の相続法改正前は期間を問わず、特別受益に当たる場合には全ての贈与が含まれる)。
遺留分の基本について

生前に許可を得たが、目的外に費消した場合
最後に、生前に許可を得たものの、その目的外に費消してしまった場合には、やはり無断で使った場合と同じく、不当利得や不法行為による請求の対象となり、金銭を返還する必要があります。この場合は、預金引き出しの許可を得ていたとしても、それはあくまで目的の範囲内に限られるもので、その範囲を超える場合には、無権限で引き出したのと同じだからです。
生前の預金引き出しによるトラブルを回避する対策
相続において、生前の預金の引き出しがトラブルに発展することを理解し、これを回避するための対策をよく講じておく必要があります。このことは、引き出しを防止したい相続人の立場ではもちろんのこと、生前に預金を引き出して、使い込みを疑われないためにも大切です。
生前の引き出しを検討する側の対策
高齢の親から預金口座の管理を任されるなど、生前の引き出しを検討せざるを得ない立場にいる人もいます。このとき、生前の預金引き出しがトラブルになりやすいことを理解し、対策を講じる必要があります。対策なく自分のものであるかのように預金を使い、後から疑われたり、責任追及をされたりするのは心外でしょう。
その対策では、次の重要なポイントを押さえてください。
- 透明性の確保
生前に預金を引き出すときは、その目的と使途を明確に記録しておいてください。可能な限り、相続人となり得る他の家族にも伝えて理解を得るなど、透明性の確保が重要です。 - 正式な文書の作成
資金の移動には、法的な文書を必ず作成しておきましょう。最悪の事態を避けるには、家族だからといって曖昧にしてはならず、出金依頼書や贈与契約書などの準備が必要です。 - 専門家との相談
大きな金額を移動するときには、法的に問題ないかどうかを知るため、弁護士のアドバイスも欠かせません。
相続を見据えた計画を立てる
生前に預金を引き出すときには、将来の相続まで見据えた計画を立てることが重要です。お金を使い込んだのではないかという疑いをかけられるのは、残った遺産の額に不満があることが原因となっている場合が多いです。
とはいえ、現在必要となる生活費や、老後の資金についても用意しなければならず、その一方で、遺産として残す額も必要となるのですから、引き出すにしても、計画性をもって進めなければなりません。
まとめ
今回は、生前に、被相続人の預貯金が引き出されていたときに、その後の相続においてどのようなトラブルが起こるか、またその際の対処法といったことについて解説しました。
使途の明らかでない預貯金の引き出しは、生前であっても、相続において大きな問題となります。生前の引き出しは、被相続人の意思に沿っている可能性もあるので、引き出した人がその点を主張して反論してくる可能性があるため、よく吟味しなければなりません。