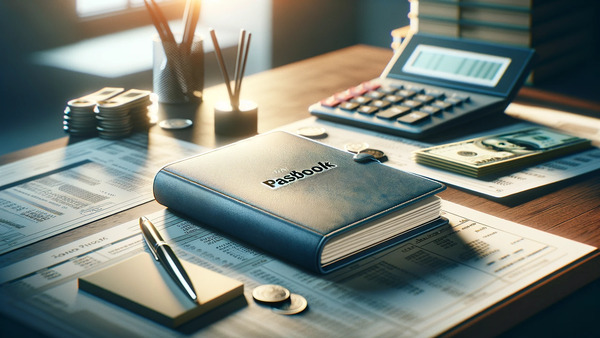亡くなった方(被相続人)の遺産のなかに、預貯金がある場合には、それも相続財産となります。銀行やゆうちょ、証券口座など、抜け漏れのないよう調べる必要があります。預金を相続しても勝手に引き出すことはできず、死亡時に一旦は凍結されます。遺産分割協議をして凍結を解除し、適切な割合に分割しなければなりません。
今回は、遺産分割における預貯金の分け方と、より良い分割方法のポイントについて解説します。
預貯金口座の凍結を解除するには
被相続人が亡くなると、相続が開始され、その時点で預貯金口座が一旦凍結されます。つまり、死亡時点で残っていた預金の残高は、すぐには引き出せなくなります。預貯金も相続財産になるため、相続人の一部が勝手に引き出せると、抜け駆けが生まれてしまうおそれがあるからです。
預貯金の分け方も決まらないうちに、勝手に引き出し、使ってしまう相続人がいると問題が悪化するため、銀行などの金融機関では、誤った相続人に払い戻して責任問題にならないよう、払い戻しを停止するのです。
凍結された口座を解除し、払い戻しを受けたり解約したりするには、遺産分割の手続きを経る必要があります。多くのケースでは、遺産分割協議書を持参して手続きを行いますが、対立の激しい家族では遺産分割調停や審判に発展することもあります。つまりは、どのような割合で相続されるかが決まった後でないと、預貯金を得ることはできないのです。
口座の名義変更について

預貯金口座の遺産分割協議の進め方
次に、遺産分割協議による預貯金の分け方について解説します。
預金という遺産の相続にあたって、まず必要となるのが遺産分割協議です。そして、話し合いが合意に達したら、相続人全員の押印した遺産分割協議書を作成し、銀行など口座のある金融機関に提出することで手続きが進みます。
預貯金は遺産分割の対象になる?
遺産分割協議で、話し合いによって合意できるならば、遺産の分割方法には制限がありません。これに対し、遺産分割調停や審判に発展したときには、裁判所による一定のルールがあります。
以前は、遺産分割協議で相続人が相続財産に含めると合意した場合以外は、預貯金は遺産分割の対象にはならないと考えられており、家庭裁判所の実務での同じ取扱いがされていました。これによると、預貯金は、相続が開始された時点で、自動的に分割され、法定相続分に応じて払い戻されることとなっていました。
その後、判例(最高裁平成28年12月19日決定)によって、預貯金も遺産分割の対象となるという判例変更がされました。その結果、現在では、預貯金をどう分けるかについて、協議したり家庭裁判所に判断してもらったりできるようになったのです。
遺産分割の基本について

適切な預貯金の分け方は?
預貯金の分け方に、制限はありません。つまり、遺産分割協議で、他の相続人が同意するならば、全ての預金を1人の相続人が承継する、という解決策をとることもできます。特に、分けづらい遺産(不動産や事業など)で高価なものがあるとき、分けやすい預貯金は、その調整として機能します。
「代償分割」といって、一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人に対して相続分に相当する金銭を払うという方法があります。このとき遺産に含まれる預貯金はまさに代償分割の資金源となります。
そのため、相続財産に多くの種類があるなかで、まずは預貯金以外の分けづらい財産の分割方法を議論した後に、相続人間に遺留分侵害などの不公平が生じてはじめて、預貯金を調整的に利用して分割する、という進め方をすれば、不公平を解消できます。
遺産分割協議がまとまった後の手続は?
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して、金融機関の手続きに進みます。遺産分割協議書には、相続人全員の押印をし、印鑑証明書、相続関係を証明する戸籍謄本などを添付します。必要書類は、事前に提出先の金融機関に確認しておきましょう。
また、金融機関側の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書には、以下の情報を正確に記載してください。
- 金融機関名
- 支店名
- 預貯金口座の種類(普通預金・当座預金)
- 口座番号
- 口座名義人
遺産分割協議書の作成方法について

相続される預貯金口座は、実際にどのように分けられる?
遺産分割の手続きが終わって、実際に預貯金を相続するときには、遺産分割が完了したことを銀行などに伝えることで、口座の凍結を解除し、払い戻しを受けることができます。
具体的には、金融機関に対し、実際に相続する人の口座などを伝え、そこに相続することが決まった金額の振込をしてもらいます。口座凍結の解除や払い戻し、解約の手続きは複雑口座凍結の解除や払い戻し、解約の具体的な手続き、必要書類は、早めに、事前に金融機関に確認しておいてください。
なお、協議のなかでは、特別受益や寄与分といった特殊な計算方法が争点となることが多く、金融機関としても、しっかりとトラブルが落ち着いていることが確認できないと、払い戻しを円滑に受けられません。
まとめ
今回は、遺産に預貯金を含む相続において、うまく分ける方法を解説しました。ほとんどの相続のケースで、預貯金は相続財産となっていますが、速やかに引き出したいと思っても意外と手間がかかり、お困りの方も多いことでしょう。
一般に、預貯金は分けやすい財産で、不公平の調整用として用いられますが、具体的なケースにおいてどのような分け方が適切かは、家族の関係や他の資産の状況によって、個別に検討しなければなりません。