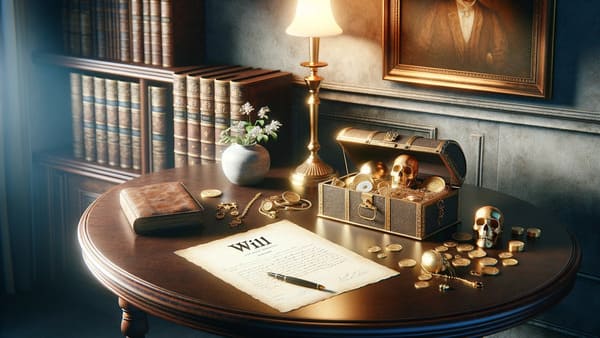遺言書を書いてみたものの、気が変わり撤回したいと思うこともあります。しかし、どのように遺言を撤回すれば良いのかご存知の方は多くないでしょう。間違った方法をとってしまうと撤回できず、希望通りの効果を実現できません。特に、自筆証書遺言の場合、専門家のサポートを受けない方も多いため、後に無効になるリスクを減らす配慮が必要です。
本解説では、遺言書を撤回する方法を注意点とともにわかりやすく解説します。また、遺言を変更したいときに、遺言書を撤回し、変更する手続きについても解説します。文例も紹介するので、遺言書の撤回を検討している方は、ぜひ本解説を読んで実践してみてください。
遺言書の撤回の基本
まず、遺言書の撤回に関する、基本的な法律知識について解説します。
遺言書の撤回とは
遺言書の撤回とは、遺言書の内容の一部または全部を無効にすることです。結論として、遺言書の撤回は、相続開始前(生前)ならばいつでも、遺言者の意思によって自由にすることができます。遺言書の撤回について定めた民法1022条は、次の通りです。
民法1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法(e-Gov法令検索)
以下のような理由で、遺言書の撤回を希望する方がいます。
- 遺産を残すはずだった家族と不仲になった
- 孫やひ孫が誕生して家族構成が変わった
- お世話になった親族や団体が出てきた
- 遺留分を侵害していたことが判明した
- 財産の内容に変更があった
例えば、全ての財産を長男に相続させる旨の遺言書を書いていたとしても、長男と不仲になり気が変わると、遺言書を撤回したくなるでしょう。このような場合、いつでも、遺言書を撤回して無効にすることが可能です。
遺言の撤回は、その一部または全部に対してすることができ、撤回された遺言については効力がなくなります。撤回後に新たに遺言をしなければ、その部分については遺言が遺されていないのと同じことになります。その結果、民法の法定相続分のルールに基づいて相続がなされます。
しかし一方で、撤回の注意点を知らず、方法を誤ると、意図した遺産相続は実現できません。撤回がうまくできていなかったり、撤回する部分の特定をミスしたり、撤回後に新たに作成した遺言が無効になったりといったリスクがあります。本解説では、撤回の方法と注意点も後述しますので、よくご確認ください。
遺言の一部を撤回することも可能
遺言は、全部ではなく一部を撤回することも可能です。
例えば、「不動産を配偶者に相続させ、預貯金は子に相続させる」といった遺言があったとしましょう。この遺言について、「預貯金を子に相続させる」部分だけを撤回して無効にすることができます。
また、新たな遺言書で「不動産を子に相続させる」と記載すると、抵触する「不動産を配偶者に相続させる」旨の遺言は撤回され、後に書いた遺言の「子に相続させる」が有効となります。
遺言書を撤回する方法と手続きの流れ
次に、遺言書を撤回する方法と手続きの流れについて解説します。
遺言書を撤回する方法は、先ほど紹介した民法1022条に「遺言の方式に従って」とある通り、遺言の方式で行うのが原則です。「遺言を撤回する」と口頭で発言するだけでは法的に撤回したことにはならないので注意してください。
「遺言の方式に従って」遺言書を撤回する方法には、次の4つの方法があります。
各方法の具体的な方法や流れ、注意点を解説していきますので、どの方法が自分に合っているかを検討してください。
「撤回する」という遺言を作成する
前の遺言書とは別に、新たに「遺言を撤回する」という遺言書(いわゆる「撤回遺言書」 )を作成する方法によって、遺言を撤回することができます。撤回遺言書の種類(方式)には制限はなく、例えば、前の遺言書が公正証書遺言であっても自筆証書遺言や秘密証書遺言によって撤回できます。
新たに撤回遺言書を作成する方法だと、遺言書が2つ以上になるため、相続人がどちらか一方だけしか発見できなかった場合に、遺言書の解釈を誤ってしまいます。このようなことのないよう複数の遺言書をまとめて保管し、家族に「遺言書は2つある」と伝えておくといった注意が必要です。
前の遺言の全部を撤回する遺言書の例
前の遺言の全部を撤回したい場合、「全部を撤回する」と明記します。文例は次の通りです。
遺言者は、本書により、令和XX年XX月XX日付の遺言の全部を撤回する。
令和XX年XX月XX日
住 所 東京都◯◯区……
氏 名 ◯◯◯◯ 印
なお、自筆証書遺言の場合には、全文と日付、氏名のすべてを自署し、押印するといった要件を満たさなければ、形式不備によって無効となる危険があるため、よく確認してください。
前の遺言の一部を撤回する遺言書の例
遺言の一部だけを撤回したいときは、以下のように撤回する部分を特定して記載します。
遺言者は、本書により、令和XX年XX月XX日付の遺言のうち「◯◯◯(第1の第1項)」の部分を撤回する。
令和XX年XX月XX日
住 所 東京都◯◯区……
氏 名 ◯◯◯◯ 印
どの遺言のうち、どの内容を撤回するのかについて、第三者が見ても明らかに理解できるよう特定して記載するのが重要なポイントです。
新たに内容の異なる遺言を残す
遺言書を撤回する方法には、前の遺言書とは内容の異なる新たな遺言書を残す方法もあります。前の遺言を、新しい遺言で「上書き」する方法だと認識すればわかりやすいでしょう。前の遺言書とは別に新たな遺言書で上書きする方法をとったとき、その2つの遺言の優先順位は、民法1023条の定めるように「抵触する部分については……撤回したものとみなす」ことになります。
いずれにせよ新しい遺言書を作成することになりますが、「撤回する」と書くのか、それとも新たな内容を記載するのかは、遺産相続を民法の定めるルールに任せたいかどうかで決めるとよいでしょう。民法に従う場合には「撤回する」と記載するだけで足りますが、撤回して新たに自分で決めたいなら、新しい遺言に遺産の分配方法について改めて記載した遺言書を作成してください。

保管していた遺言書を破棄する
民法1024条の通り、遺言者が故意に遺言書を破棄したときも、破棄した部分の遺言は撤回されたものとみなします。また、遺言の内容が「遺贈」(遺言による贈与)」だと、遺贈の目的物を破棄したときにも遺言が撤回されたものとみなします。
民法1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
民法(e-Gov法令検索)
遺言書を捨てるだけで撤回できるので、方法としては簡単です。ただし、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており破棄はできません。
法務局保管の制度を利用した自筆証書遺言は、返還を受けるために、遺言者本人が撤回書と顔写真付き身分証明書を持参して手続きをする必要があります(手数料などの費用は無料です)。また、返してもらっただけでは撤回はできず、破棄を忘れると有効な遺言が残ってしまうので注意してください。
物理的な破棄の方法で撤回する場合、必ず遺言の全部を破棄しましょう。数枚ある遺言書のの一部だけを破り捨てる方法は、法律関係に混乱を招くのでお勧めできません。
また、遺言が撤回されるのは「遺言者が故意に」破棄したときなので、次のような疑問が生じると、相続トラブルに繋がります。
- 破棄ではなく紛失してしまっただけなのではないか
- 遺言者ではなく他の家族が破棄したのではないか
したがって、遺言書を物理的に破棄する方法で遺言を撤回するときは、その後に撤回遺言書や新たな内容の遺言書を作成することを強くお勧めします。
公正証書遺言は公証役場でも撤回できる
公正証書遺言は自筆証書遺言で撤回することもできますが、公証役場で新たに前の遺言を撤回する旨の公正証書遺言(撤回公正証書遺言)を作成してもらうことで撤回が可能です。もちろん、前の公正証書遺言を撤回するだけでなく、上書きする形で新たな公正証書遺言を作成することもできます。また、前の遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言でも、公正証書遺言で撤回・修正・変更ができます。
なお、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、自分で破棄して撤回することはできません。
公正証書遺言について

自筆証書遺言は原本の変更でも実質的に撤回できる
自筆証書遺言の場合は、撤回遺言書の作成ではなく、以下のように遺言書の変更によって対応することもできます。これによって「遺言書を変更したい」という希望を叶えることができるのです。
- 撤回(削除)する部分に二重線を引く
- 撤回(削除)した箇所の付近に、遺言書に使用した印鑑で押印する(文字は見えるようにする)
- 遺言書の欄外や末尾に、「何行目の◯◯を削除した。相続太郎」のように変更した旨を記載して署名する
自筆証書遺言を法務局に保管する制度を利用している場合、遺言書の原本は法務局にあるので、原本を修正(変更)したいときは遺言書の返還を受けなければなりません。遺言書の返還を受けるには、遺言者本人が遺言書を預けた法務局に撤回書と顔写真付き身分証明書を持参して手続きをする必要があります(手数料などの費用は無料です)。
なお、自筆証書遺言の修正は、手書きで行う必要がありますが、例外的に、2018年相続法改正によって相続財産目録は手書きでなくてもよくなったため、目録に限り、手書き以外での修正、変更も許されます。
自筆証書遺言について

遺言を撤回する際の注意点
遺言を撤回する際は、以下の点に注意しておきましょう。
遺言の撤回の撤回(再度の撤回)はできない
民法1025条の定めにより、原則として遺言の撤回行為を撤回することはできません。つまり、遺言の撤回の撤回(再度の撤回)はできず、前の遺言が復活することはありません。
民法1025条(撤回された遺言の効力)
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
民法(e-Gov法令検索)
わかりやすくまとめると、撤回した遺言は、原則としてもう有効にはならない(復活しない)ということです。したがって、「遺言を撤回したけど、最初の遺言のとおりにしたい」ときは、新たに遺言を作成する必要があります。
錯誤・詐欺・強迫で撤回したときは例外的に復活する
錯誤(重要な勘違い)や詐欺(騙された)、強迫(脅された)によって遺言を撤回した場合には、例外として撤回した遺言をもう一度有効にできる(復活できる)可能性があります。錯誤については民法95条、詐欺、強迫については民法96条で取消しが可能だからです。
しかし、あくまでも例外であるため、再度の撤回遺言書で「騙されたため、令和◯年◯月◯日付撤回する旨の遺言書を撤回する」と記載しても復活が認められるかどうかは不安定です。法的に不安定な状況となる撤回の撤回(再度の撤回)をするよりは、新たに遺言書を作り直すのが安全です。
最高裁は復活に柔軟な立場を示している
また、最高裁は、撤回の撤回があった場合でも、遺言書の記載から遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは復活を認めています(最高裁平成9年11月13日判決)。
一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。
二 遺言者が、甲遺言を乙遺言をもって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する。
最高裁平成9年11月13日判決
民法1025条を必ずしも文言通りに適用するのではなく、遺言者の真意を尊重するといった法律の目的を重視し、柔軟に解釈・適用する立場を示したといえるでしょう。しかし、錯誤・詐欺・強迫と同様、新たに遺言書を作成する方法のほうがやはり確実です。
新しい遺言書が無効になるリスクを回避する
遺言を撤回するために作成する新たな遺言書(撤回遺言書)が無効であれば、「撤回したつもりだったのに撤回できていなかった」という可能性もあり、注意を要します。民法967条の通り、遺言書には法律に定める方式があり、それぞれ要件を満たさなければ無効になってしまいます。
新たに遺言を作成するときには、遺言の種類ごとのメリット、デメリットについて以下の解説を参考によく理解してください。また、撤回遺言書が無効になるリスクを回避するには、弁護士など専門家のサポートを受けることも有益です。
遺言書の基本について

法務局保管の遺言は破棄できない
法務局に保管してもらっている自筆証書遺言は手元に原本がなく破棄できないため、新たに撤回遺言書を作成する方法を検討しましょう。法務局から遺言書を返してもらって破棄する方法もありますが、遺言書本人が預けた法務局に出向く必要があるため、遠方の場合は手間がかかってしまいます。
なお、公正証書遺言も、原本が公証役場に保管されているので同じく破棄ができません。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも良いので、新たに撤回遺言書を作成しましょう。
遺言の撤回に関するよくある質問
最後に、本解説の内容を踏まえ、遺言の撤回についてのよくある質問に回答しておきます。
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できる?
撤回できます。確かに、公証人や証人の関与する公正証書遺言を、比較的容易に作成できる自筆証書遺言で撤回できることに違和感を覚える方もいます。法務省に設置された審議会の部会にて公正証書遺言の撤回は公正証書遺言に限ろうとする動きもありました。
しかし、方式が同じかどうかより、遺言者の真意の確証がとれることを重視する反対意見もあり、撤回遺言書の種類は制限されないままとなりました。遺言の種類を限定すると、迅速に遺言者の最終意思を反映できないケースも出てくるため、自筆証書遺言にも簡易さというメリットがあるのです。
撤回した遺言書の保管方法はどうすべき?
全部撤回したならば、前の遺言書は破棄して構いません。一部撤回の場合には、前の遺言書と撤回遺言書のどちらとも保管しておく必要があります。
自筆証書遺言は自身で保管する方法もありますが、2018年相続法改正で新設された法務局保管の制度を利用するのが安全です。公正証書遺言の場合は公証役場で保管します。
なぜ手元の公正証書遺言を破棄しても撤回できないの?
手元にあるのは公正証書遺言の写し(正本または謄本)であり、原本は公証役場にあるからです。
遺言者の手元にある正本の破棄が、遺言の撤回に当たると解釈する説もありますが、必ずしも裁判で同じ結論になるとは限らず、公正証書遺言を撤回したいときには、物理的な破棄以外の方法がお勧めです。
遺言を撤回ではなく修正したいときはどうする?
前の遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、以下の方法で修正できます。
- 撤回(削除)する部分に二重線を引く。
- 撤回(削除)した箇所の付近に、遺言書に使用した印鑑で押印する(文字は見えるようにする)。
- 遺言書の欄外や末尾に、「何行目の◯◯を削除した。相続太郎」のように変更した旨を記載して署名する。
まとめ
今回は、遺言書を撤回する方法と、その後に遺言を変更する手続きについて解説しました。
遺言書を撤回するには、新たに撤回遺言書(撤回する旨の遺言書)を作成するほか、遺言書を破棄したり、前の遺言書とは異なる内容の遺言書を新たに作成したりする方法があります。複数の方法についてはメリット、デメリットや注意点を理解し、状況に応じて使い分ける必要があります。
また、新たに遺言書を作成するときは、押印を忘れるなどといった形式不備によって無効にならないように注意しましょう。もし「自分の場合にどの方法で撤回すべきかわからない」「有効な遺言書が作成できたか不安だ」といった方は、弁護士に相談するのがお勧めです。