親が離婚している場合でも、子どもは相続人になります。直系尊属(自分より上の世代の直通する系統の親族)から見て、血を分けた子ならば法定相続人に該当するからです。このことは両親が離婚した後も変わることはなく、両親のどちらが親権者になっても関係ありません。
つまり、子である限り、父親、母親それぞれの相続人になるのが基本です。
本解説は、親が離婚した後の相続の考え方と、実際に相続が発生したときやるべきことを紹介します。両親が離婚すると、親権者でない親とは疎遠になる方も珍しくありません。その親が更に新たな家庭を作っていると、親の死後に、再婚した妻やその子から連絡がきて、相続トラブルに発展することもあります。
親が離婚しても子供は相続人になる
親が離婚した場合でも、子には法定相続権があります。法定相続権は、民法の定める法定相続人の有する、被相続人の遺産を承継する法律上の権利のことです。
民法887条1項に「被相続人の子は、相続人となる」という文言があるため、子の相続権は法律で認められています。したがって、戸籍上で親子関係があり続ける限り、子は父親、母親双方の法定相続人として、遺産を相続する権利を有するのであり、両親の離婚には影響されません。
両親が離婚しても相続権がある
法律上の原則として、両親が離婚をして、夫婦関係を解消したとしても、父親、母親それぞれと子との間の親子関係はなくなりません。したがって、両親の離婚後も、子の相続権は失われません。相続順位としては「子」は、必ず相続人となる「配偶者」に次ぐ、第一順位の相続人とされています。
また「子」の身分による相続人であれば、遺留分も有しています。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人の有する、相続できる最低限の割合のことであり、子の遺留分を侵害した遺産分割が行われた場合には、両親の離婚後であっても、遺留分侵害額請求によって救済されるのは当然です。
遺留分の基本について

親権がなくても相続権がある
両親が離婚すると、母親か父親のいずれかが子の親権者となります。子どもを保護するために、子の親権者を決めなければ、離婚届を役所に受領してもらうことができないからです。そして、離婚した両親のどちらが親権を取得したとしても、子の相続権には影響しません。例えば、母が親権を有し、母方で育てられたとしても、父方の相続について参加することができます。
親権とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限ないし義務のことをいいます。あくまでも親権は、子の利益を守るための権利であり、相続や遺産分割とは関係ありません。相続においては、親権の有無に関係なく子は両親の相続人となります。
なお、2024年5月17日に、離婚後の共同親権を可能とする改正民法が可決されました。改正民法が施行されると、離婚後も両親のそれぞれが親権を有する扱いも可能となります。
戸籍から抜かれても相続権は失わない
両親が離婚をすると、親権を有していない方の親が、自分の戸籍から子供の戸籍を抜くことがあります。しかし、戸籍から抜かれたとしてもなお、子は相続権を持ち続けます。
例えば、母親が親権者となり旧姓に戻るケースで、子を母親の戸籍に移すことが実務上よく行われます。この場合には子は父親の戸籍から抜けることになりますが、父の死亡時にも相続権を有します。
親の再婚相手と養子縁組しても相続権がある
両親が離婚した後に、親権を有する親が再婚するケースではどうなるでしょうか。
結論としては、親の再婚相手と普通養子縁組をした場合にも、子は、実の親の相続人であり続けます。つまり、実親の死亡時にも、養親が死亡したときにも、いずれの場面でも相続権を有することとなるのです(養子と実子の相続権は対等で、法定相続分も変わりません)。
なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、次の違いがあります。
- 普通養子縁組の場合
→実の親との親族関係が存続する - 特別養子縁組の場合
→養子縁組後は実の親との親族関係は終了する
特別養子縁組の場合、実親との親子関係が終了するため、その後は、実親の相続人ではなくなります。ただし特別養子縁組は、実親との関係悪化といった特別な事情のもと認められるもので、離婚した親が再婚する場合の養子縁組は、普通養子縁組とするのが一般的です。したがって、親の再婚者と養子縁組しても、相続権は有し続けるのが通例です。
養子縁組と相続への影響について

親の離婚と同時に離縁した養子は相続権を失う
ここまでの解説は、離婚した両親の実子についての説明です。これに対し、養子の場合には、親の離婚とともに離縁をすることが少なくありません。離縁をした養子は、養親との親子関係がなくなりますから、相続権も失うこととなります。なお、死後離縁の方法なら、相続開始後に養子縁組を解消することもできます。
死後離縁の方法と注意点について

子供が既に死亡していた場合は代襲相続が発生する
親が死亡したとき既に子が死亡している場合でも、子の子(つまり孫)がいる場合は代襲相続が発生します。代襲相続は、相続権が直系卑属(自分より下の世代の直通する系統の親族下の世代)に相続権が継承されることを指します。
代襲相続の仕組みにより、既に子が死亡している場合は孫が相続人になります。孫がまだ胎児の場合にも、相続においては胎児は出生しているものとみなすため、胎児にも代襲相続権があります。代襲相続権についても、子の代の離婚や親権の有無には全く影響されません。つまり、両親と子、いずれもが離婚していたとしても、親子関係が続く限り、孫に代襲相続権が生じます。
このように、自身の両親が死亡している場合には、代襲相続によって思わぬタイミングで相続権を得る可能性がある点に留意しておいてください。
代襲相続の基本について

離婚した親が死亡したら連絡は来る?
離婚した親の相続人になるとして、もはや疎遠になっている場合などには、どのようにして相続の開始(死亡)を知るかが問題となります。つまり「離婚した親が死亡したら、連絡が来るのだろうか」という疑問について解説していきます。
連絡が来るパターンと適切な対応方法
結論として、両親が離婚していたとしても、離婚した親が死亡したときには子どもには一定の連絡が来ることが多いです。相続人であることによって、遺産分割への参加などといった手続きに関与することが求められるからです。
以下では、他の相続人や、被相続人の債権者など、連絡が来るパターンと、それぞれの場面でどのように対応すべきかを解説します。
他の相続人からの連絡(遺産分割協議の依頼など)
他の相続人から、相続手続きの開始を通知する旨の連絡が来ることが多いです。遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して行う必要があるため、しっかりと相続人の調査をしている家庭ならば、必ず連絡が来ます。離婚後に親が再婚していると、再婚相手やその子など、全く面識のない人から突然連絡が来るケースもあります。
お悔やみの言葉を伝えると共に、遺産分割の話し合いをする日程を調整してください。縁のない人と連絡を取るのはストレスでしょうが、「親の相続」という重要な課題に真剣に向き合う必要があります。
また、離婚前に子が存在していたと分かると、他の相続人にとっては得られる遺産が減るため、敵意を向けられる(少なくとも好意を持たない)ケースも多いもの。「できれば相続させたくない」と思われ、相続放棄や遺留分の放棄を求められる可能性もあります。遺産分割がもめそうなとき、相続に精通した弁護士のアドバイスを求め、代理人として交渉を依頼するのも一つの手段です。

被相続人の債権者からの連絡(借金の督促など)
被相続人(亡くなった親)に借金がある場合、債権者から返済を求める連絡が来る場合があります。相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継するため、金融機関や消費者金融などから連絡が来る可能性は大いに考えられます。
もし債権者からの連絡が来ても、すぐ返済に応じる必要はありません。相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があり、財産に比べて借金が多い場合には、相続放棄をするのがおすすめです。相続放棄をすれば、債権者からの督促に応じる必要はありません。いずれの選択をするにせよ、まずはすべての遺産を把握するために相続財産調査をするのが第一歩となります。
相続放棄後の督促状への対応について
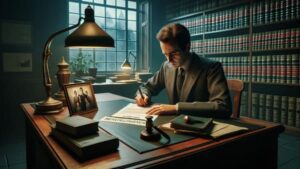
役所など行政機関からの連絡
役所などの行政機関から連絡が来る可能性もあります。例えば、一人暮らしをしていた親が死亡したとき、遺品や遺骨の引き取りを家族に依頼してくるケースです。死亡届の提出や国民健康保険証、要介護認定証の返還を求める旨の連絡がくることもあります。離婚した親が遠方に住んでいて対応が難しい場合は、相続の専門家に手続きを依頼することもできます。
税務署から相続税の申告に関するお知らせが届くこともあります。税務署は、市区町村から送られた死亡届のデータを基に、相続税が発生する可能性がある人に「相続税についてのお知らせ」を送付します。遺産が相続税の基礎控除を越えるときは、相続税の申告・納付を要します。判断に迷う場合には、税理士のサポートを受けるのがお勧めです。
警察からの連絡
親の死について不審な点があるときや事件性が疑われるときは、警察から連絡が来ることがあります。また、亡くなった人の身元確認を行う関係で、警察から協力依頼が来るケースもあります。警察から連絡があった場合、捜査に協力する姿勢を示すのが基本です。両親の離婚後ほとんど会っておらず状況がまったくわからない場合は、その旨を伝えれば問題ありません。
連絡が来ない場合とその対策
離婚した親の法定相続人となる子に対しては、遺産分割に関する連絡が来るのが通常であると解説しました。とはいえ、以下のケースでは、連絡が来ない可能性があります。
- 相続人の調査が不十分で、離婚前の子の存在を把握しきれていない
- 音信不通のため連絡先を知らなかった
- 離婚後に連絡をとっておらず住所が不明になっていた
- 感情的な対立から相続させたくないと思われている
- 疎遠だから放っておいても相続に影響はないと誤解された
離婚した親の死について連絡が来ないとき、全ての相続人を把握できておらず、そもそも離婚歴があることすら知られていなかったケースもあります。一方で、遺産を相続させたくないという理由で、意図的に連絡されず、無視されている可能性もあります。
たとえ疎遠でも、親の生死についての情報は、親の戸籍を取得すれば確認できます。常に気を配っておくのは難しいでしょうが、親の死が近いときには、念のため注意しておくべきです。なお、連絡が来ないまま、法定相続人である子の関与しないまま遺産分割が終了してしまった場合には、後から相続手続きそのものをやり直しにすることができます。このようなケースは特にトラブルになる可能性が高いため、弁護士から専門的な法的支援を受けるのがおすすめです。
遺産分割のやり直しについて

離婚した親の相続開始の連絡が来たときに子がすべきこと
離婚した親の相続開始の連絡が来たときは、相続人である子としては、やるべきことが多くあります。次に、相続人として、子どもの立場の人がすべきことを解説します。
相続人の確定と相続財産調査を行う
相続の手続きは、相続人が共同で行う必要があります。そのため、相続人の確定をするための調査が必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどることによって、見逃していた相続人を発見することができます。突然に、離婚した親の死亡についての連絡が来たとき、あなた以外にも予想外の相続人が存在している可能性があります。
あわせて、被相続人がどのような遺産を保有していたか知るため、相続財産調査を行います。被相続人が終活をしていたり、遺言書を残していたりすればスムーズに調べられますが、そういった書面のない場合、相続人が自力で調べる必要があります。相続財産を発見するのには、経験が大切なので、手がかりの少ない相続では、経験豊富な弁護士に依頼するのがよいでしょう。
相続に強い弁護士の選び方について

相続放棄するかどうか検討する
相続財産調査を行った結果、借金やローンなどのマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討します。また、離婚した親の相続にこれ以上関わりたくないといった場合も、相続放棄をするのが良い対策となります。相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。なお、3カ月の期限が経過すると単純承認したものとみなされるため注意してください。
相続放棄の基本について

遺産分割協議をする
遺産相続で遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を実施する必要があります。協議を通じて、現金や預貯金、土地や建物といった不動産などの遺産をどう分けるかを決めます。
相続人全員が合意するまで遺産分割協議は続くため、長期化します。離婚した親のうち、一緒に住んでいない方が、新たな家庭を築いた場合、他の相続人は全て「敵」の可能性もあります。遺産分割がもめるケースでは、一人で立ち向かうのではなく、弁護士のサポートを得るようにしてください。
遺産分割がもめる理由と対処法について

離婚後の相続人との不公平を争う
最後に、親の離婚によって、子どもの相続が複雑化するケースは、相続人間に不公平が生じやすい状態となっていることが容易に想像できます。このとき、離婚前の子と、離婚後に再婚した人やその子などといった新たに現れた相続人との間の不公平を解消するための争いが生じがちです。
このとき、遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停や審判といった裁判手続きに移行することとなります。また、遺留分を侵害されるような遺贈(遺言による贈与)や生前贈与が存在するときは、遺留分減殺請求を主張して争いましょう。また、親の離婚後に疎遠となっている場合に、死亡までに財産が他の相続人に分け与えられている可能性があります。このような場合、特別に与えられた利益については相続分に加えて計算すべきであると主張し、特別受益の持戻しが争点となります。
特別受益が認められる場合について

離婚した親が再婚すると子供の相続は複雑化する
離婚した親が再婚している場合、子供の相続は複雑化する可能性があります。事例を交えながら、離婚の絡む相続が複雑化する理由や、その場合の対策について解説します。
再婚相手やその子など相続人が増える
離婚した親が再婚し、子供がいる場合には相続人が増えます。例えば、離婚後に再婚した親の相続では、現在の配偶者と、全ての子が相続人となります。そして、相続人が多いほど、総意をあわせるのが難しくなり、遺産分割協議で全員が納得のいく解決にたどり着くのが困難になります。
被相続人から見て「現在の配偶者」と「前の配偶者の子」では、面識がないケースがほとんどです。同じく法定相続人ではありますが、実情は赤の他人です。現在の配偶者や子からすると「赤の他人が法定相続人であるせいで、得られる遺産が減った」という不満が生じ、争いに発展するのです。
離婚した親の再婚相手にも離婚歴があり、連れ子がいる場合などは、更に事態が複雑です。このような複雑な家庭を持つ人ほど、生前にしっかりと遺言書を作成するメリットは大きく、必ず相続トラブルの対策を講じておいてください。
異母兄弟の相続について

両親が疎遠になりやすくなる
離婚した親とは、心理的に疎遠になってしまう方は多いものです。特に親権を有していない親や、離婚後に再婚した家庭を優先する方とは、ますます関係が希薄化してしまうでしょう。両親の離婚が円満ではなかった場合は特に、子どもからコミュニケーションを控えてしまい、接点がなくなってしまうことも少なくありません。
しかし、疎遠になればなるほど相続でトラブルが起こる可能性が高まります。自分にとって不利な遺言を残される可能性も否定できません。両親の離婚によって生じる相続トラブルを避けたいなら、生前からコミュニケーションを継続することが重要です。再婚相手やその家庭とも一応の面識を作り、連絡をとっておけば、相続が発生したときスムーズに話し合いを行える可能性が高まります。
前妻の子・前夫の子の相続について

親の離婚と子の相続についてのよくある質問
最後に、親の離婚と子の相続についてのよくある質問に回答しておきます。
離婚した親が遺言を残していた場合の相続は?
離婚した親が遺言を残していた場合、原則として遺言の通りに相続されます。このとき、離婚した親と疎遠で、かつ、離婚後に再婚して新たな家庭を作っていた場合だと、離婚前の子どもにとっては不利な遺言書が発見されることは珍しくありません。
法律の定める最低限の相続割合である遺留分すら下回る遺産しかもらえない場合には、他の相続人に対して遺留分侵害額請求をして、不公平を是正するために争えます。
相続財産の内容を全く教えてもらえない場合は?
離婚した親の死について連絡が来たものの、遺産の内容を全く開示してもらえないことがあります。連絡をしてきた他の相続人にとって、できるだけ相続させたくないと希望することがその理由です。
このような場合、相続財産の内容がわからないままに遺産分割協議書にサインをしてはいけません。自身でできる範囲の調査をし、それでもなお不明点、疑問点があるなら、明らかになるまで遺産分割の話し合いは拒否しましょう。遺産分割の争いが長期化すると、遺産分割調停や審判といった裁判所の手続きに移行することとなります。
親の再婚相手から相続放棄するよう求められたら?
両親が離婚後、親が再婚しているとき、相続開始後に、再婚相手やその子から相続放棄するよう求められることがあります。このときにも、安易に応じる必要はなく、法的に権利のある遺産についてはしっかりと主張しておきましょう。
「借金の負担がある」といった脅し文句で相続放棄を迫られるケースもありますが、真実とは限りません。自分では相続財産調査をする自信がないなら弁護士に相談ください。
連絡が来ずに親の相続手続きが終了していたら?
離婚した両親と疎遠になっているケースなどでは「気づいたら親の相続手続きは終了していた」ということもあります。このとき、相続人である子を無視して終了させた遺産分割は無効であり、やり直しを求めることができます。
まとめ
親が離婚している場合でも、子供は相続する権利を有します。死亡した親に親権がなくても、戸籍から外されても関係ありません。
離婚した親が再婚し、再婚相手との間に子供がいる場合など、相続がトラブルになる事態は容易に想定されます。再婚した家庭にとって、離婚前の家庭は、相続権を有するとはいえ既に「過去」であり、できるだけ遺産を渡したくないと思う人が多いからです。争続を避けるには、生前からコミュニケーションを取る、遺言書によって故人の意思を明らかにしておくといった工夫が欠かせません。
複雑な家庭するほど、親の生前からの相続対策は必須であり、相続に強い弁護士と相談することがおすすめです。初回は無料相談を実施する法律事務所もあるので気軽に利用してみてください。


