浅野英之(弁護士)– Author –
-

遺留分を渡さなくていい方法はある?遺留分を払わないとどうなる?

-

会社を放置すると危険?休眠会社のメリット・デメリットと注意点4つ

-

超過特別受益とは?法定相続分を超える利益を返還する必要はある?

-

特別縁故者とは?認められるケースと要件、財産を受け取る流れを解説

-

死後離縁とは?相続開始後に養子縁組を解消する方法と注意点

-

遺留分侵害額請求の期限はいつまで?時効・除斥期間は?

-

遺産分割はやり直しできる?やり直せる条件と方法、見直す際の注意点

-

死後離婚とは?メリットやデメリットと相続への影響について

-

相続問題の解決は弁護士と司法書士のどちらに相談すべき?

-

死亡後の預金引き出しの法的問題と相続トラブルを避けるための解決策

-

第三者対抗要件とは?不動産の取引や相続において問題となるケース

-

親に遺言を書いてもらう方法は?7つのテクニックを解説

-

生命保険は遺産分割の対象ではない!死亡保険金が遺産になる例外も解説

-

遺言と異なる遺産分割は有効?全相続人が同意すれば可能だが例外あり

-

子供に相続させたくないときにすべき対策と6つの方法

-
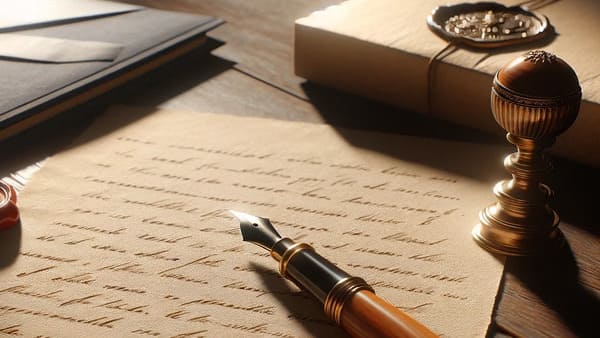
遺留分侵害額請求の通知書の書き方と、内容証明の注意点【書式付】

-

遺言書を紛失してしまったときの対応と再作成の注意点

-

遺言能力とは?遺言の有効性の判断基準をわかりやすく解説

-

相続は弁護士が重要!相続に強い弁護士の選び方ガイド

-

不動産売買における仲介と代理の違いについて解説

-

相続した不動産の調査方法と、探す時の注意点を解説します

-

相続する借金の調べ方は?相続負債を調査する具体的な方法

-

相続放棄をしたかどうか確認する方法は?照会の手順を解説

-

相続放棄申述受理証明書とは?取得の必要な場面と入手方法

-

生前贈与の契約書とは?必要な理由と作成方法【書式付】

-

相続放棄したら督促状は放置しても大丈夫?すべき対応を解説

-

相続人全員が相続放棄して相続人がいなくなったら財産は誰のもの?

-
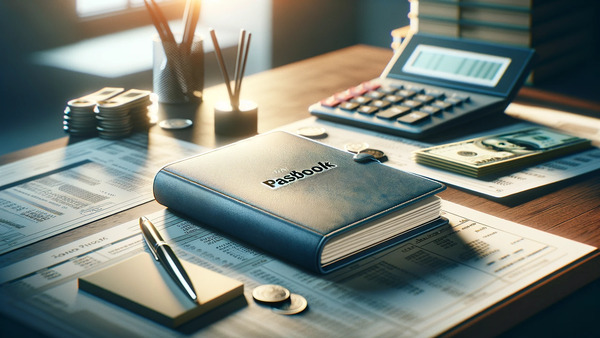
遺産分割で預貯金をうまく分ける方法と、分け方のポイントを解説

-

相続で委任状が必要なケースと委任状の書き方

-
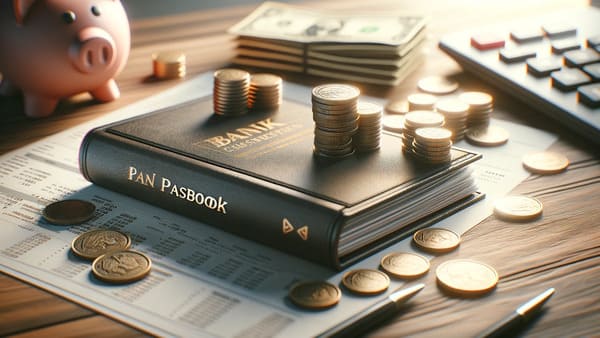
相続財産となる預貯金はどのように調査すればよいですか?

-

子供に相続させたくないときにすべき対策と6つの方法

-

相続で委任状が必要なケースと委任状の書き方

-

相続放棄してほしいと言われたらどう対応すべき?

-

清算手続き中の会社ができること、できないこと

-
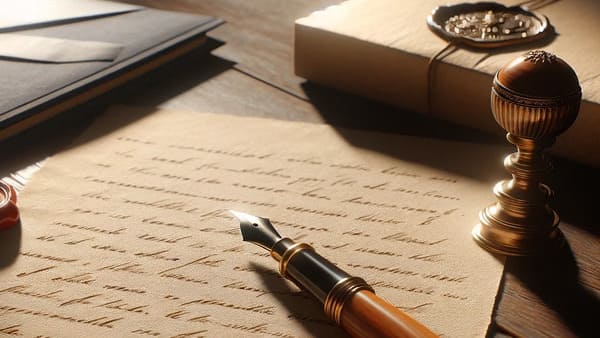
遺留分侵害額請求の通知書の書き方と、内容証明の注意点【書式付】

-

会社を放置すると危険?休眠会社のメリット・デメリットと注意点4つ

-

遺言書に書いた財産がなくなった場合の対応は?書き直さないと無効?

-
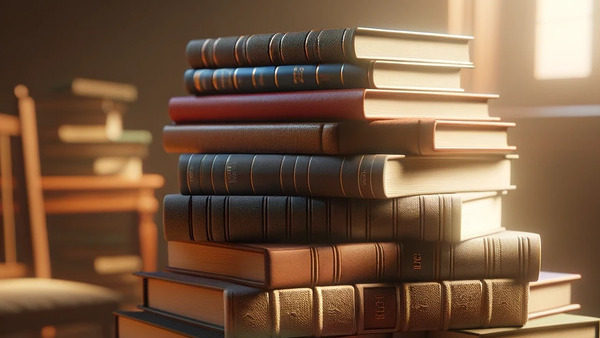
改製原戸籍とは?入手方法と相続手続きにおける利用法

-

遺言書を勝手に作成されてしまったらどう対処すべきですか?

-

遺産分割協議書とは?作成方法と注意点を解説【書式付】

-

亡くなった人の連帯保証人だと相続放棄できない?4つの対応

-

会社をたたむ方法3つ!解散・清算・破産の違いとメリットの比較

-

相続財産目録とは?作成方法と書き方の注意点【書式付】

-

外国人の相続人がいる相続手続きの注意点

-

超過特別受益とは?法定相続分を超える利益を返還する必要はある?

-

相続した連帯保証人の保証債務に消滅時効はある?

-

相続放棄したら督促状は放置しても大丈夫?すべき対応を解説

-

不動産売買における仲介と代理の違いについて解説

-

前妻の子・前夫の子も相続できる?財産を与えない方法はある?

-

いとこが亡くなったら遺産を相続できる?いとこが相続する方法は?

-
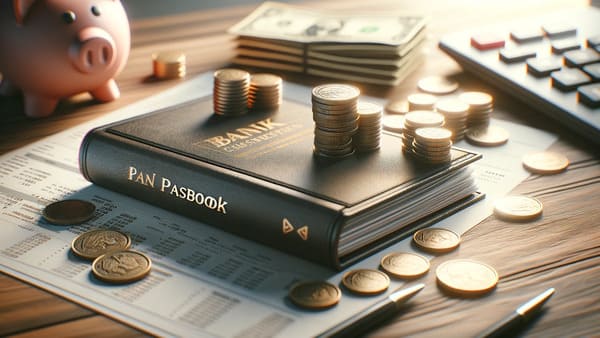
相続財産となる預貯金はどのように調査すればよいですか?

-

相続放棄と自己破産はどちらがよい?違い、判断基準と注意点を解説

-

夫婦で自宅を共有しているときの相続の注意点は?

-

相続財産に債務(借金・ローン)がある場合の遺留分の計算方法は?

-

生命保険の受取人が死亡していたときの対応方法と注意点4つ

-

連帯保証人の保証債務を、複数人で相続したとき、どう分割する?

-

換価分割とは?分割時の注意点6つと不動産相続の注意点

-

口約束の相続は有効?口約束した遺産をもらう2つの方法

-

相続した不動産の調査方法と、探す時の注意点を解説します

-

第三者対抗要件とは?不動産の取引や相続において問題となるケース


