相続放棄は、相続する権利を放棄することですが、これによって特に、亡くなった方の借金などマイナスの財産を引き継がずに済む効果があります。相続放棄をしたことを証する書面に、「相続放棄申述受理通知書」「相続放棄申述受理証明書」という2種類があります。
これらの書面が、相続放棄を主張するのに必要な場面があり、入手方法を理解しておく必要があります。今回は、これら相続放棄を証明する書面の入手方法について解説します。
相続放棄を証明する書類
まず、相続放棄を証明する2つの書類、相続放棄申述受理証明書、相続放棄申述受理通知書について、それぞれ解説します。名称が似ていますが「証明書」「通知書」という点が異なることに留意してください。
相続放棄申述受理証明書とは
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを家庭裁判所が証明する書類です。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、ある相続人が本当に相続放棄したのかは、第三者からは分かりません。そこで相続放棄したことを証明する書類が必要となり、その際に活用できるのが相続放棄申述受理証明書です。
この書面には、以下のような内容が記載されます。
続放棄申述受理証明書
事件番号 平成〇年(家)第〇〇号
申述人氏名 〇〇 〇〇
被相続人氏名 〇〇 〇〇
本籍 〇〇〇〇
死亡年月日 平成〇年〇月〇日
申述を受理した日 平成〇年〇月〇日
上記の通り、証明する
20XX年XX月XX日
東京地方家庭裁判所
裁判所書記官 相続 太郎
なお、相続放棄の手続きをしても、この相続放棄申述受理証明書は自動的には発行されず、証明書を入手するためには別途の申請手続きを要します。
相続放棄申述受理通知書とは
相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が、相続放棄の申し立てを受け付けたことを通知する書面です。この通知書は、手続きの受理を通知するもので、相続放棄をした本人に対して、1回きり、1通しか発行されず、再交付は認められません。
相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されないため、通知を受けたら早めにコピーし、失くさないよう保管してください。また、本人にしか交付されないので、第三者が相続放棄を証明する必要のあるときは、前述の相続放棄申述受理証明書を活用します。
相続放棄の証明書が必要なケース
では、相続放棄申述受理証明書などの、相続放棄を証明する書類が必要なのは、どのようなケースでしょうか。相続において必要となる場面について解説します。
不動産の相続登記
相続登記は、不動産を相続によって承継した際の名義変更のことです。
不動産の相続登記において、相続放棄している人がいるときは、その証明書を出し、既に相続人ではないことを証明する必要があります。そうでないと、残った他の相続人の登記名義に移すことはできません。このとき、戸籍謄本を収集すれば「法定相続人であること」は証明できますが、相続放棄したことまでは戸籍には記載されません。
相続登記の手続きについて

金融機関の手続き
被相続人が亡くなると銀行などの口座は凍結され、相続手続きのなかで、凍結を解除し、解約や払戻しを受ける必要があります。このとき、相続放棄をした相続人がいるときは、そのことを証明するための書面の提出を求められます。
相続放棄申述受理証明書、相続放棄申述受理通知書のいずれが必要かは、事前に金融機関に問い合あせて確認してください。
債権者に相続放棄を証明する場面
相続放棄のメリットは、被相続人の負債の返済が不要となることです。被相続人の債権者が請求してきたときに、相続放棄を理由として返済義務のないことを主張するために、その証明書を出して説得する必要があります。厳密な債権者ほど、相続放棄申述受理証明書など、公的な書面の提出を求めてきます。
なお、相続放棄をすれば被相続人の借金を返済する必要はなく、取立てが止まない場合には弁護士を窓口として通知する方法が有効です。
なお、相続放棄受理証明書は、相続放棄した本人だけでなく、債権者などの利害関係人も取得できます。相続放棄をした家庭裁判所名と事件番号を伝えれば、債権者でも証明書を取得し、相続放棄の有無を調べることができます。
相続放棄後の督促状への対応について
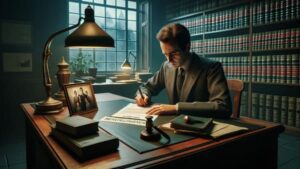
相続放棄の証明書を入手する方法
相続放棄の決断をしてから、その申述、そして証明書の入手までの流れを解説します。
- 相続放棄を家庭裁判所に申述する。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申述先となる。 - 家庭裁判所より送付された照会書に記入し、返送する。
- 相続放棄申述受理通知書が送付される(1通のみ)。
- 必要に応じて相続放棄申述受理証明書の発行を申請する。
相続放棄と同じ家庭裁判所が管轄となる。被相続人の最後の住所地は、戸籍の附票や住民票の除票などで調査することができる。
前述の通り、相続放棄申述受理通知書は、「相続放棄の申述を受け付けた」という家庭裁判所からの知らせであり、相続放棄した本人に対して1通発行されるのみです。これに対し、相続放棄申述受理証明書は、本人以外の利害関係人が発行を申請でき、かつ、必要な部数だけ発行してもらえます。
申請書式は、家庭裁判所からの通知に同封されているほか、裁判所のサイトからもダウンロード可能です。自身で対応するのが難しいときは、専門家のサポートをお受けください。
以下では、申請時の注意点について解説します。
証明書を請求できる人は?
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄した本人だけでなく、利害関係人も請求可能だと解説しました。利害関係人には、例えば次の者が該当します。
- 相続人が複数いる場合の共同相続人
- 被相続人の債権者
共同相続人は、相続放棄の有無によって自身の得られる遺産の割合が変わりますし、被相続人の債権者は、相続放棄の有無によって債権の請求先を判断しなければならず、いずれも利害関係があることが明らかです。
証明書の申請に必要な資料は?
相続放棄申述受理証明書の申請に必要となる書類は、立場によって異なることがありますが、あらかじめ家庭裁判所に問い合わせて確認しておきましょう。
相続放棄した本人が申請する場合、利害関係人のうち共同相続人、被相続人の債権者が申請する場合の、それぞれの必要書類は、次の通りです。
【本人が申請する場合】
- 申請書(本人用)
- 公的な身分証明書
- 収入印紙(1通150円)
- 認印
- (郵送の場合)返送用封筒と郵便切手
※なお、申請の際には相続放棄申述受理通知書も持参するとスムーズです。
【共同相続人が申請する場合】
- 申請書(利害関係人用)
- 利害関係を疎明する資料
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、申請者の戸籍謄本など - 公的な身分証明書
- 収入印紙(1通150円)
- 認印
- (郵送の場合)返送用封筒と郵便切手
【被相続人の債権者が申請する場合】
- 申請書(利害関係人用)
- (申請者が個人の場合)申請者の身分証明書の写し
- (申請者が法人の場合)資格証明書の原本
- 利害関係を疎明する資料
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、債権者であることを示す資料(債権者となった状況によって金銭消費貸借契約書、借用書など) - 収入印紙(1通150円)
- (郵送の場合)返送用封筒と郵便切手
特に、利害関係人が申請する場合には、その利害関係を示す資料が必要となる点に注意が必要です。
相続に必要な戸籍の集め方について

相続放棄の証明書を入手する際の注意点
最後に、相続放棄申述受理証明書など、相続放棄を証明する書類を入手する際の注意点を解説します。
申請書は正確に記載する
相続放棄申述受理証明書を申請するとき、その申請書は正確に記載してください。相続放棄の事件番号などの情報を誤ると、正しい証明書が発行されず、求める相続人の放棄に関する情報を得られなくなってしまいます。
なお、そもそも相続放棄の有無が不明な場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して照会を行い、調査することができます。
証明書は再発行できる
相続放棄申述受理証明書は、必要に応じて再発行を求めることができます。なお、家庭裁判所において相続放棄の情報が保存される期間は30年とされています。
証明書は、不動産の相続登記や、債権者に対する放棄の事実の証明のために使われ、いずれも、それら権利の取得時効や消滅時効の方が、30年より前に来るため、30年前の証明書が必要となる場面はあまりないでしょうが、できるだけ早めに入手しておくに越したことはありません。
相続放棄の照会について

まとめ
今回は、相続放棄申述受理証明書の意味と、その利用方法、入手方法について解説しました。
被相続人が大きな借金を抱えて死亡した場合など、債務を相続しないためには相続放棄が必要ですが、この手続きを対外的に証明する手段を知っておかなければ活用できません。


