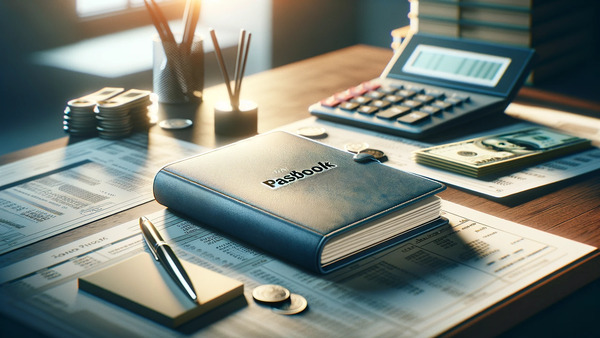遺産分割は、故人の遺産を相続人間で分けるプロセスです。
相続人が複数いる場合、遺言書に基づくか、遺言のない場合には、相続人同士の合意によって遺産分割が行われます。遺産分割協議では、相続人間の紛争を避けるためにも、公平かつ明確な合意形成が重要です。
※ 遺産分割の基本

遺産分割は、故人の遺産を相続人間で分けるプロセスです。
相続人が複数いる場合、遺言書に基づくか、遺言のない場合には、相続人同士の合意によって遺産分割が行われます。遺産分割協議では、相続人間の紛争を避けるためにも、公平かつ明確な合意形成が重要です。
※ 遺産分割の基本