遺言は、不確実な未来に備え、大切な人への最後のメッセージとして、遺志を残す重要な手段です。しかし、遺言を残すには「遺言能力」が必要となります。つまり、遺言能力とは、遺言を有効に作成するための能力です。遺言能力について具体的にどんな条件が必要かは、法律で定められています。
遺言能力のない人が残した遺言は無効です。精神的な障害や認知症などで判断能力の欠如した方が典型例です。このとき、作成した遺言がかえって争いを生んでしまうので、対策が必要です。
今回は、遺言能力の意味や判断基準、無効にならないようにする対策を解説します。また、いざ遺言能力が争いになった場合には、弁護士に相談して対応するのが有効です。
遺言能力とは
遺言能力とは、自らの意思で遺言を作成し、その内容を理解し、決定できる能力です。
遺言は、遺志を将来の分割に反映する目的で残されます。その意思がしっかり定められる状態でなければ、遺言の効力を発揮できないわけです。
遺言能力について定めた民法の規定は、次の通りです。
民法963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
遺言能力の有無は、その遺言の有効性を判断する重要な基準です。遺言を有効に残すには、遺言能力が必要で、遺言能力のない状態で残した遺言は無効です。
遺言能力は、人ごとの判断ではなくその作成時の状況による判断です。そのため、精神の障害や認知症などで判断能力の弱い人でも、時と場合によって、遺言能力が有ったり無かったりします。
遺言能力を有するための条件
遺言能力を有するといえるには、次の条件を満たす必要があります。
- 意思表示の能力
自己の意思に基づいて遺言をする意思表示ができること - 内容理解の能力
遺言の内容とその法的な影響を理解できること - 判断力
遺言によって自己の財産をどのように分配するかを合理的に判断できること
以上の3つの条件がそろって初めて、遺言能力が認められます。遺言は、相続財産の最終的な処分を決定するもので、時には高額な財産に関する判断となることも少なくありません。これらの条件を備え、その意思表示が自らの真意に沿うものである必要性が非常に強いのです。
遺言能力が求められる背景
遺言能力が法的に求められる背景に、遺言の自由と保護があります。
遺言は、個人の最終意思として尊重されるべきですが、そのためには自己の意思に基づいて遺言する能力が当然の前提となります。また、遺言能力を要求することは、遺言者の真意を尊重し、家族などの利害関係人による不当な影響から、遺言者を保護するのにも役立ちます。
したがって、遺言能力の有無は、しばしば相続の中心的な争点になります。遺言によって損する相続人は、その有効性に疑いがあれば激しく争うでしょう。遺言書の作成時は、特に注意深く進める必要があり、精神状態や判断力を適切に評価し、遺言能力を確認するのが大切です。
遺言書の基本について

遺言能力の判断基準
次に、遺言能力の判断基準について解説します。
遺言能力の判断基準は、遺言が有効か、無効かを決める重要な要素となります。遺言を書く際に配慮すべきは当然のこと、相続開始後に、遺言の有効性を争うときにも理解しておく必要があります。
満15歳以上であること
まず年齢について、有効に遺言を残すには、満15歳以上であることが必要です(民法961条)。未成年であっても、満15歳に達すれば遺言を残せる一方、14歳未満の場合にはどれほど判断力があっても、親の同意があっても、遺言は残せません。
また、遺言は本人が作成する必要があり、親権者が代わりにすることはできません(遺言代理禁止の原則)。なお、満15歳に達していても、他の条件を理由として判断能力が欠如していると、遺言能力を認められないことがあります。
事理弁識能力があること
有効に遺言を残すには、事理弁識能力が必要とされます。これは、遺言の内容と、その遺言に基づく法的な効果を、弁識し、判断するに足りる能力があるという意味です。
事理弁識能力があるかどうかは、様々な事情の総合考慮によって決めるしかなく、裁判例でも多くの議論がされてきました。精神医学の観点に加え、遺言の内容や作成経緯なども考慮されます。
考慮される事情には、次のものがあります。
- 精神的な障害の有無、性質、及び程度
精神疾患や認知症だというだけで遺言能力を否定されることはありません。症状の内容や重さが検討されますが、この評価は、医学的な判断に加え、遺言をする前後の行動や言動が参考にされます。「長谷川式簡易知能評価スケール」が有名です。 - 年齢
高齢になるほど記憶や判断力が衰えるのが通例ですが、ただ高齢だというだけで遺言能力が否定されるわけではなく、個別の事情ごとの判断となります。 - 遺言をした前後の行動や状況
遺言前後の行動が、遺言能力の評価に影響します。例えば、退院直後の遺言の場合、入院中や退院時の行動や医師とのやり取りなどが参考にされます。 - 遺言を作成する背景や動機、理由
遺言を残す理由などが、その内容と整合性があるか、合理的かどうかによって、遺言能力の有無が判断されます。 - 遺言の内容
遺言そのものの内容が、遺言者の意図に合致しているか、自然かつ合理的かといった点も遺言能力に影響します。内容が明瞭でシンプルなほど遺言能力が認められやすく、複雑で難解なほど遺言能力が否定されやすいです。 - 遺言者と相続人や受遺者との人間関係
以前からの深い関係がある場合は遺言能力が認められやすいですが、関係が希薄な場合は遺言能力が否定される傾向があります。
これらの要素は、総合的に、かつ、それぞれが関係して影響します。
例えば、遺言の内容や効果が簡単なものであるほど、必要となる理解力は低くても足りると考えられます。人間関係の深い人なら、相当高額な遺贈(遺言による贈与)でも自然と判断されるでしょうが、関係が希薄な人への多額の贈与は不自然であり、理解力の欠如から来る遺言であると判断される可能性があります。
(成年被後見人の場合)医師2名の立会い
成年被後見人の遺言能力については、民法に定めがあります。成年被後見人は、家庭裁判所への申立てによって成年後見人を選任され、判断能力を欠くことを明らかにされた人であり、遺言能力に疑いが生じやすいために特に注意を要するからです。
民法973条(成年被後見人の遺言)
1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2. 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
したがって、成年被後見人の場合は、事理弁識能力が一時的に回復した状態で遺言を作成するにあたり、医師2名の立ち会いが必要となります。なお、被補佐人、被補助人には、この規定は適用されないものの、やはり遺言能力を疑われやすいため注意が必要です。
遺言能力について争う方法
自身にとって不利な遺言が残っていたとき、遺言能力を争う方法は次の通りです。
遺言能力に関する証拠を集める
遺言作成時点の遺言能力に疑いがあるとき、まずは証拠を収集しましょう。最も大切なのは、その遺言それ自体であり、不自然な点、不合理な内容がないか確認してください。次に重要なのが、診断書やカルテなどの医療記録によって当時の健康状態を調査することです。
相続人間で話し合う
次に、相続人間での話し合いを行いましょう。相続人全員の同意があれば、遺言で禁止されていない限り、遺言とは異なる分割も可能です。ただ、遺言によって得する相続人にとっては、遺言能力がないという主張は容易には納得しがたく、合意は得づらいものです。
遺言無効確認訴訟を提起する
話し合いで解決しない場合は、遺言無効確認訴訟を起こして遺言の有効性を争います。遺言の有効性は、遺産分割の前提問題とされており、遺産分割に先立って「遺言が有効かどうか」の決着を付ける必要があります。
遺言能力を争われないための生前対策
最後に、遺言能力を争われないように遺言を残す方法を解説します。
特に、精神障害や認知症、高齢などによって遺言能力に不安のある方、不公平な分割を考えていて遺言能力を争われる可能性の高い方にとって、できるだけ有効に遺言を残すには、徹底した生前の対策が欠かせません。
不公平な遺言にしない
不公平な遺言ほど、争いになりやすいものです。自分にとって不利な遺言に不満を抱くのは当然でしょう。遺留分を侵害する遺言がその典型例です。そのため、遺言能力が争われないようにするには、不公平な遺言を残さないことが最善です。また、どうしても偏った遺産の分配を希望する場合には、それによって不利益を被る相続人に配慮し、理解を求めることが大切です。
生前からしっかりとコミュニケーションをとることが、遺言能力の争いを避けることに繋がります。
遺留分の基本について
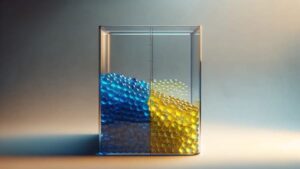
遺言能力を証明する資料を準備する
前章の通り、遺言能力の争いは、交渉から始まり、最終的には遺言無効確認訴訟で判断されます。そして、裁判所の判断は、証拠に基づいて下されるため、証拠となる資料をあらかじめ準備しておくことが良い対策となります。
遺言能力の判断基準についての解説を参考にして、次の証拠を収集してください。
- 遺言作成の前後の行動を記した日記
- 遺言作成の理由を記したメモ
- 診断書やカルテ、看護記録などの医療記録
- 医師の証言
- 遺言作成時の状況の録画、録音
- 遺言書の筆跡鑑定
また、公正証書遺言の方式を利用すれば、公証人と証人2名の関与のもとで遺言を作成できるため、遺言能力が争われるケースに備えることができます。
公正証書遺言の書き方について

まとめ
今回は、遺言能力、つまり、遺言を有効に残すことのできる能力について解説しました。
遺言能力は、遺言を残す方にとって、後世に禍根を残すことのないように配慮しなければならない重要なポイントです。そして、残された家族にとっても、発見された遺言が有効なものかどうかを判断し、公平な遺産分割を実現するのに非常に大切です。


