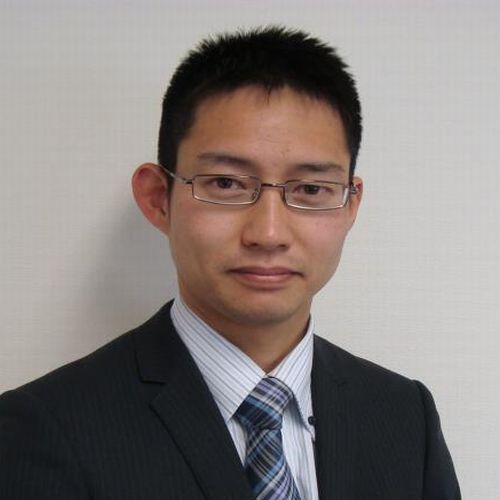分筆は、1つの土地を、2つ以上に分けることであり、不動産登記の専門用語です。具体的には、1つの登記簿に記載されている土地を、2つ以上の登記簿に載るように分割します。専門用語で、土地は「1筆(ふで)」「2筆(ふで)」と数えるので、「筆を分ける」という意味で「分筆」と呼びます。
分筆には、法律上、税務上の様々なメリットがあり、相続の前後でもよく活用されています。分筆は、土地家屋調査士の専門分野です。その具体的な方法や、相続、営繕対策などでの活用例について解説します。
分筆とは
分筆とは、1つの土地を、2つ以上に分けることです。
「土地を分ける」といっても、境界線を作ったり塀を建てたりして物理的に分けるわけではありません。土地は、国の制度である登記制度によって登録されています。この登記簿の上で、これまで1つの登記簿に記載されていた土地を、2つの登記簿に載るように分けるのが分筆です。そのため、土地の現況は、分筆前後で全く変わりませんが、分筆すると登記簿上の地番に枝番が付きます。
例えば、土地を2つに分筆したときの登記簿上の表記は次のようになります。
- 分筆前
「2番地」 - 分筆後
「2番地の1」と「2番地の2」
1つの土地だったものは、分筆によって登記上別々の土地とみなされるので、法律上、税務上様々な効果が生まれます。
分筆も、所有権移転や抵当権設定と同じく登記手続きなので、専門家に依頼するのがお勧めですが、登記を担当する司法書士とは異なり、分筆では現況調査や測量によって境界を決める必要となるために土地家屋調査士のサポートを要します。

相続において分筆を活用すべきケース
次に、相続において土地の分筆を利用したほうがよいケースを解説します。
相続において、遺産に土地が含まれるとき、分筆を活用したほうが有利になることがあります。相続前の生前対策はもちろんのこと、相続後の遺産分割でも、分筆が利用されることがあります。
分筆のメリットについて

相続財産に占める土地の割合が高い場合
相続の場面で、不動産は特に価値が高く、そのままでは遺産分割しづらい場面があります。亡くなった方(被相続人)が広い土地、立地の良い土地を持っていると、評価額が高額となりすぎて、相続の支障となることがあるのです。遺産に占める土地の割合が高すぎる相続は、調整的に利用できる預貯金や現金などの分けやすい財産が少ないと、協議が難航して争続になります。
土地しかめぼしい財産がないとすれば、相続人はみな土地を欲しがるでしょう。しかし、その土地が1つのままでは、相続人間で公平に分けることができません。とはいえ、分けずに共有のまま放置すれば、争いが長期化し将来の禍根を残します。
そのため、遺産に占める土地の割合が高すぎることが判明している場合、生前対策として、家族が死亡するより前に土地を分筆するのが有益です。可能ならば、相続人の人数や、相続分の割合に応じて分筆しておくのがよいでしょう。また、生前対策が間に合わなくても、遺産分割時に分筆すれば、公平に遺産分割協議を成立させる可能性を高めることがきます。
土地の一部だけを売却したい場合
相続人間で、土地の活用方法について意見が分かれることがあり、このとき、全ての人の納得いく解決を模索するために、分筆を活用すべきケースがあります。
土地は、登記簿上の単位でしか取引できないので、1つの土地のままでは、その1つを売却することはできません。分筆によって2つ以上に分ければ、別々に処分することができ、意見の相違する各相続人の希望をそれぞれ叶えることができます。例えば、次の例があります。
- 自宅として利用したい相続人と、既に実家を離れており売却したい相続人の対立
- 投資不動産を現在の賃貸人に貸し続けたい相続人と、売却したい相続人の対立
相続人同士に資金力の格差があるとき、資力の少ない相続人は、相続のタイミングで不動産を現金化することを望む例はよくあります。そして、資力の十分な相続人にとっては、寝かせておきたいという需要があり、対立を生むのです。
土地の一部の用途を変更したい場合
土地の用途を、専門用語で「地目」といいます。登記簿に記載される地目は「宅地」「田」「畑」「雑種地」など、利用目的によって様々です。この地目もまた、1つの土地の一部だけ変更することは許されません。
したがって、相続で取得した不動産の用途を一部だけ変更したい場合には、分筆が必要です。例えば、これまで被相続人が自宅として使用していた土地の一部を、不要となった広い自宅を建て替えて駐車場にしたいケースなどは、典型的な分筆の活用例です。
土地の相続税評価額が高額な場合
土地の相続税評価が高すぎるときにも、分筆を活用して評価額を下げるべき場面といえます。不動産の価値が高すぎると、それ以外の遺産から相続税を払いきれない場合があり、この場合、生前からの節税対策として、分筆が効果を発揮します。
つまり、相続税の支払いをする余力がないとき、土地の一部を分筆して売却し、納税資金を捻出したり、土地の一部を相続税の物納に供したりすることができます。土地の分筆に相続税が絡む場合には、遺産全体を総合的に見た税務のプランニングが必要なため、税理士のアドバイスを聞いて進める必要があります。
公平な土地活用を希望するとき
土地がある程度の面積があると、遺産分割のときの最も公平な分け方が、相続分にしたがった土地そのものの分割であることも少なくありません。つまり、土地の現物分割の場面です。このとき、土地そのものを分けるには、分筆が必要となります。
ただし、立地や形状、接する道路の幅や種類によっては、単純に面積比で分けたとしても価値が平等にはならないおそれがあり、土地評価が難しい場面もあります。
分筆と分割の違い
分筆と似た用語に「分割」があります。
分筆が、土地を登記簿上で2つに分けるのに対して、単に土地を2つに物理的に分けることを「分割」と呼びます。また、分筆は専門用語であるのに対して、分割は一般的に使われる日常用語です。そのため、分筆と分割は混同されたり、一緒に使われたりすることがあります。
1つの土地を、塀や壁で2つに区分して、2人の共有者で利用するという場合に、分筆はしなくても、土地の分割はした、と考えることもあります。なお、「遺産分割」というときの「分割」は、専門的な法律用語であり、承継した相続財産を、相続人らで分けることを意味します。遺産に複数の土地が含まれ、それぞれを相続人で別々に分けるときには、分筆は必要ありません。
遺産分割の基本について

土地を分筆する具体的な方法
最後に、土地を分筆すべきケースにおいて、具体的に分筆をする方法を解説します。
土地の分筆手続きには、2〜6ヶ月程度の長い期間がかかります。相続の場面で、亡くなる前にあわてて生前対策をしようとするのではなく、十分な時間的余裕を見ておきましょう。
分筆の話し合いをする
ある土地を分筆して2つ以上に分けるとき、分筆の割合に決まりはありません。そのため、必ずしも「等分」でなくてもよく、土地の形状や利用方法、所有者間の公平や平等を考慮し、どの境界で分筆するのが適切か、話し合いをする必要があります。
相続した不動産を分筆する場合、共有となっている相続人間での話し合いは、遺産分割協議と同時に行うことができます。このとき、必ずしも法定相続分に応じた分筆とする必要もありません。相続のタイミングで分筆を希望する場合、分筆登記の申請は相続人全員でする必要があります(この点でも、遺産分割協議が成立しなければ、分筆登記に合意してもらえないでしょう)。
共同相続人の1人が分筆登記に協力しないときは、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てます。
測量を行う
分筆の割合が決まったら、次に、土地家屋調査士に依頼し、測量の方法によって、土地の現況を調査します。
分筆の登記を行う
調査が済んだら、土地家屋調査士が分筆の登記をします。これは、登記の種類のうち、表題登記となります。
分筆登記にかかる土地家屋調査士の費用は、確定測量が必要なケースで土地の面積や隣接土地所有者の人数、公道か私道かなどで変動しますが、100〜200㎡程の宅地を2分割する場合だと、概算で40万円〜90万円程度が相場です。面積が広かったり、地形が複雑だったり、近隣対応の人数が多かったりする難易度の高いケースでは、100万円以上の費用がかかる場合があります。
不動産登記について

まとめ
今回は、分筆の基礎知識と、特に不動産相続において必要となる分筆登記の手続きについて、土地家屋調査士が解説しました。
分筆は、争続を回避したり、相続税を安く抑えたりといった、相続の様々な場面で活用することができますが、費用もかかるため、最適な方法かどうか、事前に専門家との相談が必要です。