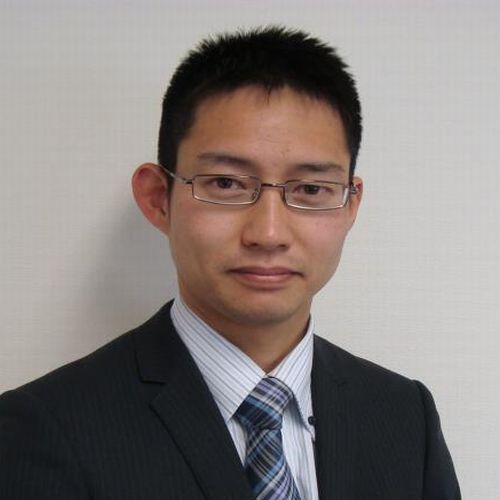面積が広く、形もよい土地は使い勝手がよいため、土地の価値が高くなります。しかし、相続の場面では、良い土地ばかりでなく、活用に悩むものも多く登場します。
このようなとき、資産価値が低く、むしろ「誰に相続させるのか」「相続税を払えるのか」といった悩みを生む財産にもなってしまいます。「財産がなければ争続にはならないのでは」と考える人もいますが、財産価値の低い不動産もまた、多くの問題を引き起こし、相続トラブルの火種となります。
今回は、活用の難しい土地を分筆するメリットについて、活用例とともに解説します。
そもそも分筆とは
分筆とは、不動産(土地や建物)が1つの登記簿に記載された状態から、複数の登記簿に分ける手続きです。この手続きは、不動産を複数の所有者に分割する場面や、一部の土地を売却・譲渡するときに必要となります。分筆すると、各土地に個別の登記簿が作成され、法的に独立した扱いを受けます。
これにより、管理や取引が容易になる効果があります。分筆の手続きの概要は、次の通りです。
- 測量の実施
分筆する土地の境界を確定するため測量をします。土地家屋調査士に依頼するのが通例です。 - 法務局への申請
分筆申請書や測量図、登記申請書を準備し、法務局に提出します。 - 登記の完了
法務局での審査を経て、分筆が承認されると、新しい登記簿が作成されます。
分筆手続きには、測量費用や登記手数料などがかかります。また、手続きの複雑さや土地の状況によっては、専門家の助言が必要になります。
分筆の基本について

分筆のメリット
土地を分筆することには、大きなメリットがありますので、それらの利点について解説します。
相続の場面では、分筆は、相続開始後に遺産分割を公正に進めるのにも役立ちますが、生前の対策にこそ効果を発揮します。
財産管理が容易になる
分筆のメリットの1つ目が、財産管理が容易になることです。
分筆をすることで、土地や建物の利用状況に合わせた、明確な所有権を登記簿に反映することができます。これにより、自身の財産を正確に把握できるようにし、所有者や共有者、隣地の所有者との間で、財産を明確化し、将来のトラブルを防ぐことができます。また、取引のしやすさにも繋がり、土地の一部を売却したり、特定の区画を活用したりするのに役立ちます。より柔軟かつ迅速に不動産取引を進めるためには、分筆は欠かせません。
どの土地を誰に譲渡するかを明確にすることは、相続時のトラブル防止にもなります。
資産価値を最大化できる
分筆のメリットの2つ目は、不動産の資産価値を最大化できることです。
不動産市場には多様なニーズがありますが、大規模な土地よりも小規模なものを求める人が多く、分筆によって市場のニーズに合わせた免責とすることは、価格の高騰に繋がります。特に都市部では小規模の土地の需要が高く、分筆によって資産価値を高めることができます。また、分筆によって土地の一部の利用目的を変えることができ、潜在的な価値の引き上げにもなります。
そして、分筆すれば、柔軟に販売したり賃貸したり、開発計画に供したりすることができますし、不動産に投資をする人にもリスクが低く好まれるようになります。
相続税を節税できる
次に、分筆のメリットの3つ目が、相続税を節税できる点です。
分筆をうまく活用すれば、相続税の計算上、1つの土地のまま評価するよりも、税額を低く抑えることができます。例えば、2つの道路に面した便利な土地は価値が高く、分筆によって、それぞれが1面しか道路のない土地となれば、各土地の評価額の合計は下がることになります。
相続が開始するより前に、生前から土地の分筆をしておけば、それにかかる諸費用についても遺産から支出することができます。
遺産分割に資する
不動産は、そもそも分けづらい財産です。建物は物理的に半分にすることができないですし、土地についても小さければ小さいほど分けることができません。とはいえ、共有のまま放置しておけば、いつまでも嫌な相続人と顔を突き合わせなければならず、いつ紛争化するかもわかりません。
分筆を有効的に進めなければ、遺産分割のトラブルは拡大してしまいます。ただ、大規模で価値の高い土地でも、分け方によっては公平でなくなるため、片方だけ価値が上がってしまいトラブルの原因となります。
遺産分割の基本について

分筆を検討する際の注意点
最後に、分筆を検討する際に気をつけておくべき注意点について解説します。
分筆のリスクと注意点
分筆は多くのメリットをもたらしますが、リスクや注意すべき点もあります。
- 分筆には費用がかかる
測量費用、申請費用などがかかります。費用は、土地の大きさや形状、隣接地の所有者の数、接する道路が公道か私道か、といった点で変わるものの、少なくとも40〜50万円はかかる可能性があります。 - 分筆には時間がかかる
分筆の手続きには時間がかかることがあります。測量や、隣地所有者との交渉などを含め、少なくとも3ヶ月程度は余裕を見ておきましょう。相続の場面だと、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に間に合うように進めなければなりません。 - 土地活用の制約がある可能性がある
分筆を行う前に、地域の土地や建物の規制がないか調査してください。建築規制などがあると、分筆で狙っていた土地活用ができない可能性があります。また、分筆された土地に基本的なインフラ(電気、水道、ガスなど)が接続できるか確認が必要です。 - 近隣との関係に注意する
分筆により、近隣の土地所有者が増える可能性があり、その場合に境界線や権利の争いに発展します。
注意点として、分筆がかえって争いのもとにならないようにしなければなりません。特に、相続の場面で活用する際には、分筆によって土地の市場価値が高まると、かえって相続税が高くなってしまう危険があります。誰がどのように相続するかが決まっていないのに不用意に分筆すると、遺産分割の争いが起こりやすくなります。
また、不合理な分割は認められず、1つの土地が道路に全く接しないようにしたり、2メートル以上の道路に接していない土地が出現したりすると、実態のない分筆であると判断されるおそれがあります。
分筆の適切なタイミング
分筆を行う適切なタイミングは、次の要素に基づいて検討してください。分筆によるタイミングをしっかり検討し、土地の価値を最大化し、法的なリスクを避けることができます。すべての要因を慎重に検討し、適切な計画を立てることが重要です。
まとめ
今回は、分筆のメリットについて解説しました。特に、相続の場面では、分筆に様々なメリットがあります。
相続において、土地を分筆すれば、遺産分割がしやすくなったり、相続税の節税になったりしますが、注意点も多く、事前に信頼できる専門家に相談して進めなければなりません。