相続や不動産取引など、不動産の権利が変動するときは、正確な登記が非常に重要です。このとき、不動産登記には「表示登記」と「権利登記」があることを知り、この2つの違いを理解する必要があります。多くの方は、司法書士など専門家に依頼するでしょうが、基本は把握しておきましょう。
表示登記は、不動産の物理的な特徴を明確にし、権利登記はその不動産の所有権や抵当権といった権利関係を記録する役割を有します。そして、これらのいずれもが、不動産の正確な情報を公に示し、取引の透明性を保つためには不可欠です。それぞれ、表示登記は土地家屋調査士が、権利登記は司法書士が行うという違いもあります。
今回は、不動産登記のうち表示登記と権利登記の違いについて解説します。相続登記をスムーズに進めるためにもぜひ参考にしてください。
不動産登記の基本
はじめに、不動産登記の基本である、表示登記、権利登記という2つの用語を解説します。
表示登記とは
表示登記とは、その不動産がどのようなものであるかを表す、基本的な情報を記載した登記の部分です。不動産の物理的な特性が、表示登記に公的に記録されています。登記簿謄本のうち、表示登記をされている部分を「表題部」と呼びます。
表示登記の部分には、次の情報が含まれています。
【土地の場合】
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 原因及びその日付
【建物の場合】
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 原因及びその日付
表示登記の目的は、不動産が法的に認識され、他の不動産と識別されることであり、これによって取引の明確性が保たれます。申請には、所定の登記申請書に加え、不動産の測量図や建物の平面図などを要します。これら必要書類により、不動産の実態が登記と整合していることを証明する必要があるからです。
表示登記が必要となるのは、例えば次のケースです。
- 新築物件の建設
- 増改築
- 建物の滅失
- 土地の区画整理
- 土地の分筆や合筆
適切な表示登記がなされていないと、所有権移転や抵当権設定といった権利登記が適切に行えません。表示登記は、権利登記の大前提として、どのような不動産かを表す重要な部分だといってよいでしょう。そして、表示登記は不動産取引だけでなく、税務や裁判所などのその他の手続きにおいても、その不動産がどのような性状であるかを示す重要な役割を果たします。
権利登記とは
権利登記とは、不動産の所有権や抵当権など、権利関係を明確にするための登記の部分を指します。登記簿謄本のうち、権利登記が記載される部分を「権利部」と呼びます。権利部は「甲区」と「乙区」に分かれています。
- 甲区
所有権に関する権利の情報(所有権、所有権仮登記、差押え、仮差押えなど) - 乙区
所有権以外の権利の情報(抵当権、地上権、地役権、賃借権など)
権利登記によって、表示登記で特定された不動産を、誰が所有しているか、どのような権利が設定されているか、といったことを公的に記録することができます。そしてその記録は、その権利を第三者に対抗する意味を持ちます(登記のこの効果を「第三者対抗要件」といいます)。権利変動を対抗し、財産を失わないためにも、変動があったら速やかに登記すべきであり、この登記を担当するのが司法書士です。
権利登記の手続きは、所有権の移転や抵当権の設定時など、権利が変動したときに行われます。手続きを開始するには、登記申請書に加えて、売買契約書や抵当権設定契約書などの登記原因を証する文書が必要となります。登記はその管轄の法務局で行われます。
表示登記と権利登記の違い
次に、表示登記と権利登記の違いについて、わかりやすく解説します。
表示登記と権利登記の違いについて説明するにあたり、それぞれの目的、法的効果や、担当する専門家の種類によって区別する必要があります。
目的による違い
表示登記は、不動産の物理的な特徴を記録するためのもので、いわば不動産の「身分証」です。これにより土地や建物がどのようなものであるかを明らかにします。一方で、権利登記は、その不動産に設定された権利を公示することを役割としています。
法的効果による違い
表示登記は、不動産が新たに生まれたり、無くなったりするときに作られ、その不動産がそこにあること(もしくはないこと)を示すという法的効果があります。これに対し、権利登記は、そこに記載された権利について第三者に対抗するという重要な効果を有します。
いずれも不動産取引や相続の場面において重要なのは当然です。ただし、表示登記だけしても権利は保護されず、不動産の所有権を主張するならば、権利登記も行う必要があります。これによって、不動産取引の安全性と透明性を高めることができるからです。
登記を担当する専門家の違い
表示登記と権利登記とは、その登記を担当する専門家が異なります。いずれも登記の専門家でありながら、表示登記は土地家屋調査士、権利登記は司法書士が担当します。役割分担ははっきりしており、混同しないようにしてください。
登記の専門家としては司法書士が有名ですが、表示登記については一部の例外を除き、代理で申請することはできません。
相続問題の専門家について

不動産登記の手続きのポイント
不動産登記の手続きは、所有権の移転や権利の設定など、不動産に関する重要な変更を公的に記録するものです。これらの手続きをスムーズに進めるには以下のポイントに注意してください。
- 事前の準備
登記に必要な書類を事前に整理し、情報を正確に把握しておくのが大切です。収集しておくべきものには、権利証や固定資産税評価証明書などがあります。 - 正確な情報の提供
手続きを誤らないためには、申請書に正確な情報を記載することが大切です。専門家に依頼する場合にも、誤った情報を伝えないよう注意してください。 - 手続きの流れの理解
登記手続きは複数のステップからなるため、手続きの全体像を把握して進めないと、手続きが遅れる原因となります。
その上で、登記は自分ですることもできるものの、ミスが起こりやすくなります。スムーズに進めるには専門家に任せるのが有益です。専門家に依頼すれば、法律や制度に対する専門知識を活かし、スピーディに進められます。手続きに不慣れな人が進めるよりも時間と労力を軽減でき、また、間違いがなく進めることで、将来のトラブルを予防することができます。
専門家を選ぶ際には、その経験や専門分野、過去の実績などを確認し、信頼できるパートナーを選ぶようにしてください。
相続に強い司法書士の選び方について
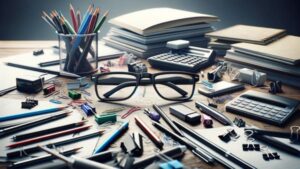
登記を要する具体例
不動産登記における表示登記と権利登記をイメージしてもらいやすくするため、特に相続のケースにおいて、どのような場面でそれぞれの登記が必要となるのか、具体例を解説します。
Aさんは生前対策として、自身が死亡した後にできるだけ争いが起こらないよう、土地を相続人の数に応じて分筆することにしました。このとき、分筆後に行うべき登記が「表示登記」です。表示登記により、分筆後の土地がそれぞれどのような内容かを公に記録し、将来のトラブルを避けられます。
相続において、遺産分割の結果、承継した不動産については速やかに相続登記をする必要があります。このときに行う登記が「権利登記」です。
まとめ
今回は、不動産登記のうち、表示登記と権利登記の違いについて解説しました。
いずれも重要であることに違いはありませんが、相続の場面でも、いずれの登記も必要となり、区別しなければならないことがあります。このとき、担当する専門家が異なる点には注意を要します。間違えず、表示登記については土地家屋調査士、権利登記については司法書士に依頼してください。
登記は、自分でもすることができますが、専門家に任せた方が手間がかからずスムーズです。確実な登記によって不動産の価値を守り、将来にわたって安心して管理できるようにしましょう。


