もし遺産が本来の相続人でない人の手に渡ってしまった場合、正当な相続人はどうやって取り返せるでしょうか。このような状況で、正規の相続人が行使できるのが「相続回復請求権」(民法884条)。この権利を行使すれば、奪われた遺産を回復できるチャンスがあります。
本解説では、相続回復請求権の意味と、この権利が認められる状況、そして遺産を取り戻すために必要な手続きを解説します。また、権利を失くしてしまわないよう時効についても説明します。なお、相続回復請求権は、多くの人から遺留分侵害額請求権と誤解されやすいですが、その違いも理解しておいてください。
相続回復請求権の理解を深めることは、もしもの時に自身の権利を守る役に立ちます。
相続回復請求権の基本
まず、相続回復請求権とはどのような意味か、その意義と、行使すべき背景や必要性を解説します。
相続は、人が死亡すると開始しますが、何らかの事情で、自分が相続できるはずの財産を好き勝手に使われてしまう場面があります。こうした侵害者に対して、相続人がその相続権を回復するときに利用するのが、相続回復請求権です。
相続回復請求権とは(民法884条)
相続回復請求権とは、相続権を侵害された相続人が,侵害されている相続権の回復を請求する権利のことです。
実際には相続人でないにもかかわらず相続人として行動する者(「表見相続人」と呼びます)が登場した場面で、正当な相続人(「真正相続人」と呼びます)が遺産の返還を求めることができる権利であり、これによって自己の相続権を回復することができます。例えば、相続人でない人が遺産を占有しているとき、この権利を行使することで占有を解き、相続人の地位を回復することができます。
民法884条は、相続回復請求権について次のように定めます。
民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
民法(e-Gov法令検索)
全く相続と関係ない人が「表見相続人」として侵害をしているケースもあれば、共同相続人の一部が、法定相続分を超えて他の相続人の権利を侵している場合もあり、いずれも、相続回復請求権の相手方となる可能性があります。
相続回復請求権は、個別の遺産に対する侵害を排除するものではありません。そうではなく、相続人ではないのに相続人として振る舞う人に対し、遺産を包括的に返還するよう求める権利です。特定の物に対する権利ではなく、その集合体としての包括的な権利なのです。
以上のように、相続回復請求権は、相続回復請求権は遺留分侵害額請求権とともに「相続人の権利を守る仕組み」と位置づけることができます。
相続回復請求権の効果
相続回復請求が認められると、請求した人が、相続開始時から相続人の地位にあったこととなり、遺産に関する権利を取得します。これによって、請求者は相手方から、遺産を引き渡してもらったり、抹消登記手続きをさせたりすることができます。
相続回復請求権は、相手方に対して包括的に遺産の返還を求めることができるので、真の相続人にとっては、より容易に目的物の回復を求められるメリットがあります。相続回復請求権なら個々の遺産を列挙し、それぞれの所有権を立証する必要がなく、相続権を証明することで足りるからです。
相続回復請求権を行使できる人とは
次に、相続回復請求権を行使できる人について、解説します。
権利を行使できる人の条件
相続回復請求権を行使できるのは、真正相続人または包括受遺者です。包括遺贈を受けた人は、相続人と同じ地位を有するため、相続人と同じく相続回復請求権を行使できます。
以下、権利を行使できる人と、そうでない人を整理します。
【相続回復請求権を行使できる人】
- 真正相続人
- その法定代理人
- 相続分の譲受人
- 包括受遺者
【相続回復請求権を行使できない人】
- 真正相続人からの転得者
- 真正相続人の相続人
一身専属権であり、特定承継人は行使できないとした裁判例(最高裁昭和32年9月19日判決)があります。また、同じく一身専属権なので、死亡により当然消滅し、相続されないと考えられています。
なお、相続回復請求権の放棄は認められていません(大審院昭和13年7月26日判決)。
相続回復請求権を活用すべき具体的なケース
相続回復請求権は、表見相続人が、真正相続人の相続権を侵害している場面、つまり具体的には、遺産である不動産を専有されてしまった場合や、所有権移転登記を勝手にされてしまったケースで活用できます。相続権が侵害されたという客観的な事実があれば足り、侵害する意思までは必要ないとされています(最高裁昭和39年2月27日判決)。
具体的に相続人の相続権が侵害されている場面としては、以下の状況が考えられます。
- 相続開始時に胎児であった者
胎児を見逃して遺産分割がされてしまっていた場合、その分割は相続人である胎児の権利を侵害するため、相続回復請求権を行使できます。 - 被相続人から遺言で認知された者(死後認知)
死後認知されたにもかかわらず、それを無視して遺産分割された場合、認知によって「子」の続柄を取得した真正相続人は、相続回復請求権を行使できます。
相続回復請求権の相手方とは
次に、相続回復請求権を行使する相手方について解説します。
相手方となる表見相続人の条件
相続回復請求権の相手方となるのは「表見相続人」、つまり、相続人を僭称する人です。表見相続人とは、例えば、次の者を指します。
相手方として判断が難しいケースもあり、以下の通り、裁判例で争いになっています。
裁判例では、表見相続人からの転得者(特定承継人)に対する請求については、884条の適用を否定しています(大審院大正5年2月8日判決)。他方で、表見相続人の相続人に対する請求については、884条の適用を認めます(大審院昭和10年4月27日判決)。
また、共同相続人が、他の相続人の持分を侵害している場合にも適用されますが、その適用範囲は限られており、「自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称する者」「相続権があると信じる合理的な理由がないのに相続人であると称し,相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者」は、本来この権利が対象とする相手方には含まれないとされています(最高裁昭和53年12月20日判決)。
表見相続人となる具体的なケース
具体的にイメージできるよう、表見相続人が出現する具体例を説明します。
【相続欠格者による侵害の例】
相続欠格の事由があるのにそれを隠して、遺産である不動産の相続登記をした場合、その相続欠格者は相続権を侵害する「表見相続人」となり、相続回復請求権の相手方になります。
【死後認知による例】
死後認知によって「子」の続柄の人が出現すると、法定相続人の範囲が変わります。その結果、死後認知が発覚するよりも前に、直系尊属や兄弟姉妹が遺産分割によって遺産を得てしまっていた場合、これらの人は「表見相続人」となり、争族回復請求権の相手方になります。
相続回復請求権の消滅時効(5年・20年)
相続回復請求権は、一定の期間がすぎると時効により消滅してしまいます。相続回復の請求権には、期限があるのです。相続回復請求権の消滅時効について、解説していきます。
時効の起算点と計算方法
相続回復請求権の時効は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から5年です(短期消滅時効)。「相続権を侵害された事実を知った時」は、自分が相続人であること、及び、相続から除外されていることを知った時と解されます(大審院明治38年9月19日判決)。短期消滅時効は、相続人の権利を早期に安定させるための定めです。権利行使をすることで、相続回復請求権の消滅時効を中断させることができます(大審院昭和7年9月22日判決)。
また、20年の長期消滅時効も定められています。20年の起算点は、相続権が侵害された事実を知っていたかどうかにかかわらず、相続開始時とされており、これは除斥期間ではなく時効期間であると判断されています(最高裁昭和23年11月6日判決)。
なお、相続回復請求をする相手方が、既に取得時効によって遺産の権利を得てしまった場合、相続回復請求権を行使できません。
最高裁昭和53年12月20日判決は、共同相続人の1人が遺産に含まれる不動産について単独名義の相続登記をしたのに対し、他の相続人が共有権に基づいて妨害排除請求をすることを認め、相続回復請求権の時効の適用はないと判断しました。
長く放置してしまった妨害を排除する必要があるために、相続回復請求権の時効後も救済した裁判例として注目されます。
時効を援用できるのは善意・無過失の表見相続人のみ
相続回復請求権には時効の定めがありますが、ただし、善意無過失の表見相続人しか時効を援用できないとされています。つまり、悪意又は有過失の表見相続人は、時効を主張できません。
例えば、自己が相続人でないことを知りながら相続人と称し、または、その者に相続権があると信じるべき合理的な理由がないのに自らを相続人であると称して、遺産を占有管理して侵害している人はそもそも時効によって保護する必要がないからです。
善意、無過失の判断は、侵害の開始時点を基準とします。つまり、侵害をした後で、自分が相続人ではない(表見相続人である)と知ったとしても、その人は時効を援用することができます。なお、善意無過失の立証責任は、権利行使をする側が負います(最高裁平成11年7月19日判決)。
共同相続人についても、本来の持分を超える部分にまで自分の権利が及ばないことを知っていたり、信じる合理的な理由のない場合にも同じく、時効の援用はできません。
相続回復請求権と遺留分侵害額請求権の違い
遺留分侵害額請求は、一定の法定相続人が、自己に認められた相続財産に対する最低限の取り分(遺留分)を侵害されときに、その相手方に遺留分相当の金銭を請求できる権利です。「相続人を保護する権利」という点で、相続回復請求権と似ていますが、全く異なるものです。
- 請求内容の違い
相続回復請求権は財産自体の返還を請求できますが、遺留分侵害額請求権が請求できるのは金銭の支払いのみです(2018年の相続法改正前は、遺留分減殺請求権は財産の返還請求も可能でした)。 - 請求主体の違い
相続回復請求権は、真正な相続人なら誰でも請求できますが、遺留分侵害額請求の主体は、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち、配偶者、子(とその代襲者)、直系尊属ですす(民法1042条1項)。
遺留分の基本について
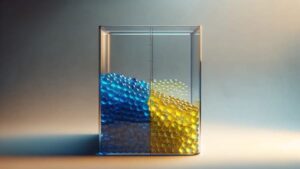
相続回復請求権の行使方法
最後に、相続回復請求権を具体的にどう行使していけばよいのか、その方法を解説します。相続回復請求権の行使方法は特に制限がなく、裁判上の行使はもちろん、裁判外での行使も可能です。
まずは裁判外で話し合う
相続権を侵害されてしまったら、いきなり裁判に持ち込むのではなく、まずは話し合いでの解決を目指します。相続回復請求権の考え方は複雑であり、裁判でも確定的な判断の少ない分野です。リスクを最小限にしたいなら、是非とも話し合いで解決したいところです。
時効の完成まで残り間もないなら、証拠を残すため内容証明で請求書を送ってください。話し合いで納得いく解決が得られるなら、合意内容も書面化しましょう。合意書は公正証書化しておくと、いざその合意が果たされなかったときに、裁判せずに強制執行することができます。
調停を申し立てる
相続回復請求事件は家庭に関する事件であり、「調停前置」の考えによってまず家事調停の申立てをしなければなりません(家事法257条1項、244条)。調停を経ないで訴えが提起された場合には、裁判所は職権で家事調停に付することになります(家事法257条2項本文)。
ただし、調停に付することが相当でないと認められるときはこの限りではないとされ(同項ただし書)、例外的に初めから訴訟をすることができる場合もあります。例えば、被告が所在不明であったり、事前交渉の経緯から調停期日に欠席することが明白であったり、合意成立の見込みがほとんどないような場合です。
訴訟を提起する
調停不成立の場合には審判には移行せず、訴訟提起するか検討することとなります。
したがって、交渉や調停でも解決の目処が立たないとき、相続回復請求権についての訴訟を提起します。訴訟は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に提起します。
遺産分割調停や審判をすることはできない
相続回復請求権の訴訟は「遺産分割調停」とは異なります。そのため、既に共同相続人との間で分割協議中でも、不当に侵害されている状態を回復するためには、交渉や訴訟によって解決していかねばなりません。
また、相続回復請求権をめぐる争いは、家庭に関する紛争ではありますが、訴訟手続によるものであり、調停が不成立となっても審判には移行しません。
遺産分割調停の手続きについて

まとめ
今回は、相続財産が侵害されてしまったときに、真正な相続人に認められる権利について、解説しました。法律の世界では、この権利を相続回復請求権と呼ぶこともあり、相続人の利益を保護するために機能します。
ただ、せっかく権利があるとはいえ、いつまでも行使せずにいると消滅時効によって消滅してしまうおそれもあります。裁判外の話し合いで解決を目指すことを優先すべきですが、思うように進まず泥沼化してしまうのも事実。特に、共同相続人間での争いはこうした傾向にあります。争いが複雑化してしまう前に弁護士に相談ください。


